| 桜田門外の変 紀州藩出身 皇女・和宮と結婚 江戸幕府第14代将軍 |
徳川家茂 | 徳川家茂 |
| 徳川吉宗 | ||
| 徳川綱吉 | ||
| 徳川家定 | ||
| 水田跡や高床式倉庫跡 軍需工場建設の際に発見 弥生時代の遺跡 静岡県静岡市の遺跡 |
登呂遺跡 | 登呂遺跡 |
| 岩宿遺跡 | ||
| 造山遺跡 | ||
| 三内丸山遺跡 | ||
| 谷口古墳 龍王崎古墳群 菜畑遺跡 吉野ヶ里遺跡 |
島根県 | 佐賀県 |
| 福岡県 | ||
| 岡山県 | ||
| 佐賀県 | ||
| 有村次左衛門 尊攘派の水戸浪士が実行 1860年に起きた事件 大老・井伊直弼を襲撃 |
応天門の変 | 桜田門外の変 |
| 蛤御門の変 | ||
| 安和の変 | ||
| 桜田門外の変 | ||
| 戦後の好景気 なべ底不況の前 1955年~1957年 初代天皇 |
神武景気 | 神武景気 |
| 特需景気 | ||
| 岩戸景気 | ||
| いざなぎ景気 | ||
| 父はヘンリー2世 プランタジネット朝の国王 第3回十字軍に参加 別名「獅子心王」 |
ジェームズ1世 | リチャード1世 |
| エリザベス1世 | ||
| チャールズ1世 | ||
| リチャード1世 | ||
| イギリスの王朝 1066年~1154年 ヘンリー1世 ウィリアム1世 |
ステュワート朝 | ノルマン朝 |
| ハノーヴァー朝 | ||
| プランタジネット朝 | ||
| ノルマン朝 | ||
| 自由民権運動最大の激化事件 首謀者は田代栄助 「困民党」を結成 1884年の現在の埼玉県で発生 |
福島事件 | 秩父事件 |
| 高田事件 | ||
| 秩父事件 | ||
| 群馬事件 | ||
| 武田二十四将の一人 築城、軍略の天才 第四次川中島の戦いで戦死 「ヤマカン」の由来とする説 |
山本勘助 | 山本勘助 |
| 小畠虎盛 | ||
| 原虎胤 | ||
| 板垣信方 | ||
| 織田信長に仕えた武将 長光寺城での瓶割り 最後は越前北ノ庄で自端 妻はお市の方 |
上杉謙信 | 柴田勝家 |
| 武田信玄 | ||
| 柴田勝家 | ||
| 織田信長 | ||
| 織田信長に仕えた武将 鉄砲の名手として名を馳せる 甲賀出身の忍者だとする説も 清洲会議には出席できず |
丹羽長秀 | 滝川一益 |
| 明智光秀 | ||
| 滝川一益 | ||
| 柴田勝家 | ||
| 約700万年前に出現 二足歩行で道具を使う アウストラロピテクス 現在のチンパンジーに近い |
新人 | 猿人 |
| 旧人 | ||
| 原人 | ||
| 猿人 | ||
| 約20万年前に現れる ジャワのソロ人 アフリカのローデシア人 ネアンデルタール人 |
旧人 | 旧人 |
| 新人 | ||
| 原人 | ||
| 猿人 | ||
| 古代ギリシャの哲学者 アレキサンダー大王の家庭教師 リュケイオンという学校を創設 プラトンの弟子 |
プラトン | アリストテレス |
| ソクラテス | ||
| アリストテレス | ||
| ディオゲネス | ||
| 古代ギリシャの哲学者 キュニコス学派 狂えるソクラテス 樽の中で暮らす |
プラトン | ディオゲネス |
| ソクラテス | ||
| アリストテレス | ||
| ディオゲネス | ||
| 著書『ソクラテスの弁明』 本名は「アリストクレス」 アトランティス大陸について著述 学園「アカデメイア」を設立 |
タレス | プラトン |
| アリストテレス | ||
| プラトン | ||
| ソクラテス | ||
| 国境を黒竜江・外興安嶺に定める ロシア側はピョートル大帝 清側は康熙帝 1689年に結ばれた対等な条約 |
イリ条約 | ネルチンスク条約 |
| 北京条約 | ||
| キャフタ条約 | ||
| ネルチンスク条約 | ||
| 長屋王 橘諸兄 道鏡 藤原不比等 |
奈良時代 | 奈良時代 |
| 大和時代 | ||
| 鎌倉時代 | ||
| 室町時代 | ||
| 洗礼名はシメオン 豊前のキリシタン大名 豊臣秀吉の参謀として活躍 通称は「官兵衛」 |
大村純忠 | 黒田如水 |
| 大友宗麟 | ||
| 黒田如水 | ||
| 有馬晴信 | ||
| 「利休七哲」の一人 名前は「重然」 豊臣家の筆頭茶人 独特の形状の茶碗 |
芝山監物 | 古田織部 |
| 古田織部 | ||
| 瀬田正忠 | ||
| 細川忠興 | ||
| 「利休七哲」の一人 小倉藩の初代藩主 茶道・三斎流の開祖といわれる 妻の洗礼名はガラシャ |
芝山監物 | 細川忠興 |
| 古田織部 | ||
| 瀬田正忠 | ||
| 細川忠興 | ||
| 西周 中村正直 福沢諭吉 森有礼 |
平民社 | 明六社 |
| 明六社 | ||
| 愛国社 | ||
| 玄洋社 | ||
| 古代の占い 『古事記』にも記載 ははかの木 鹿の肩甲骨を焼く |
太占 | 太占 |
| 盟神探湯 | ||
| 産土神 | ||
| 亀卜 | ||
| 鎌倉時代に五摂家と呼ばれる 基実に始まる 鷹司家が分かれる 後に総理大臣の文鷹を輩出 |
鷹司家 | 近衛家 |
| 一条家 | ||
| 近衛家 | ||
| 二条家 | ||
| イギリスの経済学者 大学卒業後は牧師に 社会主義思想を批判 著書『人口論』 |
マルサス | マルサス |
| ベンサム | ||
| ホッブズ | ||
| ハイデッガー | ||
| 功利主義の代表的論者 パノプティコン型監獄を考案 イギリスの法学者・哲学者 最大多数の最大幸福 |
マルサス | ベンサム |
| ベンサム | ||
| ホッブズ | ||
| ハイデッガー | ||
| 公武合体運動 1862年に起きた事件 尊攘派の水戸浪士が実行 老中・安藤信正を襲撃 |
桜田門外の変 | 坂下門外の変 |
| 坂下門外の変 | ||
| 応天門の変 | ||
| 安和の変 | ||
| 江戸時代の陽明学者 大分県の耶馬渓の命名者 息子は三樹三郎 著書『日本外史』 |
荻生徂徠 | 頼山陽 |
| 室鳩巣 | ||
| 蒲生君平 | ||
| 頼山陽 | ||
| 徳川家宣、家継の時代に活躍 幕府の将軍侍講 正徳の治をおこなう 著書『西洋紀聞』 |
新井白石 | 新井白石 |
| 阿部正弘 | ||
| 酒井忠清 | ||
| 間部詮房 | ||
| 著書『プロレゴメナ』 ドイツ観念論哲学の祖 著書『純粋理性批判』 コペルニクス的転回 |
カント | カント |
| ラッサール | ||
| フッサール | ||
| ベンサム | ||
| ドイツを中心とする宗教戦争 ボヘミアで勃発 1618年に始まる ウェストファリア条約で締結 |
七年戦争 | 三十年戦争 |
| 百年戦争 | ||
| 八十年戦争 | ||
| 三十年戦争 | ||
| 1944年10月に服毒自殺 ドイツの元陸軍元帥 アフリカ戦線で活躍 愛称は「砂漠の狐」 |
エルヴィン・ロンメル | エルヴィン・ロンメル |
| アルベルト・シュペーア | ||
| ヨーゼフ・ゲッペルス | ||
| アドルフ・アイヒマン | ||
| 初代の王はマンコ・カパック 結び縄「キープ」 首都はクスコ スペイン人ピサロに滅ぼされる |
エジプト文明 | インカ文明 |
| メソポタミア文明 | ||
| インカ文明 | ||
| マヤ文明 | ||
| 1688年~1689年 権利の章典を発布 ジェームズ2世が王位から追放 ウィリアム3世が即位 |
ロシア革命 | 名誉革命 |
| 清教徒革命 | ||
| フランス革命 | ||
| 名誉革命 | ||
| 五街道のひとつ 笹子峠 小仏峠 下諏訪 |
奥州街道 | 甲州街道 |
| 日光街道 | ||
| 東海道 | ||
| 甲州街道 | ||
| 髀肉の嘆 桃園の誓い 水魚の交わり 三顧の礼 |
韓信 | 劉備 |
| 劉邦 | ||
| 諸葛孔明 | ||
| 劉備 | ||
| 作家セルバンテスも参加 1571年 ギリシャ中部 連合艦隊がオスマン帝国を撃破 |
アクチウムの海戦 | レパントの海戦 |
| レパントの海戦 | ||
| サラミスの海戦 | ||
| ミッドウェー海戦 | ||
| ジブラルタル海峡の北西 1805年 ネルソン提督の英艦隊が勝利 ナポレオン戦争最大の海戦 |
レパントの海戦 | トラファルガーの海戦 |
| ミッドウェー海戦 | ||
| トラファルガーの海戦 | ||
| アクチウムの海戦 | ||
| 詩人アイスキュロスも参加 紀元前480年 アテネの南西 ギリシャ艦隊対ペルシャ艦隊 |
アクチウムの海戦 | サラミスの海戦 |
| レパントの海戦 | ||
| サラミスの海戦 | ||
| ミッドウェー海戦 | ||
| 戦国時代の合戦 舞台は摂津国と山城国の境 明智光秀の「三日天下」の終わり 別名「天王山の戦い」 |
桶狭間の戦い | 山崎の戦い |
| 山崎の戦い | ||
| 姉川の戦い | ||
| 厳島の戦い | ||
| 戦国時代の合戦 舞台は近江国 浅井長政・朝倉義景連合軍 織田信長 |
姉川の戦い | 姉川の戦い |
| 賤ヶ岳の戦い | ||
| 桶狭間の戦い | ||
| 三方ヶ原の戦い | ||
| イタリア出身のイエズス会員 明の時代に中国で活躍 『坤輿万国全図』を作成 中国名は利瑪竇 |
カスティリオーネ | マテオ・リッチ |
| フェルビースト | ||
| マテオ・リッチ | ||
| アダム・シャール | ||
| 兼序 盛親 国親 元親 |
長宗我部氏 | 長宗我部氏 |
| 蠣崎氏 | ||
| 島津氏 | ||
| 甲斐武田氏 | ||
| チャールズ1世誕生 細川ガラシャ死去 イギリス東インド会社設立 関ヶ原の戦い |
1604年 | 1600年 |
| 1596年 | ||
| 1600年 | ||
| 1598年 | ||
| ハルドゥーン ルシュド シーナー バットゥータ |
ウルグ | イブン |
| ニザーム | ||
| イブン | ||
| アプデュル | ||
| 幕末の四賢候 藩営工場集成館を設立 日本初の写真のモデル 薩摩藩主 |
島津斉彬 | 島津斉彬 |
| 伊達宗城 | ||
| 松平慶永 | ||
| 山内容堂 | ||
| 第41代天皇 歴史上初の太上天皇 藤原京に遷都 父は天智天皇、夫は天武天皇 |
元明天皇 | 持統天皇 |
| 皇極天皇 | ||
| 推古天皇 | ||
| 持統天皇 | ||
| 第45代天皇 文武天皇の第1皇子 国分寺・国分尼寺 東大寺の大仏 |
聖武天皇 | 聖武天皇 |
| 元正天皇 | ||
| 天武天皇 | ||
| 天智天皇 | ||
| 文武天皇の第1皇子 墾田永年私財法を制定 国分寺・国分尼寺 東大寺の大仏 |
聖武天皇 | 聖武天皇 |
| 元明天皇 | ||
| 天武天皇 | ||
| 天智天皇 | ||
| 第52代天皇 父は桓武天皇 平城天皇の弟 三筆の一人 |
白河天皇 | 嵯峨天皇 |
| 村上天皇 | ||
| 嵯峨天皇 | ||
| 醍醐天皇 | ||
| 第56代天皇 名は惟仁 藤原良房が摂政に 源氏の祖 |
宇多天皇 | 清和天皇 |
| 陽成天皇 | ||
| 清和天皇 | ||
| 仁明天皇 | ||
| 第72代天皇 北面の武士を創設 賀茂河の水、双六の賽、山法師 史上初めて院政を行う |
白河天皇 | 白河天皇 |
| 村上天皇 | ||
| 嵯峨天皇 | ||
| 醍醐天皇 | ||
| 第81代天皇 母は建礼門院徳子 歴代最年少の8歳で崩御 壇ノ浦の戦い |
白河天皇 | 安徳天皇 |
| 後白河天皇 | ||
| 後鳥羽天皇 | ||
| 安徳天皇 | ||
| 第82代天皇 父は高倉天皇 『新古今和歌集』の編纂を命じる 承久の乱を起こす |
白河天皇 | 後鳥羽天皇 |
| 後白河天皇 | ||
| 後鳥羽天皇 | ||
| 醍醐天皇 | ||
| 第117代天皇 江戸時代の天皇 桃園天皇崩御後に即位 現時点で最後の女性天皇 |
後桜町天皇 | 後桜町天皇 |
| 元正天皇 | ||
| 明正天皇 | ||
| 元明天皇 | ||
| 第121代天皇 名は統仁(おさひと) 平安神宮の祭神 妹和宮の降嫁に同意 |
孝明天皇 | 孝明天皇 |
| 桃園天皇 | ||
| 桜町天皇 | ||
| 光格天皇 | ||
| 平安時代の天皇 宇多天皇の第1皇子 菅原道真を右大臣に登用 延喜の治 |
白河天皇 | 醍醐天皇 |
| 村上天皇 | ||
| 嵯峨天皇 | ||
| 醍醐天皇 | ||
| 庚午年籍 近江大津宮 漏刻 中大兄皇子 |
桓武天皇 | 天武天皇 |
| 天武天皇 | ||
| 天智天皇 | ||
| 聖武天皇 | ||
| 健児(こんでい)の制を実施 坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命 784年、長岡京に遷都 794年、平安京に遷都 |
桓武天皇 | 桓武天皇 |
| 天武天皇 | ||
| 天智天皇 | ||
| 聖武天皇 | ||
| 人返しの法 株仲間の解散 上知令 水野忠邦 |
寛政の改革 | 天保の改革 |
| 天保の改革 | ||
| 聖徳の治 | ||
| 享保の改革 | ||
| 天下三名槍の一つ 作者は藤原正真 全長4m以上の長槍 本多忠勝の愛槍 |
蜻蛉切 | 蜻蛉切 |
| 日本号 | ||
| 雷切 | ||
| 籠釣瓶 | ||
| 天下五剣のうちの一つ 元々は足利将軍家の家宝 後に前田家の家宝に 作者は典太光世 |
蜻蛉切 | 大典太 |
| 日本号 | ||
| 大典太 | ||
| 雷切 | ||
| 天下五剣の一つ 作者は大原安綱 津山松平家の家宝 源頼光が怪物退治に使用した伝説 |
童子切 | 童子切 |
| 鬼丸 | ||
| 数珠丸 | ||
| 三日月宗近 | ||
| 豊臣秀吉の五大老のひとり 厳島の戦いなどで水軍を指揮 秀吉より1年早く死去 毛利元就の三男 |
加藤清正 | 小早川隆景 |
| 小早川隆景 | ||
| 宇喜多秀家 | ||
| 福島正則 | ||
| イギリスの哲学者 無神論者として弾圧される 万人の万人に対する闘争 著書『リヴァイアサン』 |
マルサス | ホップズ |
| ケインズ | ||
| ホップズ | ||
| ハイデッガー | ||
| 万暦帝 建文帝 洪武帝 永楽帝 |
唐 | 明 |
| 随 | ||
| 宋 | ||
| 明 | ||
| 袁帝 穆宗 徳宗 玄宗 |
唐 | 唐 |
| 随 | ||
| 宋 | ||
| 明 | ||
| ルーズベルト チャーチル 蒋介石 1943年11月 |
カサブランカ会談 | カイロ会談 |
| テヘラン会談 | ||
| カイロ会談 | ||
| ヤルタ会談 | ||
| 奈良県明日香村 円墳 極彩色の壁画 1972年に発掘 |
岩屋山古墳 | 高松塚古墳 |
| 石舞台古墳 | ||
| 高松塚古墳 | ||
| キトラ古墳 | ||
| 幕末の長州藩士 松下村塾に学ぶ 吉田松陰の妹婿 禁門の変で敗れて自刃 |
三吉慎蔵 | 久坂玄瑞 |
| 吉田稔麿 | ||
| 大楽源太郎 | ||
| 久坂玄瑞 | ||
| 現在の岐阜県大垣市に建設 木下藤吉郎が築城 蜂須賀小六が協力 「一夜城」の伝説 |
備中高松城 | 墨俣城 |
| 稲葉山城 | ||
| 墨俣城 | ||
| 淀城 | ||
| 日本初の条坊制 奈良時代の都 持統天皇が遷都 現在の奈良県橿原市 |
福原京 | 藤原京 |
| 平城京 | ||
| 藤原京 | ||
| 長岡京 | ||
| 平安時代の都 現在の兵庫県神戸市 平清盛 1180年の一年のみ |
福原京 | 福原京 |
| 平城京 | ||
| 藤原京 | ||
| 長岡京 | ||
| 共和党出身のアメリカ大統領 カリブ海に「棍棒外交」を展開 ポーツマス条約 テディベアの名前の由来 |
ウィリアム・マッキンレー | セオドア・ルーズベルト |
| ウィリアム・タフト | ||
| ウッドロウ・ウィルソン | ||
| セオドア・ルーズベルト | ||
| 1937年 7月7日 北京の郊外 日中戦争の発端 |
ノモンハン事件 | 虚構橋事件 |
| 張鼓峰事件 | ||
| 柳条湖事件 | ||
| 虚構橋事件 | ||
| 1939年 ハルハ河戦争 満州とモンゴルの国境 日本軍がソ連軍に敗退 |
ドレフュス事件 | ノモンハン事件 |
| 盧溝橋事件 | ||
| 柳条湖事件 | ||
| ノモンハン事件 | ||
| 十三人の合議制の一人 後鳥羽上皇より追討の宣旨 仲恭天皇の皇位を廃する 鎌倉幕府の第2代執権 |
二階堂行政 | 北条義時 |
| 北条義時 | ||
| 梶原景時 | ||
| 阿野全成 | ||
| 異国警固番役を設置 二月騒動 2度の元寇を退ける 鎌倉幕府第8代執権 |
北条時宗 | 北条時宗 |
| 北条時頼 | ||
| 北条時政 | ||
| 北条義時 | ||
| バルラス部族の出身 チンギス・ハンの子孫と自称 別名はタメルラン 1370年に帝国を建国 |
ティムール | ティムール |
| オゴタイ | ||
| アクバル | ||
| チャガタイ | ||
| 斎藤実 米内光政 原敬 鈴木善幸 |
山口県 | 岩手県 |
| 岩手県 | ||
| 静岡県 | ||
| 広島県 | ||
| 歴史上の名言 ジュリアス・シーザー ゼラの戦い VENI、VIDI、VIGI |
ローマは一日にしてならず | 来た、見た、勝った |
| サイは投げられた | ||
| ブルータス、お前もか | ||
| 来た、見た、勝った | ||
| 薩摩藩出身の首相 海軍大将 シーメンス事件で総辞職 虎ノ門事件で総辞職 |
西園寺公望 | 山本権兵衛 |
| 黒田清隆 | ||
| 山本権兵衛 | ||
| 桂太郎 | ||
| 暗殺された大統領 暗殺犯はチョルゴッシュ 20世紀最初の大統領 北米最高峰デナリ山の別名 |
ケネディ | マッキンリー |
| マッキンリー | ||
| ガーフィールド | ||
| リンカーン | ||
| 拷問の一種 鼠小僧が受けた拷問 罪人の肌を刃物で傷つける 傷口に塩を塗り込む |
塩責め | 塩責め |
| 海老責め | ||
| 算盤責め | ||
| 笞打ち | ||
| 1953年ソ連の最高指導者に ファーストネームはニキータ 冷戦の「雪どけ」に尽力 スターリン批判 |
ブレジネフ | フルシチョフ |
| マレンコフ | ||
| コスイギン | ||
| フルシチョフ | ||
| 江戸時代の旗本 一心太助 家康・秀忠・家光に仕える 天下の御意見番 |
柳沢吉保 | 大久保彦左衛門 |
| 新井白石 | ||
| 一心太助 | ||
| 大久保彦左衛門 | ||
| 十手術の達人 当理流 吉岡憲法と試合 宮本武蔵の父 |
新免無二斎 | 新免無二斎 |
| 伊藤一刀斎 | ||
| 松本備前守 | ||
| 斎藤伝鬼房 | ||
| 三島神社の瓶割刀を授かる 弟子に小野善鬼、小野忠明 秘太刀「払捨刀」 一刀流剣術の祖 |
新免無二斎 | 伊藤一刀斎 |
| 伊藤一刀斎 | ||
| 松本備前守 | ||
| 斎藤伝鬼房 | ||
| 明暗 天蓋 普化宗 尺八 |
修行僧 | 虚無僧 |
| 僧兵 | ||
| 雲水 | ||
| 虚無僧 | ||
| 考案者は佐藤新助 大仏銭 文銭 銭形平次の投げ銭 |
寛平大宝 | 寛永通宝 |
| 文久永宝 | ||
| 寛永通宝 | ||
| 和同開珎 | ||
| 1328年~1589年 フランスの王朝 フィリップ6世 アンリ3世 |
ランカスター朝 | ヴァロワ朝 |
| ヨーク朝 | ||
| ヴァロワ朝 | ||
| カペー朝 | ||
| 1921年に結成された政党 党歌は『ジョヴィネッツァ』 バドリオ政権が解散させる ムッソリーニが率いる |
ファランヘ党 | ファシスト党 |
| ファシスト党 | ||
| 青年イタリア党 | ||
| ナチス党 | ||
| フランシスコ・ミランダ トゥサン・ルーベルチュール サン・マルティン シモン・ボリーバル |
ラテンアメリカ | ラテンアメリカ |
| 東南アジア | ||
| オーストラリア | ||
| アフリカ | ||
| 幕末の思想家 妻は勝海舟の妹 東洋道徳、西洋芸術 『海防八策』『急務十事』 |
吉田松陰 | 佐久間象山 |
| 佐久間象山 | ||
| 小林虎三郎 | ||
| 大村益次郎 | ||
| 延喜・天暦の治が理想 二条河原落書 2年半で崩壊 後醍醐天皇 |
安政の大獄 | 建武の新政 |
| 建武の新政 | ||
| 大化の改新 | ||
| 明暦の大火 | ||
| 1356年に完成 イスラム世界の重要な資料 イブン・バツータ アジア・アフリカ・ヨーロッパ |
東方見聞録 | 三大陸周遊記 |
| 三大陸周遊記 | ||
| 西遊録 | ||
| ガリバー旅行記 | ||
| 1826年の独立記念日に死去 アメリカ独立宣言の起草者の一人 アメリカ合衆国初代国務長官 アメリカ合衆国第3代大統領 |
ウィルソン | ジェファーソン |
| セオドア・ルーズベルト | ||
| ジェファーソン | ||
| ワシントン | ||
| 42歳の若さで大統領に就任 日露戦争の和平交渉に尽力 アメリカ合衆国第26代大統領 「テディ・ベア」の名前の由来 |
J・F・ケネディ | セオドア・ルーズベルト |
| セオドア・ルーズベルト | ||
| フランクリン・ルーズベルト | ||
| ジェファーソン | ||
| 米史上で唯一、4選された大統領 カイロ会談・ヤルタ会談に参加 アメリカ合衆国第32代大統領 ニューディール政策 |
J・F・ケネディ | フランクリン・ルーズベルト |
| セオドア・ルーズベルト | ||
| フランクリン・ルーズベルト | ||
| ジェファーソン | ||
| 小説『阿部一族』の舞台 細川氏の居城 西南戦争では籠城戦 別名は銀杏城 |
犬山城 | 熊本城 |
| 丸岡城 | ||
| 熊本城 | ||
| 彦根城 | ||
| フランク王国の王朝 ルネサンス ピピンの寄進 カール大帝の活躍 |
カロリング朝 | カロリング朝 |
| メロヴィング朝 | ||
| カペー朝 | ||
| ヴァロワ朝 | ||
| フランク国王 トランプのキングのモデル ローランの歌 西ローマ帝国を復興 |
ロタール1世 | カール大帝 |
| ルートヴィヒ2世 | ||
| カール大帝 | ||
| ピピン | ||
| 英・ビクトリア時代の首相 命日は「桜草忌」 インド帝国の樹立 スエズ運河の買収 |
ソールズベリ | ディズレーリ |
| パーマストン | ||
| ディズレーリ | ||
| グラッドストン | ||
| イギリスの政治家 アイルランド問題の解決 4度首相を務めた 光栄ある孤立 |
ソールズベリ | グラッドストン |
| パーマストン | ||
| ディズレーリ | ||
| グラッドストン | ||
| プロイセンの国王 啓蒙絶対君主の典型 君主は国家第一の下僕 サンスーシ宮殿 |
ヨーゼフ2世 | フリードリヒ2世 |
| フランツ1世 | ||
| フリードリヒ1世 | ||
| フリードリヒ2世 | ||
| 明六社を設立した政治家 国枠主義者・西野文太郎に暗殺 港区三田の坂の名前になっている 初代の文部大臣 |
西周 | 森有礼 |
| 福沢諭吉 | ||
| 加藤弘之 | ||
| 森有礼 | ||
| 自らを「カンガ人」と呼んだ ウル、ウルクなどの都市国家 ジッグラト、楔型文字 どこから来たのか謎の民族 |
アラム人 | シュメール人 |
| アッカド人 | ||
| シュメール人 | ||
| フェニキア人 | ||
| テューダー朝最後の君主 母はアン・ブーリン アルマダの海戦で勝利 別名「バージンクイーン」 |
アン女王 | エリザベス1世 |
| エリザベス1世 | ||
| メアリー1世 | ||
| メアリー2世 | ||
| 幕末期の土佐藩士 薩長同盟の実現に尽力 近江屋事件で暗殺 陸援隊の創設者 |
近藤長二郎 | 中岡慎太郎 |
| 池内蔵太 | ||
| 中岡慎太郎 | ||
| 武市瑞山 | ||
| 金泳三 ピアース 足利義栄 徳川家茂 |
11代 | 14代 |
| 15代 | ||
| 14代 | ||
| 12代 | ||
| 獄中で大逆事件を免れる サンディカリズムを唱える 月刊『平民新聞』を創刊 憲兵大尉・甘粕正彦により暗殺 |
大杉栄 | 大杉栄 |
| 幸徳秋水 | ||
| 片山潜 | ||
| 賀川豊彦 | ||
| アナーキストを弾圧 明治時代末期の事件 明治天皇暗殺疑惑 幸徳秋水らが死刑に |
森戸事件 | 大逆事件 |
| 十月事件 | ||
| 大逆事件 | ||
| 大津事件 | ||
| 「天応」と「大同」の間の元号 坂上田村麻呂が蝦夷地を征討 平安京への遷都 最澄が創建した寺の名前 |
貞観 | 延暦 |
| 弘仁 | ||
| 天慶 | ||
| 延暦 | ||
| ローマ帝国第5代皇帝 セネカが家庭教師 母はアグリッピナ 暴君として有名 |
ウェスパシアヌス | ネロ |
| ネロ | ||
| ティベリウス | ||
| ティトゥス | ||
| 今川氏の府中 島津氏の鹿児島 大内氏の山口 北条氏の小田原 |
寺内町 | 城下町 |
| 宿場町 | ||
| 門前町 | ||
| 城下町 | ||
| ガラス工芸ではエミール・ガレ 絵画ではアルフォンス・ミュシャ 19世紀末ヨーロッパで流行 フランス語で「新しい芸術」 |
ダダイズム | アール・ヌーボー |
| アール・ヌーボー | ||
| ガンダーラ美術 | ||
| ルネサンス | ||
| 立憲政友会の創立に参加 日本初の本格的政党内閣を組織 1921年に東京駅で暗殺される 愛称は「平民宰相」 |
加藤友三郎 | 原敬 |
| 原敬 | ||
| 寺内正毅 | ||
| 桂太郎 | ||
| 海難事故にあい漂流 エカチェリーナ2世に謁見 ラクスマンにより伴い帰国 北槎聞略 |
大黒屋光太夫 | 大黒屋光太夫 |
| ジョセフ彦 | ||
| 高田屋嘉兵衛 | ||
| ジョン万次郎 | ||
| 剣の流派 棒術 開祖は近藤内蔵之助 近藤勇 |
神道無念流 | 天然理心流 |
| 示現流 | ||
| 二天一流 | ||
| 天然理心流 | ||
| キリスト教が題材 堕天使ルシファー アダムとイブも登場 ジョン・ミルトンの小説 |
学問のすすめ | 失楽園 |
| 西洋の没落 | ||
| 失楽園 | ||
| 資本論 | ||
| Our American Cousin 舞台はワシントンD.C. 犯人はジョン・ブース フォード劇場で発生 |
キング牧師の暗殺 | リンカーンの暗殺 |
| マルコムXの暗殺 | ||
| リンカーンの暗殺 | ||
| ジョン・F・ケネディの暗殺 | ||
| 頭を撃たれて即死 犯人はロランド・ガルマン 1983年8月21日 舞台はマニラ国際空港 |
キング牧師の暗殺 | ベニグノ・アキノの暗殺 |
| マルコムXの暗殺 | ||
| ベニグノ・アキノの暗殺 | ||
| ロバート・ケネディの暗殺 | ||
| 砂沢遺跡 垂柳遺跡 亀ヶ岡遺跡 三内丸山遺跡 |
宮城県 | 青森県 |
| 秋田県 | ||
| 青森県 | ||
| 福島県 | ||
| 池上曽根遺跡 心合寺山古墳 誉田山古墳 大仙陵古墳 |
青森県 | 大阪府 |
| 北海道 | ||
| 大阪府 | ||
| 愛知県 | ||
| カリンバ遺跡 垣ノ島遺跡 忍路環状列石 常呂遺跡 |
青森県 | 北海道 |
| 北海道 | ||
| 大阪府 | ||
| 愛知県 | ||
| 蜆塚遺跡 和田岡古墳群 御厨古墳群 登呂遺跡 |
愛知県 | 静岡県 |
| 北海道 | ||
| 静岡県 | ||
| 青森県 | ||
| 宮崎県出身の外交官 ハーバード大学への第1回留学生 ポーツマス条約に調印 関税自主権を回復 |
青木周蔵 | 小村寿太郎 |
| 岩倉具視 | ||
| 小村寿太郎 | ||
| 寺島宗則 | ||
| 和歌山県にあった城 羽柴秀吉が築城 別名「虎伏城」 紀州徳川家の居城 |
太田城 | 和歌山城 |
| 和歌山城 | ||
| 信貴山城 | ||
| 高取城 | ||
| 第1次はパレスチナ戦争 第2次はスエズ戦争 第3次は6日戦争 第4次は10月戦争 |
朝鮮戦争 | 中東戦争 |
| アロー戦争 | ||
| 湾岸戦争 | ||
| 中東戦争 | ||
| 三好長慶の家臣 上泉伊勢守信綱の弟子 石舟斎 柳生新陰流を創始 |
塚原卜伝 | 柳生宗厳 |
| 小野忠明 | ||
| 柳生宗厳 | ||
| 東郷重位 | ||
| ネムルット・ダー ハットゥシャシュ カッパドキア トロイ遺跡 |
イラク | トルコ |
| トルコ | ||
| レバノン | ||
| イラン | ||
| パサルガダエ チョガ・ザンビール ベヒストゥン碑文 ペルセポリス遺跡 |
イラク | イラン |
| トルコ | ||
| レバノン | ||
| イラン | ||
| ネルチンスク条約を結ぶ 三藩を廃止 清の第4代皇帝 有名な字典を編纂 |
光緒帝 | 康熙帝 |
| 乾隆帝 | ||
| 雍正帝 | ||
| 康熙帝 | ||
| 邪馬台国の都とする説も 弥生時代の遺跡 古代史ブームを巻き起こす 佐賀県神埼市にある遺跡 |
荒神谷遺跡 | 吉野ヶ里遺跡 |
| 吉野ヶ里遺跡 | ||
| 纒向遺跡 | ||
| 三内丸山遺跡 | ||
| 松尾伝蔵 斎藤実 岡田啓介 高橋是清 |
五・一五事件 | 二・二六事件 |
| 十月事件 | ||
| 二・二六事件 | ||
| 三月事件 | ||
| 清が結んだ条約 甲申事変後の1885年締結 清仏戦争後の1885年締結 アロー戦争後の1858年締結 |
天津条約 | 天津条約 |
| 上海条約 | ||
| 重慶条約 | ||
| 北京条約 | ||
| 堀田正俊 酒井忠勝 井伊直幸 井伊直弼 |
大目付 | 大老 |
| 若年奇 | ||
| 側用人 | ||
| 大老 | ||
| ウィーン会議の出席者 神聖同盟を提唱 アウステルリッツの戦いで敗北 ロシアの皇帝 |
ハルデンベルク | アレクサンドル1世 |
| アレクサンドル1世 | ||
| カッスルレー | ||
| ネッセルローデ | ||
| ○微中台 ○衣事件 冠衣十二階では最上位 ○禁城 |
紫 | 紫 |
| 黄 | ||
| 赤 | ||
| 黒 | ||
| レイテ沖海戦で沈没 日本が建造した最後の戦艦 軍艦史上最多の攻撃を受ける 大和型戦艦の2番艦 |
武蔵 | 武蔵 |
| 山城 | ||
| 霧島 | ||
| 長門 | ||
| ウィーン会議の出席者 ナポレオンとの戦いに惨敗 「不定詞王」とあだ名される プロイセンの国王 |
カッスルレー | フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 |
| フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 | ||
| ネッセルローデ | ||
| ハルデンベルク | ||
| 1815年 主戦場はラ・ベル・アリアンス ウェリントンが勝利 ナポレオンの百日天下に終止符 |
ワーテルローの戦い | ワーテルローの戦い |
| ヴァルミーの戦い | ||
| アウステルリッツの戦い | ||
| イエナの戦い | ||
| ウィーン会議の出席者 トーリー党内閣の首相を務める ベートーベンの楽曲の題材 ワーテルローでナポレオンを撃破 |
ウェリントン | ウェリントン |
| メッテルニヒ | ||
| ハルデンベルク | ||
| カッスルレー | ||
| 戦国時代の兵器 澤瀉(おもだか) 十文字 笹穂 |
鉄砲 | 槍 |
| 弓 | ||
| 槍 | ||
| 薙刀 | ||
| 一番出来のよい答案は「圧巻」 秀才、進士、明経などの科目 中国の官吏登用制度 隋の時代から清の時代まで |
郷挙里選 | 科挙 |
| 九品官人法 | ||
| 猛安・謀克 | ||
| 科挙 | ||
| バルキシメト シウダー・グアヤナ マラカイボ カラカス |
キューバ | ベネズエラ |
| ベネズエラ | ||
| ウルグアイ | ||
| パラグアイ | ||
| 京都の三条木屋町 2009年、跡地に居酒屋が開業 主の惣兵衛は獄中で病死 新選組が尊王攘夷派を襲撃 |
寺田屋 | 池田屋 |
| 松坂屋 | ||
| 池田屋 | ||
| 近江屋 | ||
| 1922年に発見 「死者の丘」の意味 インダス川下流のシンド地方 インダス文明の遺跡 |
アンコール・ワット | モヘンジョ・ダロ |
| ボロブドゥール | ||
| モヘンジョ・ダロ | ||
| アジャンター石窟寺院 | ||
| 山濤 阮咸 阮籍 魏・普の時代における七人 |
賤ヶ岳の七本槍 | 竹林の七賢 |
| 全真教の七真人 | ||
| 竹林の七賢 | ||
| 浄土真宗の七高僧 | ||
| 二十四孝 親孝行 孔門十哲の一人 驪興閔氏の始祖 |
陸績 | 閔子騫 |
| 孟宗 | ||
| 閔子騫 | ||
| 朱寿昌 | ||
| 二十四孝 時は恭武 親孝行 竹の名前 |
唐夫人 | 孟宗 |
| 朱寿昌 | ||
| 孟宗 | ||
| 呉猛 | ||
| 東北地方の戦国武将 石田三成の次男・重成を保護する 南部家の内紛に乗じて独立 弘前城の完成を見ないまま死去 |
津軽為信 | 津軽為信 |
| 最上義光 | ||
| 戸沢盛安 | ||
| 蘆名盛氏 | ||
| 東北地方の戦国武将 人取橋の戦いなどで活躍 通称は小十郎 伊達政宗を幼少期から支える |
津軽為信 | 片倉景綱 |
| 最上義光 | ||
| 片倉景綱 | ||
| 蘆名盛氏 | ||
| 戦国時代の真田家の武将 関ヶ原の戦いでは東軍につく 『真田丸』では大泉洋が演じる 昌幸の嫡男、幸村の兄 |
真田信之 | 真田信之 |
| 真田昌輝 | ||
| 真田昌幸 | ||
| 真田信尹 | ||
| 武田二十四将の一人 上田合戦で徳川軍を撃退 表裏比興の者 幸隆の三男、幸村の父 |
真田昌幸 | 真田昌幸 |
| 横田高松 | ||
| 曽根昌世 | ||
| 高坂昌信 | ||
| 周布政之助 入江久一 来島又兵衛 久坂玄瑞 |
会津藩士 | 長州藩士 |
| 土佐藩士 | ||
| 薩摩藩士 | ||
| 長州藩士 | ||
| 池内蔵太 沢村惣之丞 福岡孝悌 岡田以蔵 |
会津藩士 | 土佐藩士 |
| 土佐藩士 | ||
| 薩摩藩士 | ||
| 長州藩士 | ||
| 幕末の人斬り 土佐藩士 武市瑞山に師事 勝海舟の護衛をしたことも |
田中新兵衛 | 岡田以蔵 |
| 桐野利秋 | ||
| 河上彦斎 | ||
| 岡田以蔵 | ||
| ネブカドネザル2世の遺構 紀元前7世紀~6世紀に建造 イランの遺跡 空中庭園の伝説 |
パルミラ遺跡 | バビロン遺跡 |
| バビロン遺跡 | ||
| ウル遺跡 | ||
| バールベック遺跡 | ||
| バーンチエン遺跡 プラ・パトムチェーディー ワット・ポー アユタヤ遺跡 |
スリランカ | タイ |
| パキスタン | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| プランバナン寺院群 ウルン・ダヌ・バトゥール寺院 サンギラン初期人類遺跡 ボロブドゥール寺院 |
スリランカ | インドネシア |
| パキスタン | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| 室町時代の四職の一つ 明徳の乱を起こした「満幸」 別名「六分一殿」 応仁の乱の西軍総大将「宗全」 |
一色氏 | 山名氏 |
| 赤松氏 | ||
| 京極氏 | ||
| 山名氏 | ||
| 京都府にあった城 羽柴秀吉が一時期居城に 羽柴秀吉と明智光秀の戦い 別名「天王山城」 |
福知山城 | 山崎城 |
| 信貴山城 | ||
| 山崎城 | ||
| 小谷城 | ||
| 解体後は名古屋城の建材に 斯波義重が築城 織田信長の居城 信長の死後に会議 |
清州城 | 清州城 |
| 駿府城 | ||
| 岩村城 | ||
| 長篠城 | ||
| 別名は「府中城」 藤堂高虎による輪郭式縄張 徳川家康が亡くなった場所 静岡市にあった城 |
清州城 | 駿府城 |
| 駿府城 | ||
| 岩村城 | ||
| 長篠城 | ||
| 別名「沈み城」 村中城を改修したもの 鍋島直茂が築城 佐賀城にあった城 |
飫肥城 | 佐賀城 |
| 佐賀城 | ||
| 名護屋城 | ||
| 府内城 | ||
| 別名は「森岳城」 石高に対し分不相応な豪華さ 松倉重政が築城 長崎県にあった城 |
飫肥城 | 島原城 |
| 島原城 | ||
| 平戸城 | ||
| 府内城 | ||
| 蛭子山古墳 私市円山古墳 蛇塚古墳 伏見桃山陵 |
大阪府 | 京都府 |
| 愛知県 | ||
| 京都府 | ||
| 群馬県 | ||
| 泳ぎの名手 馬を巡って源頼政の子と争いに 安徳天皇の父親という説も 父親は平清盛 |
源範頼 | 平宗盛 |
| 阿野全成 | ||
| 梶原景時 | ||
| 平宗盛 | ||
| 保元の乱で勝利 後白河法皇と対立 武士としては初の太政大臣 史上初の武家政権を樹立 |
平清盛 | 平清盛 |
| 平時忠 | ||
| 平景清 | ||
| 平正盛 | ||
| 藤内光澄に討たれる 別名「清水冠者」 妻は源頼朝の娘・大姫 父は木曽義仲 |
上総広帯 | 木曽義高 |
| 仁田忠常 | ||
| 武田信義 | ||
| 木曽義高 | ||
| 後鳥羽天皇を幽閉し征東大将軍に 別名「朝日将軍」 源頼朝の従兄弟 巴御前と恋仲 |
工藤祐経 | 木曽義仲 |
| 仁田忠常 | ||
| 上総広常 | ||
| 木曽義仲 | ||
| 国会主義団体の一つ 1901年に設立 内田良平らが結成 ロシアと清の間にある川 |
黒竜会 | 黒竜会 |
| 明六社 | ||
| 玄洋社 | ||
| 血盟団 | ||
| 大日本帝国海軍の軍人 皇国の興廃この一戦にあり 別名「東洋のネルソン」 日露戦争の連合艦隊司令長官 |
秋山真之 | 東郷平八郎 |
| 石原莞爾 | ||
| 山下奉文 | ||
| 東郷平八郎 | ||
| 本日休診 ジョン寓次郎漂流記 黒い雨 山椒魚 |
国木田独歩 | 井伏鱒二 |
| 井伏鱒二 | ||
| 山本有三 | ||
| 田山花袋 | ||
| 生命の冠 真実一路 女の一生 路傍の石 |
長塚節 | 山本有三 |
| 井伏鱒二 | ||
| 山本有三 | ||
| 田山花袋 | ||
| クレス・オルデンバーグ ジョージ・シーガル ロイ・リキテンスタイン アンディー・ウォーホル |
アースワーク | ポップ・アート |
| アクション・ペインティング | ||
| デ・ステイル | ||
| ポップ・アート | ||
| ヴィラ・ジュリア博物館 ボルゲーゼ美術館 アカデミア美術館 ウフィツィ美術館 |
フランス | イタリア |
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| スペイン | ||
| ベラスケス ゴヤ ダリ ピカソ |
イタリア | スペイン |
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| アメリカ | ||
| 元「MI6」の諜報部員 ラッフルズホテル 人間の絆 月と六ペンス |
オスカー・ワイルド | サマセット・モーム |
| サマセット・モーム | ||
| ディケンズ | ||
| スチーブンソン | ||
| ウィンダミア夫人の扇 サロメ ドリアン・グレイの肖像 幸福の王子 |
オスカー・ワイルド | オスカー・ワイルド |
| サマセット・モーム | ||
| ディケンズ | ||
| スチーブンソン | ||
| 大いなる遺産 オリバー・ツイスト クリスマス・キャロル 二都物語 |
オスカー・ワイルド | ディケンズ |
| サマセット・モーム | ||
| ディケンズ | ||
| スチーブンソン | ||
| 『小倉百人一首』8首目の詠み人 平安時代初期の僧侶 宇治山に住んでいた 六歌仙のひとり |
西行法師 | 喜撰法師 |
| 能因法師 | ||
| 喜撰法師 | ||
| 寂蓮法師 | ||
| 出家前は北面の武士 和歌四天王のひとり 鎌倉時代の作家・歌人 代表作『徒然草』 |
西行法師 | 兼好法師 |
| 能因法師 | ||
| 喜撰法師 | ||
| 兼好法師 | ||
| 元は北面の武士 俗名は佐藤義清 平安時代の歌人 歌集『山家集』 |
西行法師 | 西行法師 |
| 能因法師 | ||
| 喜撰法師 | ||
| 寂蓮法師 | ||
| ヘミングウェイ フォークナー シンクレア・ルイス スタインベック |
桂冠詩人 | ノーベル賞作家 |
| ノーベル賞作家 | ||
| ロスト・ジェネレーション | ||
| 空想社会主義 | ||
| 版元の蔦谷重三郎とのコンビ 江戸時代の浮世画家 役者の大首絵を描く その正体は不明 |
鈴木春信 | 東洲斎写楽 |
| 喜多川歌麿 | ||
| 東洲斎写楽 | ||
| 安藤広重 | ||
| 父は火消し同心 1858年にコレラで死去 木曽街道六十九次 代表作『東海道五十三次』 |
鈴木春信 | 安藤広重 |
| 喜多川歌麿 | ||
| 東洲斎写楽 | ||
| 安藤広重 | ||
| 背景は日清戦争 結核が原因で分かれる男女 川島武男と片岡浪子 作者は徳富蘆花 |
不如帰 | 不如帰 |
| 浮雲 | ||
| 高野聖 | ||
| 野菊の墓 | ||
| 日本の近代小説の先駆け 言文一致の文体 主人公は内海文三 作者は二葉亭四迷 |
不如帰 | 浮雲 |
| 浮雲 | ||
| 高野聖 | ||
| 野菊の墓 | ||
| 1906年「ホトトギス」に発表 松田聖子主演で映画化 主人公は政夫と民子 作者は伊藤左千夫 |
不如帰 | 野菊の墓 |
| 浮雲 | ||
| 高野聖 | ||
| 野菊の墓 | ||
| 鎌研坂、小天温泉、峠の茶屋 ヒロインは那美 主人公は青年画家 智に働けば角が立つ |
明暗 | 草枕 |
| 草枕 | ||
| それから | ||
| 門 | ||
| アメリカの女流作家 ローリーの娘 秘密の花園 『小公子』『小公女』 |
パール・バック | バーネット |
| ガートルード・スタイン | ||
| バーネット | ||
| ルイザ・オルコット | ||
| 輝ける闇 玉、砕ける 『裸の王様』で芥川賞受賞 オーパ! |
開高健 | 開高健 |
| 五木寛之 | ||
| 大江健三郎 | ||
| 谷崎潤一郎 | ||
| 芦屋市に記念館 『卍』『蓼食う虫』 『痴人の愛』『春琴抄』 『細雪』『刺青』 |
開高健 | 谷崎潤一郎 |
| 五木寛之 | ||
| 大江健三郎 | ||
| 谷崎潤一郎 | ||
| 世間知らず 友情 お目出たき人 「新しき村」を建設 |
永井荷風 | 武者小路実篤 |
| 堀辰雄 | ||
| 下村湖人 | ||
| 武者小路実篤 | ||
| 19世紀フランスの作家 ベラミ 脂肪の塊 女の一生 |
モーパッサン | モーパッサン |
| ユーゴー | ||
| バルザック | ||
| モリエール | ||
| 小説『ふくろう党』でデビュー 『人間喜劇』と題した小説集 『ゴリオ爺さん』『谷間の百合』 19世紀フランスの作家 |
モーパッサン | バルザック |
| ユーゴー | ||
| バルザック | ||
| モリエール | ||
| 著書『存在と無』 ノーベル文学賞を辞退 小説『嘔吐』 妻はボーボワール |
モーパッサン | サルトル |
| サルトル | ||
| バルザック | ||
| モリエール | ||
| 今村昌平監督が映画化 主人公は閑間重松 被爆者を描いた作品 作者は井伏鱒二 |
金色夜叉 | 黒い雨 |
| 高野聖 | ||
| 黒い雨 | ||
| 蒲団 | ||
| 愛知県吉良町出身 元横綱審議委員会委員 『鶺鴒の巣』『天皇機関説』 小説『人生劇場』 |
葛西善蔵 | 尾崎士郎 |
| 長塚節 | ||
| 井伏鱒二 | ||
| 尾崎士郎 | ||
| 『源叔父』で文壇デビュー 忘れえぬ人々 武蔵野 牛肉と馬鈴薯 |
葛西善蔵 | 国木田独歩 |
| 長塚節 | ||
| 井伏鱒二 | ||
| 国木田独歩 | ||
| ヘミングウェイの小説 第一次世界大戦が舞台 看護婦キャサリン アメリカ兵ヘンリー |
日はまた昇る | 武器よさらば |
| 武器よさらば | ||
| 誰がために鐘は鳴る | ||
| 老人と海 | ||
| ヘミングウェイの小説 主人公はロバート・ジョーダン マリアとの恋愛 スペイン内乱が舞台 |
日はまた昇る | 誰がために鐘は鳴る |
| 武器よさらば | ||
| 誰がために鐘は鳴る | ||
| 老人と海 | ||
| ティッセン・ポルネッサ美術館 国立ソフィア王妃芸術センター ミロ美術館 プラド美術館 |
アメリカ | スペイン |
| オランダ | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ボス『快楽の園』 ベラスケス『ブレダの開城』 ゴヤ『着衣のマハ』『裸のマハ』 スペイン・マドリードの美術館 |
オルセー美術館 | プラド美術館 |
| プラド美術館 | ||
| グッゲンハイム美術館 | ||
| アルテ・ピナコテーク | ||
| 主人公は呉服問屋の娘 千重子と苗子 川端康成の小説 舞台は京都 |
伊豆の踊り子 | 古都 |
| 舞姫 | ||
| 眠れる美女 | ||
| 古都 | ||
| 山田耕筰と雑誌「詩と音楽」創刊 詩集『邪宗門』『思ひ出』 歌集『桐の花』『雲母集』 童謡『この道』『ペチカ』の作詞 |
土井晩翠 | 北原白秋 |
| 北原白秋 | ||
| 高村光太郎 | ||
| 野口雨情 | ||
| 群馬県前橋の医者の家に誕生 娘の葉子も作家 口語自在詩を確立 詩集『青猫』『月に吠える』 |
野口雨情 | 萩原朔太郎 |
| 高村光太郎 | ||
| 萩原朔太郎 | ||
| 北原白秋 | ||
| 森鴎外の小説 弟を助ける姉 父親を探す旅 安寿と厨子王 |
高瀬舟 | 山椒太夫 |
| ヰタ・セクスアリス | ||
| 山椒太夫 | ||
| 舞姫 | ||
| 主人公はフェリックス ヒロインはアンリエット 貴族の夫人と青年の恋 バルザックの小説 |
谷間の百合 | 谷間の百合 |
| 赤と黒 | ||
| レ・ミゼラブル | ||
| 神々は渇く | ||
| ヨセフス サルスティウス トゥキディデス ジュリアス・シーザー |
戦記 | 戦記 |
| 議事録 | ||
| 回顧録 | ||
| 日記 | ||
| ジュール・パスキン モーリス・ユトリロ マルク・シャガール モディリアニ |
バルビゾン派 | エコール・ド・パリ |
| エコール・ド・パリ | ||
| ブリュッケ | ||
| コブラ | ||
| ジュール・デュプレ コンスタン・トロワイヨン テオドール・ルソー ミレー |
バルビゾン派 | バルビゾン派 |
| エコール・ド・パリ | ||
| ブリュッケ | ||
| コブラ | ||
| 主人公は武山信二 友情と忠誠心の板ばさみ 二・二六事件 三島由紀夫の命日 |
宴のあと | 憂国 |
| 十日の菊 | ||
| 午後の曳航 | ||
| 憂国 | ||
| 最後の無頼派 1950年に直木賞を受賞 代表作『火宅の人』 長女・ふみは女優 |
檀一雄 | 檀一雄 |
| 高見順 | ||
| 織田作之助 | ||
| 坂口安吾 | ||
| 群馬県館林市に記念館 『生』『妻』『縁』 蒲団 田舎教師 |
国木田独歩 | 田山花袋 |
| 長塚節 | ||
| 井伏鱒二 | ||
| 田山花袋 | ||
| ほどほどの懸想 はなだの女御 花桜折る少将 虫めづる姫君 |
宇津保物語 | 堤中納言物語 |
| 堤中納言物語 | ||
| 大和物語 | ||
| 落窪物語 | ||
| 平安時代に成立 作者は不明 前半は琴を巡る物語 後半は皇位継承争いを描く |
宇津保物語 | 宇津保物語 |
| 堤中納言物語 | ||
| 大和物語 | ||
| 落窪物語 | ||
| 平安時代に成立 少将道頼との恋愛 主人公は美しいお姫様 継母によるいじめ |
宇津保物語 | 落窪物語 |
| 堤中納言物語 | ||
| 大和物語 | ||
| 落窪物語 | ||
| ヘッダ・ガブラー ペール・ギュント ノルウェーの作家 人形の家 |
イプセン | イプセン |
| リンドグレーン | ||
| サン・テグジュペリ | ||
| メーテルリンク | ||
| 人間の土地 南方郵便機 夜間飛行 星の王子さま |
イプセン | サン・テグジュペリ |
| リンドグレーン | ||
| サン・テグジュペリ | ||
| メーテルリンク | ||
| 聖アントワーヌの誘惑 感情教育 サランボー ボヴァリー夫人 |
アンリ・バルビュス | フローベール |
| ロマン・ロラン | ||
| アルフレッド・ミュッセ | ||
| フローベール | ||
| ニュー・ラナークで工場を経営 理想郷ニュー・ハーモニーを建設 イギリスの社会思想家 空想的社会主義 |
ロバート・オーエン | ロバート・オーエン |
| マルクス | ||
| バーナード・ショー | ||
| サン・シモン | ||
| 紫の蒲團に坐る春日かな 春や昔十五万石の城下哉 松山や秋より高き天主閣 柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 |
小林一茶 | 正岡子規 |
| 与謝蕪村 | ||
| 松尾芭蕉 | ||
| 正岡子規 | ||
| 江戸時代の画家 八橋蒔絵硯箱 紅白梅図屏風 燕子花図屏風 |
土佐光沖 | 尾形光琳 |
| 尾形光琳 | ||
| 俵屋宗達 | ||
| 狩野永徳 | ||
| 安土桃山時代の画家 安土城や大阪城の障壁画 唐獅子図屏風 洛中洛外図屏風 |
土佐光沖 | 狩野永徳 |
| 尾形光琳 | ||
| 俵屋宗達 | ||
| 狩野永徳 | ||
| シェイクスピア作品 四大悲劇の主人公 王ダンカンを暗殺する スコットランドの将軍 |
リア王 | マクベス |
| オセロ | ||
| ハムレット | ||
| マクベス | ||
| 仏像の種類 日光 観世音 弥勒 |
天 | 菩薩 |
| 明王 | ||
| 菩薩 | ||
| 如来 | ||
| 月世界旅行 海底二万マイル 十五少年漂流記 八十日間世界一周 |
ジュール・ベルヌ | ジュール・ベルヌ |
| スティーブンソン | ||
| エドガー・ライス・バローズ | ||
| ヘンリー・ハガード | ||
| 1911年ノーベル文学賞受賞 ペレアスとメリザンド ベルギーの作家 青い鳥 |
メーテルリンク | メーテルリンク |
| イプセン | ||
| キップリング | ||
| セルバンテス | ||
| 聖体の論議 アテネの学堂 キリストの変容 小椅子の聖母 |
ミケランジェロ | ラファエロ |
| レオナルド・ダ・ビンチ | ||
| ボッティチェリ | ||
| ラファエロ | ||
| シェークスピア作品 四大悲劇の主人公 娘2人に国を追い出される ブリテンの王 |
ハムレット | |
| オセロ | ||
| マクベス | ||
| リア王 | ||
| 生きている兵隊 風にそよぐ葦 『人間の壁』『蒼氓』 第1回芥川賞受賞 |
川口松太郎 | 石川達三 |
| 石川達三 | ||
| 火野葦平 | ||
| 石川淳 | ||
| 主人公はジム・ホーキンズ ヒスパニョーラ号 作者はスチーブンソン 海賊ジョン・シルバー |
宝島 | 宝島 |
| 白鯨 | ||
| 失われた地平線 | ||
| タイピー | ||
| ドナト・ブラマンテ アンドレア・パラーディオ ジョルジョ・ヴァザーリ フィリッポ・ブルネレスキ |
オランダ | イタリア |
| ポルトガル | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| 『雲の墓標』『暗い波濤』 『山本五十六』『志賀直哉』 南蛮阿房列車 長女はタレントの佐和子 |
坂口安吾 | 阿川弘之 |
| 逢坂剛 | ||
| 阿川弘之 | ||
| 黒岩重吾 | ||
| 主人公は人気作家 緒形拳主演で映画化 妻子ある男性の恋を描く 檀一雄の自伝的小説 |
吉里吉里人 | 火宅の人 |
| 赤頭巾ちゃん気をつけて | ||
| 火宅の人 | ||
| 月山 | ||
| 平安時代の六歌仙の一人 平城天皇の孫 『伊勢物語』の主人公 ちはやぶる神代もきかず~ |
在原業平 | 在原業平 |
| 小野小町 | ||
| 大伴黒主 | ||
| 文屋康秀 | ||
| フランス印象派の画家 『田舎の踊り』『街の踊り』 息子のジャンは映画監督 水浴の女たち |
ルノワール | ルノワール |
| ピカソ | ||
| ゴッホ | ||
| ルーベンス | ||
| ジャクソン・ポロック エドワード・ホッパー キース・ヘリング アンディ・ウォーホル |
イタリア | アメリカ |
| イギリス | ||
| ドイツ | ||
| アメリカ | ||
| ホックニー コンスタブル ビアズリー ターナー |
イタリア | イギリス |
| オランダ | ||
| イギリス | ||
| ドイツ | ||
| 題名は北原白秋の詩に由来 母親との再会と別れ 作者は山本有三 主人公は少年・守川義夫 |
路傍の石 | 真実一路 |
| 夜明け前 | ||
| 田舎教師 | ||
| 真実一路 | ||
| 舞台は中山道の馬籠宿 木曽路はすべて山の中である 作者は島崎藤村 主人公は青山半蔵 |
破戒 | 夜明け前 |
| 路傍の石 | ||
| 田舎教師 | ||
| 夜明け前 | ||
| 春のやおぼろ名義で執筆 日本近代写実小説の先駆け 主人公は野々口精作 作者は坪内逍遥 |
破戒 | 当世書生気質 |
| 真実一路 | ||
| 当世書生気質 | ||
| 田舎教師 | ||
| 四里の道は長かった。 主人公は林清三 作者は田山花袋 青年教師の夢と現実を描く |
破戒 | 田舎教師 |
| 真実一路 | ||
| 当世書生気質 | ||
| 田舎教師 | ||
| 同人誌「白樺」に発表 人間の生と死について考察 作者は志賀直哉 電車にはねられ養生生活に |
暗夜行路 | 城の崎にて |
| 小僧の神様 | ||
| 城の崎にて | ||
| 細雪 | ||
| 1921年から雑誌「改造」に連載 自らの出自に苦しむ小説家 作者は志賀直哉 主人公は時任謙作 |
暗夜行路 | 暗夜行路 |
| 小僧の神様 | ||
| 城の崎にて | ||
| 細雪 | ||
| 第94回直木賞を受賞 「ルンルン」を流行語に 葡萄が目にしみる 不機嫌な果実 |
江國香織 | 林真理子 |
| 山田詠美 | ||
| 林真理子 | ||
| よしもとばなな | ||
| 第97回直木賞を受賞 本名は「双葉」 愛称は「ポンちゃん」 代表作『ベッドタイムアイズ』 |
江國香織 | 山田詠美 |
| 山田詠美 | ||
| 林真理子 | ||
| よしもとばなな | ||
| 第130回直木賞を受賞 父・滋はエッセイスト きらきらひかる 号泣する準備はできていた |
江國香織 | 江國香織 |
| 山田詠美 | ||
| 林真理子 | ||
| よしもとばなな | ||
| 1929年ノーベル文学賞受賞 魔の山 ブッデンブローク家の人々 ベニスに死す |
ゲーテ | トマス・マン |
| トマス・マン | ||
| カフカ | ||
| レマルク | ||
| 1946年ノーベル文学賞受賞 春の嵐 デミアン 車輪の下 |
シラー | ヘルマン・ヘッセ |
| ゲーテ | ||
| ヘルマン・ヘッセ | ||
| ヘルダーリン | ||
| ワレンシュタイン三部作 ウィルヘルム・テル 群盗 ベートーベンの『第九』を作詞 |
ゲーテ | シラー |
| シラー | ||
| レマルク | ||
| ハウプトマン | ||
| ゆく春やおもたき琵琶の抱心 五月雨や大河を前に家二軒 春の海終日のたりのたりかな 菜の花や月は東に日は西に |
松尾芭蕉 | 与謝蕪村 |
| 小林一茶 | ||
| 与謝蕪村 | ||
| 正岡子規 | ||
| 作者は三島由紀夫 読売文学賞受賞作 主人公は溝口 実際の事件を題材とした作品 |
仮面の告白 | 金閣寺 |
| 人間失格 | ||
| 斜陽 | ||
| 金閣寺 | ||
| 湯ヶ島温泉 ヒロインは薫 天城峠 下田港 |
舞姫 | 伊豆の踊子 |
| 雪国 | ||
| 伊豆の踊子 | ||
| 古都 | ||
| のっそり十兵衛 主人公は大工 谷中感応寺 作者は幸田露伴 |
黒い雨 | 五重塔 |
| 五重塔 | ||
| 浮雲 | ||
| 不如帰 | ||
| 決闘により死亡 エヴゲニー・オネーギン 大尉の娘 スペードの女王 |
ショーロホフ | プーシキン |
| トルストイ | ||
| プーシキン | ||
| ドストエフスキー | ||
| 舞台は東京都福生市 三田村邦彦主演で映画化 若者たちの乱れた生活を描く 村上龍の芥川賞受賞作 |
火宅の人 | 限りなく透明に近いブルー |
| 氷点 | ||
| 限りなく透明に近いブルー | ||
| 月山 | ||
| 女殺油地獄 心中天網島 国姓爺合戦 曽根崎心中 |
近松門左衛門 | 近松門左衛門 |
| 松尾芭蕉 | ||
| 尾形光琳 | ||
| 井原西鶴 | ||
| 歌枕の所在地 瀬田橋 志賀 伊吹山 |
信濃 | 近江 |
| 出羽 | ||
| 上野 | ||
| 近江 | ||
| 歌枕の所在地 更級山 諏訪海 浅間山 |
信濃 | 信濃 |
| 出羽 | ||
| 陸奥 | ||
| 下野 | ||
| ○○克郎 ○○風太郎 ○○悠介 ○○詠美 |
三浦 | 山田 |
| 山田 | ||
| 永井 | ||
| 藤原 | ||
| The Ark Sakura The Ruined Map The Woman in the Dunes The Box Man |
安部公房 | 安部公房 |
| 川端康成 | ||
| 夏目漱石 | ||
| 三島由紀夫 | ||
| Patriotism After the Banquet The Sound of Waves Confessions of a Mask |
安部公房 | 三島由紀夫 |
| 川端康成 | ||
| 夏目漱石 | ||
| 三島由紀夫 | ||
| The Lake The Master of Go The Old Capital Snow Country |
安部公房 | 川端康成 |
| 川端康成 | ||
| 夏目漱石 | ||
| 三島由紀夫 | ||
| The Wayfarer And Then The Gate I Am a Cat |
安部公房 | 夏目漱石 |
| 川端康成 | ||
| 夏目漱石 | ||
| 三島由紀夫 | ||
| 作者は太宰治 井伏鱒二の元に滞在 太宰の心情を綴ったエッセイ 富士には月見草がよく似合う |
斜陽 | 富嶽百景 |
| 人間失格 | ||
| 走れメロス | ||
| 富嶽百景 | ||
| 後半を書いたのは総生寛 ロンドンまでの旅を描く 作者は仮名垣魯文 主人公は弥次喜多の孫 |
当世書生気質 | 西洋道中膝栗毛 |
| 破戒 | ||
| 西洋道中膝栗毛 | ||
| 田舎教師 | ||
| 国木田独歩がモデルの作家 京マチ子主演で映画化 作者は有島武郎 主人公は早月葉子 |
カインの末裔 | 或る女 |
| お目出たき人 | ||
| 生れ出づる悩み | ||
| 或る女 | ||
| 舞台は万寿丸 北海道室蘭市に文学碑 作者は葉山嘉樹 石炭を運ぶ船で働く人々 |
海に生くる人々 | 海に生くる人々 |
| 太陽のない街 | ||
| 党生活者 | ||
| セメント樽の中の手紙 | ||
| 舞台は倉田工業 前編のみで未完 作者は小林多喜二 主人公は共産党員 |
海に生くる人々 | 党生活者 |
| 太陽のない街 | ||
| 党生活者 | ||
| セメント樽の中の手紙 | ||
| アンチヒーロー 約30年間新聞に連載 主人公は机竜之助 作者は中里介山 |
山椒魚 | 大菩薩峠 |
| 大菩薩峠 | ||
| 真空地帯 | ||
| おろしや国酔夢譚 | ||
| 後に作者が最後の一文を削除 習作『幽閉』を元にした小説 舞台は谷川の岩屋 作者は井伏鱒二 |
恩讐の彼方に | 山椒魚 |
| 檸檬 | ||
| 山椒魚 | ||
| 大菩薩峠 | ||
| えたいの知れない不吉な塊 京都の丸善書店 爆弾を仕掛ける空想 作者は梶井基次郎 |
檸檬 | 檸檬 |
| 山椒魚 | ||
| 城のある町にて | ||
| 蔵の中 | ||
| 作者はトム・ウルフ サム・シェパード主演で映画化 主人公はチャック・イェーガー マーキュリー計画を描く |
ソフィーの選択 | ライト・スタッフ |
| ライト・スタッフ | ||
| 天使よ、故郷を見よ | ||
| 虚栄の篝火 | ||
| 主人公は脚本家の野島 ヒロインは杉子 作家は武者小路実篤 恋に悩む友人の大宮 |
カインの末裔 | 友情 |
| 友情 | ||
| 義血侠血 | ||
| お目出たき人 | ||
| 主人公は苦学生・村越欣弥 ヒロインは水芸人・水島友 『瀧の白糸』の題名で戯曲化 作者は泉鏡花 |
カインの末裔 | 義血侠血 |
| 友情 | ||
| 義血侠血 | ||
| お目出たき人 | ||
| ギョーム、アポリネールの造語 アンドレ・ブルトンが提唱 ダリ、マグリット 「超現実主義」と訳される |
キュビスム | シュールレアリスム |
| アール・ヌーボー | ||
| シュールレアリスム | ||
| アール・デコ | ||
| ギュンター・グラス テオドール・モムゼン ヘルタ・ミュラー トマス・マン |
アイルランドのノーベル賞作家 | ドイツのノーベル賞作家 |
| ドイツのノーベル賞作家 | ||
| イタリアのノーベル賞作家 | ||
| スペインのノーベル賞作家 | ||
| クロード・シモン パトリック・モディアノ アンドレ・ジイド アルベール・カミュ |
イタリアのノーベル賞作家 | フランスのノーベル賞作家 |
| アメリカのノーベル賞作家 | ||
| フランスのノーベル賞作家 | ||
| アイルランドのノーベル賞作家 | ||
| V・S・ナイポール ジョン・ゴールスワージー バートランド・ラッセル カズオ・イシグロ |
スペインのノーベル賞作家 | イギリスのノーベル賞作家 |
| アイルランドのノーベル賞作家 | ||
| イギリスのノーベル賞作家 | ||
| イタリアのノーベル賞作家 | ||
| 北欧神話 魔法の紐グレイプニルで繋がれる オーディンを飲み込む オオカミの姿の巨大な怪物 |
トール | フェンリル |
| フレイヤ | ||
| フェンリル | ||
| ロキ | ||
| 北欧神話 絞める力帯はメギンギョルズ 愛用の金槌はミョルニル 雷や天候の神 |
トール | トール |
| フレイヤ | ||
| フェンリル | ||
| ロキ | ||
| 仄仄○○ 荷○○ 精進○○ ○○透け |
焼け | 明け |
| 抜け | ||
| 掛け | ||
| 明け | ||
| 衣紋○○ 働き○○ 頭○○ 雑巾○○ |
焼け | 掛け |
| 抜け | ||
| 掛け | ||
| 明け | ||
| シン ネルガル マルドゥク イシュタル |
バビロニア神話 | バビロニア神話 |
| ギリシャ神話 | ||
| アステカ神話 | ||
| ケルト神話 | ||
| 漢字の部首 雁 雇 難 |
ゆうぶ | ふるとり |
| とます | ||
| ふるとり | ||
| かぶ | ||
| 漢字の部首 厚 原 厄 |
どぶ | がんだれ |
| しぶ | ||
| にちぶ | ||
| がんだれ | ||
| 漢字の部首 圧 在 地 |
どぶ | どぶ |
| しぶ | ||
| にちぶ | ||
| がんだれ | ||
| 漢字の部首 暦 春 明 |
どぶ | にちぶ |
| しぶ | ||
| にちぶ | ||
| がんだれ | ||
| 漢字の部首 歴 歪 武 |
どぶ | しぶ |
| しぶ | ||
| にちぶ | ||
| がんだれ | ||
| 漢字の部首 くに つつみ もん |
たれ | かまえ |
| つくり | ||
| にょう | ||
| かまえ | ||
| 漢字の部首 ばく えん しん |
たれ | にょう |
| つくり | ||
| にょう | ||
| へん | ||
| 2種類の鳥を使った表現 全身黒一色の鳥 全身白一色の鳥 囲碁の別名 |
鵜の目鷹の目 | 鳥鷲の争い |
| 雉も鳴かずば撃たれまい | ||
| 鶏群の一鶴 | ||
| 鳥鷲の争い | ||
| ことわざ 2種類の鳥が出てくる 出典は『晋書』 凡人の中に優れた者が一人いる |
鵜の目鷹の目 | 鶏群の一鶴 |
| 雉も鳴かずば撃たれまい | ||
| 鶏群の一鶴 | ||
| 鳥鷲の争い | ||
| フランス語の品詞 travailler prendre gagner |
動詞 | 動詞 |
| 形容詞 | ||
| 代名詞 | ||
| 接続詞 | ||
| フランス語の品詞 beau neuf grand |
動詞 | 形容詞 |
| 形容詞 | ||
| 代名詞 | ||
| 接続詞 | ||
| 市に○を放つ 口の○ 苛政は○よりも猛し ○の威を借る狐 |
豹 | 虎 |
| 虎 | ||
| 蛇 | ||
| 熊 | ||
| オンブズマン タングステン スモーガスボード ニッケル |
フェニキア語 | スウェーデン語 |
| ラテン語 | ||
| スウェーデン語 | ||
| ポルトガル語 | ||
| 日本神話 アマテラスの弟 食物の神を殺す イザナギの右目 |
ニニギノミコト | ツクヨミノミコト |
| サルタヒコ | ||
| コトアマツカミ | ||
| ツクヨミノミコト | ||
| 日本神話 大地を象徴する神 大黒天と同一視される 因幡の白兎を助ける |
ニニギノミコト | オオクニヌシノミコト |
| サルタヒコ | ||
| オオクニヌシノミコト | ||
| ツクヨミノミコト | ||
| Buenas dias Bunenas tardes Buenas noches Hola |
英語 | スペイン語 |
| スペイン語 | ||
| イタリア語 | ||
| ロシア語 | ||
| なむ ぞ こそ や |
係り結び | 係り結び |
| ナ行変格活用 | ||
| ラ行変格活用 | ||
| ナリ活用 | ||
| いまそかり あり をり はべり |
係り結び | ラ行変格活用 |
| ナ行変格活用 | ||
| ラ行変格活用 | ||
| ナリ活用 | ||
| ギリシャ神話 クレタ王ミノスの娘 ダイダロスの迷宮を脱出 困難を脱出するときの導き役 |
メドゥーサの首 | アリアドネの糸 |
| シシュフォスの岩 | ||
| ダモクレスの剣 | ||
| アリアドネの糸 | ||
| 季節を表す単語 hiver automne printemps |
スペイン語 | フランス語 |
| フランス語 | ||
| オランダ語 | ||
| イタリア語 | ||
| 季節を表す単語 primavera inverno estate |
スペイン語 | イタリア語 |
| フランス語 | ||
| オランダ語 | ||
| イタリア語 | ||
| mars novembre avril juillet |
ノルウェー語 | フランス語 |
| スペイン語 | ||
| オランダ語 | ||
| フランス語 | ||
| イタリア・トスカナ地方の方言 天国・煉獄・地獄が舞台 ベアトリーチェが登場 ダンテの代表作 |
新生 | 神曲 |
| 牧歌 | ||
| 神曲 | ||
| 抒情詩集 | ||
| 1511年頃に完成 女神モリア 哲学者や聖職者を批判 エラスムスの代表作 |
新生 | 愚神礼讃 |
| 愚神礼讃 | ||
| 神曲 | ||
| 抒情詩集 | ||
| 1596年頃に刊行 全12巻の予定が6巻のみ刊行 アーサー王 エドモンド・スペンサーの代表作 |
神仙女王 | 神仙女王 |
| 愚神礼讃 | ||
| 神曲 | ||
| 抒情詩集 | ||
| 自立語 活用しない 単独では主語になれない 連用修飾語になれる |
副詞 | 副詞 |
| 助動詞 | ||
| 形容詞 | ||
| 動詞 | ||
| 五段活用動詞は当てはまらない 上一段活用動詞は当てはまる 下一段活用動詞も当てはまる 「見れる」「食べれる」 |
ら抜き言葉 | ら抜き言葉 |
| とか弁 | ||
| ほう弁 | ||
| れ足す言葉 | ||
| 西日本を中心に流行 変格活用動詞は当てはまらない 可能を表す言葉に使用 「読めれる」「飲めれる」 |
ら抜き言葉 | れ足す言葉 |
| とか弁 | ||
| ほう弁 | ||
| れ足す言葉 | ||
| 旧約聖書の登場人物 土を耕す者 人類最初の殺人者 アダムとイブの長男 |
イブ | カイン |
| ノア | ||
| カイン | ||
| アベル | ||
| 旧約聖書の登場人物 羊を飼う者 兄に殺される アダムとイブの次男 |
イブ | アベル |
| ノア | ||
| カイン | ||
| アベル | ||
| 万○ 新○ ○雨 嫩○ |
赤 | 緑 |
| 黄 | ||
| 緑 | ||
| 青 | ||
| ○甌無欠 ○城鉄壁 ○枝玉葉 ○科玉条 |
金 | 金 |
| 紫 | ||
| 白 | ||
| 青 | ||
| エウパラモスとアルキッペの子 「工芸者」を意味する名前 クノッソス宮殿の迷宮を建設 息子のイカロスは墜落死 |
ラオコーン | ダイダロス |
| クロノス | ||
| ダイダロス | ||
| ヒュアキントス | ||
| 笑面○叉 ○雨対牀 秉燭○遊 ○郎自大 |
昼 | 夜 |
| 暮 | ||
| 夜 | ||
| 夕 | ||
| 縦○○ 相○○ ○○心地 勝ち名○○ |
引き | 乗り |
| 押し | ||
| 乗り | ||
| 切り | ||
| 令狸執○ 城狐社○ 首○両端 猫○同眠 |
鼠 | 鼠 |
| 虎 | ||
| 馬 | ||
| 蛇 | ||
| 猛○伏草 為○傅翼 燕頷○頸 暴○馮河 |
蛇 | 虎 |
| 馬 | ||
| 虎 | ||
| 牛 | ||
| 独語で「オープストガルテン」 スペイン語で「ウエルト」 フランス語で「ヴェルジュ」 英語で「オーチャード」 |
植物園 | 果樹園 |
| 果樹園 | ||
| 動物園 | ||
| 梅園 | ||
| 売れ○ ○が出る ○が付く 揚げ○を取る |
足 | 足 |
| 肩 | ||
| 腕 | ||
| 腹 | ||
| 邑○群吠 陶○瓦鶏 驢鳴○吠 ○馬之労 |
龍 | 犬 |
| 鶴 | ||
| 犬 | ||
| 兎 | ||
| 嫁○随○ 斗酒隻○ ○鳴狗盗 ○口牛後 |
牛 | 鶏 |
| 馬 | ||
| 犬 | ||
| 鶏 | ||
| 蜀○日に吠ゆ 煩悩の○は追えども去らず ○に論語 ○の川端歩き |
牛 | 犬 |
| 馬 | ||
| 犬 | ||
| 狐 | ||
| ○奏 盈○ 臨○ ○夜 |
金 | 月 |
| 夢 | ||
| 神 | ||
| 月 | ||
| エジプト神話の神 死者の審判で天秤にかける孫 妻はインプト 犬の頭を持つ |
アヌビス | アヌビス |
| バステト | ||
| オシリス | ||
| ラー | ||
| ハヤブサの頭を持つ バステトの父 アメンやホルスと習合 エジプト神話の太陽神 |
アヌビス | ラー |
| バステト | ||
| オシリス | ||
| ラー | ||
| 作文○上 韋編○絶 益者○友 冷汗○斗 |
四 | 三 |
| 一 | ||
| 九 | ||
| 三 | ||
| ○の頬冠 ○の目借り時 ○の行列 ○の面に水 |
蜂 | 蛙 |
| 蛙 | ||
| 蟻 | ||
| 魚 | ||
| ローマ神話の神様 カピトリヌスの丘 ギリシャ神話ではアテナ フクロウは夜飛ぶ |
プルートー | ミネルバ |
| マーキュリー | ||
| ミネルバ | ||
| ダイアナ | ||
| ○狩獲麟 隻履○帰 ○施捧心 ○方浄土 |
南 | 西 |
| 北 | ||
| 西 | ||
| 東 | ||
| ○兵急接 ○褐穿結 ○慮軽率 軽薄○小 |
重 | 短 |
| 明 | ||
| 軽 | ||
| 短 | ||
| ○裘肥馬 群○折軸 ○裘肥馬 ○佻浮薄 |
重 | 軽 |
| 明 | ||
| 軽 | ||
| 短 | ||
| 深溝○塁 置酒○会 有智○才 ○論卓説 |
高 | 高 |
| 長 | ||
| 重 | ||
| 明 | ||
| ○を指して馬となす ○を追う者は山を見ず 夢野の○ 中原に○を逐う |
鹿 | 鹿 |
| 猪 | ||
| 兎 | ||
| 象 | ||
| ○武者 ○見て矢を引く 山より大きな○は出ぬ ○も七代目には豕になる |
鹿 | 猪 |
| 猪 | ||
| 兎 | ||
| 象 | ||
| 舐犢之○ ○屋及烏 敬天○人 ○別離苦 |
夢 | 愛 |
| 死 | ||
| 愛 | ||
| 離 | ||
| 舎人 宿直 黄蜀葵 鶏冠 |
「け」から始まる読み | 「と」から始まる読み |
| 「く」から始まる読み | ||
| 「と」から始まる読み | ||
| 「い」から始まる読み | ||
| 余波 等閑 瞿麦 就中 |
「お」から始まる読み | 「な」から始まる読み |
| 「あ」から始まる読み | ||
| 「す」から始まる読み | ||
| 「な」から始まる読み | ||
| 好 送 罪 答 |
指事文字 | 会意文字 |
| 仮借文字 | ||
| 会意文字 | ||
| 象形文字 | ||
| 白首○面 赤手○拳 天○海濶 色即是○ |
山 | 空 |
| 月 | ||
| 空 | ||
| 氷 | ||
| ○○からも立ち序 箱根知らずの○○話 ○○の敵を長崎で討つ ○○っ子は五月の鯉の吹き流し |
伊勢 | 江戸 |
| 江戸 | ||
| 大阪 | ||
| 出雲 | ||
| 口では○○の城も建つ 江戸は八百八町○○は八百八橋 京の夢○○の夢 京の着倒れ○○の食い倒れ |
伊勢 | 大阪 |
| 江戸 | ||
| 大阪 | ||
| 出雲 | ||
| ファテープル・シークリー カジュラーホー遺跡 ハンピの建造物群 アジャンター石窟群 |
カンボジア | インド |
| インド | ||
| インドネシア | ||
| ウズベキスタン | ||
| 『龍馬伝』で真木よう子が演じた 寺田屋に奉公する 坂本龍馬と結婚 晩年は横須賀で酒びたりの生活に |
千葉佐那子 | 楢崎龍 |
| 平井加尾 | ||
| お元 | ||
| 楢崎龍 | ||
| 18世紀フランスの哲学者 百科全書派 著書『社会契約論』『エミール』 『むすんでひらいて』を作曲 |
アンリ・ベルクソン | ジャン=ジャック・ルソー |
| ロラン・バルト | ||
| ヴァルター・ベンヤミン | ||
| ジャン=ジャック・ルソー | ||
| 1600年に豊後に到着 オランダ船 ヤン・ヨーステン ウィリアム・アダムス |
ノルマントン号 | リーフデ号 |
| リーフデ号 | ||
| ビーグル号 | ||
| モリソン号 | ||
| ○○と焼き味噌 ○○履いて首っ丈 ○○も仏も同じ木のきれ ○○を預ける |
木靴 | 下駄 |
| 脚絆 | ||
| 足袋 | ||
| 下駄 | ||
| 作家の言葉 ヴェルレーヌの詩集にある一節 太宰治が引用 格闘家・前田日明がさらに引用 |
生まれ出ずる悩み | 選ばれし者の恍惚と不安 |
| 人生は一箱のマッチに似ている | ||
| 則天去私 | ||
| 選ばれし者の恍惚と不安 | ||
| 1455年に西郷氏が築城 別名は「籠城」 徳川家康が生まれた場所 愛知県にあった城 |
清州城 | 岡崎城 |
| 岩村城 | ||
| 長篠城 | ||
| 岡崎城 | ||
| ロシアの来日使節 大黒屋光太夫らと同行 エカテリーナ2世の親書を携える 根室に来航 |
プチャーチン | ラクスマン |
| レザノフ | ||
| ラクスマン | ||
| フヴォストフ | ||
| 江戸時代の探検家 伊能忠敬に測量技術を学ぶ 樺太が島であることを確認 タタール海峡の日本名 |
近藤重蔵 | 間宮林蔵 |
| 間宮林蔵 | ||
| 松浦武四郎 | ||
| 最上徳内 | ||
| 細川忠興が改築 戦国末期に毛利氏が築城 福岡県にあった城 幕末の長州征伐で落城 |
小倉城 | 小倉城 |
| 飫肥城 | ||
| 福岡城 | ||
| 名護屋城 | ||
| 新選組の隊士 三番隊組長や撃剣師範を務める 藤田五郎に改名して警察官に 西南戦争では西郷軍と戦う |
沖田総司 | 斎藤一 |
| 斎藤一 | ||
| 近藤勇 | ||
| 藤堂平助 | ||
| 鎌倉末期から南北朝時代の武将 「建武の新政」では武者所の長 分倍河原の戦い 稲村ヶ崎に黄金の太刀を投ずる |
鹿島高徳 | 新田義貞 |
| 畠山義就 | ||
| 斯波高経 | ||
| 新田義貞 | ||
| 2曲1双の屏風 尾形光琳による模写も有名 一面に金箔が張ってある 作者は俵屋宗達 |
富岳三十六景 | 風神雷神図屏風 |
| 風神雷神図屏風 | ||
| 鳥獣戯画 | ||
| 蒙古襲来絵詞 | ||
| クレオパトラの針 ギリシャ語で「焼串」 パリのコンコルド広場 古代エジプトの記念碑 |
オベリスク | オベリスク |
| ピラミッド | ||
| ジッグラト | ||
| メンヒル | ||
| 本名は「茂次郎」 岡山県生まれの画家・詩人 明治から大正にかけ美人画で人気 流行歌『宵待草』の作詞 |
菱川師宣 | 竹久夢二 |
| 萩原翔太郎 | ||
| 竹久夢二 | ||
| 高村光太郎 | ||
| 幕末の儒学者 安政の大獄で処刑 勤王の志士として活躍 父は山陽 |
所郁太郎 | 頼三樹三郎 |
| 頼三樹三郎 | ||
| 梅田雲浜 | ||
| 小林虎三郎 | ||
| 広津和郎と中村光夫の論争 太陽のせいで殺人を犯す 主人公はムルソー アルベール・カミュの小説 |
異邦人 | 異邦人 |
| ジャン・クリストフ | ||
| 嘔吐 | ||
| 危険な関係 | ||
| 野田城の戦い 大ていは地に任せて~ 病状が悪化して撤退 現在の長野県で病死 |
豊臣秀吉の最後 | 武田信玄の最後 |
| 今川義元の最後 | ||
| 織田信長の最後 | ||
| 武田信玄の最後 | ||
| 白い魔女 カスピアン王 ペペンシー家の4きょうだい 不思議なライオン・アスラン |
ピノキオ | ナルニア国物語 |
| 不思議の国のアリス | ||
| ジャングル・ブック | ||
| ナルニア国物語 | ||
| 致良知(ちりょうち) 近江聖人 その名は屋敷内の老木から 日本陽明学の始祖 |
熊沢蕃山 | 中江藤樹 |
| 中江藤樹 | ||
| 山鹿素行 | ||
| 荻生徂徠 | ||
| ○で掘って鍬で埋める 細くても○は呑めぬ 棒ほど願って○ほど叶う ○のむしろ |
刃 | 針 |
| 箸 | ||
| 筆 | ||
| 針 | ||
| 聖書の中の言葉 新約聖書・使徒言行録 絵画のモチーフにも パウロが回心してキリスト教徒に |
死に至る病 | 目から鱗が落ちる |
| 目から鱗が落ちる | ||
| 狭き門より入れ | ||
| 汝の隣人を愛せよ | ||
| 大のサッカーファン 愛称は「鉄のお嬢さん」 キリスト教民主同盟に所属 ドイツ初の女性首相 |
アンゲラ・メルケル | アンゲラ・メルケル |
| マーガレット・サッチャー | ||
| タンス・チルレル | ||
| エディット・クレッソン | ||
| 日本蔑視の発言を連発 社会党の政治家 元シャテルロー市長 フランス初の女性首相 |
アンゲラ・メルケル | エディット・クレッソン |
| マーガレット・サッチャー | ||
| タンス・チルレル | ||
| エディット・クレッソン | ||
| 265年に成立 420年に滅亡 都は洛陽 魏の司馬炎が建国 |
魏 | 普 |
| 後漢 | ||
| 普 | ||
| 蜀 | ||
| 奈良時代の僧 最初の日本全図に名前を残す 生きながら「菩薩」と呼ばれる 日本最初の「大僧正」の位 |
行基 | 行基 |
| 空也 | ||
| 源信 | ||
| 日親 | ||
| 1945年7月17日~8月2日 ツェツィーリエンホーフ宮殿 米・英・ソの首脳が出席 戦後処理と日本の終戦について |
ポツダム会談 | ポツダム会談 |
| カイロ会談 | ||
| カサブランカ会談 | ||
| ヤルタ会談 | ||
| ギリシャ語で「プシュケ」 イタリア語で「アニマ」 ドイツ語で「ゼーレ」 英語で「ソウル」 |
愛 | 魂 |
| 力 | ||
| 夢 | ||
| 魂 | ||
| 戦国時代の合戦 舞台は三河国 織田・徳川連合軍と武田軍の戦い 鉄砲隊が大活躍 |
桶狭間の戦い | 長篠の戦い |
| 三方ヶ原の戦い | ||
| 長篠の戦い | ||
| 姉川の戦い | ||
| 都はプルシャプラ 中国では「貴霜朝」 ガンダーラ美術 カニシカ王 |
ヴァルダナ朝 | クシャーナ朝 |
| マウリヤ朝 | ||
| クシャーナ朝 | ||
| グプタ朝 | ||
| 詩集『酔いどれ船』 詩集『イリュミナシオン』 詩集『地獄の季節』 早熟の天才 |
ポール・エリュアール | アルチュール・ランボー |
| ルイ・アラゴン | ||
| アルチュール・ランボー | ||
| アンドレ・ブルトン | ||
| 江戸時代の藩校 1868年の弘道館戦争 総合大学にたとえられる 徳川斉昭が創設 |
彦根藩の弘道館 | 水戸藩の弘道館 |
| 佐賀藩の弘道館 | ||
| 備後福山藩の弘道館 | ||
| 水戸藩の弘道館 | ||
| 諸子百家のひとつ 竹林の七賢が有名 「無為自然」を説く 老荘思想 |
墨家 | 道家 |
| 法家 | ||
| 道家 | ||
| 名家 | ||
| バラの棘で負った傷が元で死去 ドイツの詩人 ドゥイノの悲歌 マルテの手記 |
リルケ | リルケ |
| ヘルダーリン | ||
| カフカ | ||
| ハウプトマン | ||
| 車胤 孫康 受験情報誌のタイトル 苦学して大成すること |
風樹の嘆 | 蛍雪の功 |
| 累卵の危 | ||
| 蛍雪の功 | ||
| 嚢中の錐 | ||
| 森川許六 向井去来 榎本其角 服部嵐雪 |
孔門の十哲 | 蕉門の十哲 |
| 金門の十哲 | ||
| 木門の十哲 | ||
| 蕉門の十哲 | ||
| ホメロス作『イリアス』の主人公 ステュクス川に侵される 亀に追いつけない 人間のかかとの「腱」に名を残す |
ヘラクレス | アキレウス |
| ケンタウロス | ||
| アキレウス | ||
| オイディプス | ||
| 「3B政策」の都市のひとつ 東ローマ帝国の首都 コンスタンティノープルに改名 現在のイスタンブール |
ビザンチウム | ビザンチウム |
| ベルリン | ||
| ブダペスト | ||
| ベオグラード | ||
| イスラム国家 アウラングゼーブのとき最大領土 初代皇帝はバーブル 首都はアグラ |
ムガル帝国 | ムガル帝国 |
| オスマン帝国 | ||
| ビザンツ帝国 | ||
| 神聖ローマ帝国 | ||
| 群馬県にあった城 上杉謙信の関東攻略の拠点 御館の乱後、北条氏の手に 真田氏の拠点 |
箕輪城 | 沼田城 |
| 沼田城 | ||
| 鉢形城 | ||
| 川越城 | ||
| 18世紀のロシア皇帝 ピョートル3世の妃 エルミタージュ美術館 ポーランド分割 |
エカテリーナ2世 | エカテリーナ2世 |
| エカテリーナ1世 | ||
| ピョートル1世 | ||
| イワン4世 | ||
| 上杉謙信に仕えた四天王の一人 朝廷との折衝役を担当 川中島の戦いで謙信を救出 娘婿の兼続は大河ドラマの主人公 |
柿崎景家 | 直江景綱 |
| 甘粕景持 | ||
| 直江景綱 | ||
| 宇佐美定満 | ||
| アメリカの戦艦 1898年にハバナ湾で爆沈 沈没時、日本人も8人乗船 米西戦争のきっかけ |
ミズーリ号 | メイン号 |
| ポチョムキン号 | ||
| メイン号 | ||
| ミシシッピ号 | ||
| 1945年8月に組閣 「一億総懺悔」を提唱 終戦処理内閣を組織 皇族出身 |
幣原喜重郎 | 東久邇宮稔彦 |
| 鈴木貫太郎 | ||
| 吉田茂 | ||
| 東久邇宮稔彦 | ||
| 拓殖大学を創立 第2代台湾総督 首相在職日数は歴代2位の2886日 西園寺公望と交代で首相を務める |
加藤高明 | 桂太郎 |
| 清浦奎吾 | ||
| 高橋是清 | ||
| 桂太郎 | ||
| 現在のメキシコに栄えた ケツァルコアトル 首都はテノチティトラン スペイン人コルテスに滅ぼされる |
アステカ文明 | アステカ文明 |
| テオティワカン文明 | ||
| オルメカ文明 | ||
| インカ文明 | ||
| 西暦234年におこる 魏と蜀の戦い 現在の陝西省が舞台 諸葛亮の死により蜀が撤退 |
長坂の戦い | 五丈原の戦い |
| 官渡の戦い | ||
| 街亭の戦い | ||
| 五丈原の戦い | ||
| 「第三の新人」の作家 『白い人』で芥川賞受賞 『沈黙』『海と毒薬』 別名は「狐狸庵山人」 |
遠藤周作 | 遠藤周作 |
| 安岡章太郎 | ||
| 庄野潤三 | ||
| 吉行淳之介 | ||
| 「美濃三人衆」の一人 武田勝頼と内通した罪で追放 竹中半兵衛と稲葉山城を占拠 稲葉一鉄との戦いで自害 |
安藤守就 | 安藤守就 |
| 氏家ト全 | ||
| 堀尾吉晴 | ||
| 生駒親正 | ||
| 中国の古代王朝 紀元前16~11世紀 湯王が夏を滅ぼして創始 周の武王に滅ぼされる |
魏 | 殷 |
| 周 | ||
| 殷 | ||
| 楚 | ||
| ファン・ボイ・チャウ ベトナム 日本への留学 読みは「ドンズー」 |
西遊運動 | 東遊運動 |
| 北東遊運動 | ||
| 南遊運動 | ||
| 東遊運動 | ||
| わずか2歳で皇帝に即位 清の第12代皇帝 1934年に満州国皇帝となる 映画『ラストエンペラー』 |
乾隆帝 | 宣統帝 |
| 同治帝 | ||
| 康熙帝 | ||
| 宣統帝 | ||
| サイクス・ピコ協定 フサイン・マクマホン協定 バルフォア宣言 シオニズム運動 |
カシミール問題 | パレスティナ問題 |
| パレスティナ問題 | ||
| ポーランド問題 | ||
| チェチェン問題 | ||
| 天気を表す言葉 篠を突く 車軸を流す 馬の背を分ける |
雨 | 大雨 |
| 大雨 | ||
| 日照り | ||
| 雷 | ||
| 天気を表す言葉 青女 立花 風花 |
大雨 | 雪 |
| 雷 | ||
| 雪 | ||
| 日照り | ||
| 11歳で将軍に あだ名は「左様せい様」 保科正之を重用 江戸幕府の第4代将軍 |
徳川家綱 | 徳川家綱 |
| 徳川吉宗 | ||
| 徳川家光 | ||
| 徳川秀忠 | ||
| 雍正帝 乾隆帝 康熙帝 宣統帝 |
明 | 清 |
| 宋 | ||
| 唐 | ||
| 清 | ||
| 紀元前3000年頃メネス王が統一 アマルナ美術が発達 古・中・新の3王国 都はメンフィスにテーベ |
アッシリア | エジプト |
| エジプト | ||
| メソポタミア | ||
| バビロニア | ||
| 神田明神に祀られている 別名「相馬小次郎」 承平の乱を起こす 関東を制圧し「新皇」を自称 |
平貞盛 | 平将門 |
| 平将門 | ||
| 平敦盛 | ||
| 平時忠 | ||
| 平安時代の武将 能や幸若舞の題材 笛の名手 一ノ谷の戦いで戦死 |
平貞盛 | 平敦盛 |
| 平将門 | ||
| 平敦盛 | ||
| 平時忠 | ||
| 家景 貞景 教景 義景 |
朝倉氏 | 朝倉氏 |
| 小田原北条氏 | ||
| 六角氏 | ||
| 真田氏 | ||
| ○○は器ならず ○○は和して同ぜず ○○、豹変する ○○、危うきに近寄らず |
孟子 | 君子 |
| 荀子 | ||
| 君子 | ||
| 孔子 | ||
| 日本の黒い霧 或る「小倉日記」伝 ゼロの焦点 『点と線』『砂の器』 |
松本清張 | 松本清張 |
| 大江健三郎 | ||
| 吉行淳之介 | ||
| 谷崎潤一郎 | ||
| 1916年から雑誌「文明」に連載 主人公は駒代 花柳界を描いた作品 作者は永井荷風 |
お目出たき人 | 腕くらべ |
| 腕くらべ | ||
| 或る女 | ||
| 義血侠血 | ||
| サットン・フー スカラ・ブレイ リング・オブ・ブロッガー ストーンヘンジ |
イギリス | イギリス |
| スペイン | ||
| ギリシャ | ||
| フランス | ||
| 四書のひとつ もともとは『礼記』の一遍 朱熹の注釈書 四書の最後に位置付けられる |
論語 | 中庸 |
| 孟子 | ||
| 中庸 | ||
| 大学 | ||
| 1985年に上海市長に就任 趙紫陽の後任として党総書記に 反日教育を推進し謝罪を要求 1993年に中国国家主席に就任 |
トウ小平 | 江沢民 |
| 華国鋒 | ||
| 江沢民 | ||
| 劉少奇 | ||
| 紫電清○ 露往○来 秋○三尺 秋○烈日 |
霜 | 霜 |
| 雷 | ||
| 雨 | ||
| 雪 | ||
| 米西戦争の講和条約 七年戦争の講和条約 クリミア戦争の講和条約 アメリカ独立戦争の講和条約 |
パリ条約 | パリ条約 |
| ジュネーブ条約 | ||
| ロンドン条約 | ||
| ローザンヌ条約 | ||
| 大江時広が築城 直江兼続が城主に 伊達政宗が生まれた城 山形県にあった城 |
小峰城 | 米沢城 |
| 弘前城 | ||
| 二本松城 | ||
| 米沢城 | ||
| 別名は「虎伏城」 山名持豊が築城 兵庫県朝来市に城跡 日本のマチュピチュ |
太田城 | 竹田城 |
| 竹田城 | ||
| 三木城 | ||
| 御着城 | ||
| ○才六 ○を以て馬を相す ○を吹いて疵を求む ○筋ほども疑わない |
爪 | 毛 |
| 口 | ||
| 毛 | ||
| 耳 | ||
| スペインの画家 1808年5月3日 カルロス4世の家族 『着衣のマハ』『裸のマハ』 |
ベラスケス | ゴヤ |
| エル・グレコ | ||
| ゴヤ | ||
| ムリリョ | ||
| オルガス伯の埋葬 聖衣剥奪 トレド風景 「ギリシャ人」という意味 |
ベラスケス | エル・グレコ |
| エル・グレコ | ||
| ゴヤ | ||
| ムリリョ | ||
| 夏目漱石の後期三部作のひとつ 先生と私 両親と私 先生と遺書 |
三四郎 | こころ |
| こころ | ||
| それから | ||
| 草枕 | ||
| 猿が髭揉む ○に烏帽子 ○舞腰 ○の尻笑い |
狼 | 猿 |
| 猪 | ||
| 猿 | ||
| 鼠 | ||
| 室町幕府第6代将軍 永享の乱で足利持氏を討伐 くじ引きで将軍に 赤松満祐に暗殺される |
足利義教 | 足利義教 |
| 足利義量 | ||
| 足利義政 | ||
| 足利義満 | ||
| 源頼朝と平維盛の戦い 1180年の戦い 水鳥の羽音で平氏が敗走 現在の静岡県で発生 |
一ノ谷の戦い | 富士川の戦い |
| 富士川の戦い | ||
| 屋島の戦い | ||
| 墨俣川の戦い | ||
| ティルスの植民都市 フェニキア人が建設 ローマとのポエニ戦争 名将ハンニバル |
スパルタ | カルタゴ |
| ローマ | ||
| アテネ | ||
| カルタゴ | ||
| 轍鮒の○ 短兵○ 焦眉の○ 序破○ |
急 | 急 |
| 緩 | ||
| 時 | ||
| 曲 | ||
| 武田信玄 甲陽軍鑑 武田節 組織の中の人の結束を説いた言葉 |
心頭滅却すれば火もまた涼し | 人は城、人は石垣、人は堀 |
| 風林火山 | ||
| 人は城、人は石垣、人は堀 | ||
| 渋柿は渋柿として使え | ||
| ダロウェー○○ ボヴァリー○○ 武蔵野○○ 真珠○○ |
物語 | 夫人 |
| 紀行 | ||
| 日記 | ||
| 夫人 | ||
| 太平洋戦争末期に製造 墓地は山口県大津島 小説『出口のない海』 人間魚雷 |
震洋 | 回天 |
| 伏竜 | ||
| 回天 | ||
| 海龍 | ||
| ことばの由来になった動物 風が吹けば桶屋がもうかる 火中の栗を拾う ちょっかい |
イヌ | ネコ |
| キツネ | ||
| ネコ | ||
| ネズミ | ||
| ○花斉放 ○載無窮 ○川帰海 ○錬成鋼 |
千 | 百 |
| 万 | ||
| 百 | ||
| 十 | ||
| 父と子 ルージン ムムー 猟人日記 |
チェーホフ | ツルゲーネフ |
| トルストイ | ||
| ツルゲーネフ | ||
| マヤコフスキー | ||
| 本名は「菊池久徳」 天道浮世出星操 雷太郎強悪物語 『浮世風呂』『浮世床』 |
恋川春町 | 式亭三馬 |
| 滝沢馬琴 | ||
| 式亭三馬 | ||
| 十返舎一九 | ||
| 劉備の元で活躍した武将 漢中攻略戦で大活躍 字は「孟起」 父親は馬騰 |
黄忠 | 馬超 |
| 趙雲 | ||
| 馬超 | ||
| 張飛 | ||
| 江戸時代からは松平氏が城主 堀尾吉晴が築城 島根県にあった城 天守が国宝に指定 |
松江城 | 松江城 |
| 津和野城 | ||
| 備中高松城 | ||
| 月山富田城 | ||
| 仏教を厚く保護 デリーにある錆びない鉄柱 マウリヤ朝の第3代の王 漢字では「阿育王」 |
チャンドラグプタ2世 | アショーカ王 |
| アショーカ王 | ||
| カニシカ王 | ||
| ハルシャ・ヴァルダナ |
| 原田克吉の指揮 戸ノ口原の合戦 燃え盛る鶴ヶ城 飯盛山で自刃 |
A
| ボンドパッダーエが発見 現地の言葉で「死の丘」の意味 上下水道も整備された インダス文明の古代都市 |
B
| 主人公はのっそり十兵衛 貧しい職人気質の大工 舞台は谷中感応寺 幸田露伴の小説 |
C
| 次の画像から連想される小説で知られる文豪は? |
D
| フランス文学 デュヴィヴィエ監督が映画化 ルナールの小説 赤い髪とソバカスだらけの少年 |
C
| 僕って何? 人生劇場 高田馬場ラブソング 青春の門 |
B

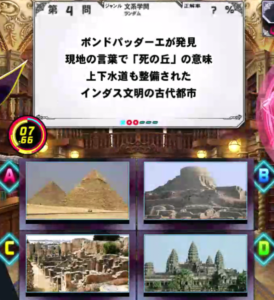
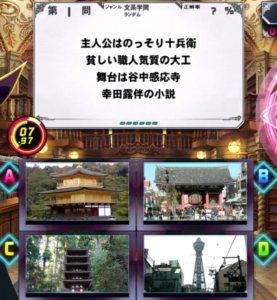
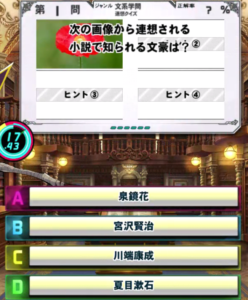

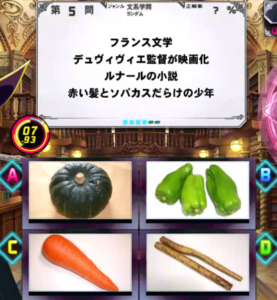

なぜかカクテルの問題が1つありますね。
とても文系とは思えないですし、
ライフスタイルの連想☆3に同じ問題があるので
こちらは削除していいと思います。
自分で誤操作して気付かないままだったのでしょうか。
なぜ文系にあるのか自分にもわかりませんが
こちら削除しました。