| 良くないものが広まっています | 蔓延る | はびこる |
| 暴力や強権によって、他者の権利などを踏みにじること | 蹂躙 | じゅうりん |
| 江戸時代中期に伊予吉田藩の藩医を務めた医学者です | 平住専庵 | ひらずみせんあん |
| 気晴らしに見物や遊びにでかけること | 物見遊山 | ものみゆさん |
| 髪の色と目の色から西洋人のことをいう言葉です | 紅毛碧眼 | こうもうへきがん |
| 過去の例や手本などに照らして考えること | 鑑みる | かんがみる |
| 第1回文化勲章を受賞した明治生まれの歌人です | 佐佐木信綱 | ささきのぶつな |
| 源義仲軍と平家軍の合戦があった石川県と富山県の県境 | 倶利伽羅峠 | くりからとうげ |
| 日本軍が満州国の皇帝とした清朝最後の皇帝・宣統帝 | 溥儀 | ふぎ |
| 奥州藤原氏の初代当主は「藤原○○」? | 清衡 | きよひら |
| 「天下の台所」に建てられました | 蔵屋敷 | くらやしき |
| 正倉院などに見られる建築様式 | 校倉造 | あぜくらづくり |
| 仁徳天皇のお墓とされる最大の前方後円墳 | 大仙陵 | だいせんりょう |
| 1861年に武市半平太によって結成された政治組織です | 土佐勤王党 | とさきんのうとう |
| イギリス王・ヘンリ7世の時に確立された国王直属の裁判所 | 星室庁 | せいしつちょう |
| 「聖徳太子」のことを、最近の教科書ではこう教えています | 厩戸皇子 | うまやどのおうじ |
| 倒幕運動と結びついた政治思想 | 尊王攘夷 | そんのうじょうい |
| 「赤城の山も今宵限り」の名文句で有名な江戸時代の侠客 | 国定忠治 | くにさだちゅうじ |
| 和歌の別名です | 三十一文字 | みそひともじ |
| 周恩来の死で首相に就任 | 華国鋒 | かこくほう |
| 人の夢とはこんなものです | 儚い | はかない |
| 弟と大喧嘩をした日本神話に登場する神です | 海幸彦 | うみさちひこ |
| 日本神話に登場する英雄です | 素戔鳴尊 | スサノオノミコト |
| 白話文字を提唱した中国の思想家 | 胡適 | こてき |
| 詩集『一握の玻璃』『砂金』などで知られる詩人 | 西条八十 | さいじょうやそ |
| 主人公・道子とその従兄弟の愛を描いた大岡昇平の代表作 | 武蔵野夫人 | むさしのふじん |
| 小説『日輪』『旅愁』で知られる新感覚派の作家 | 横光利一 | よこみつりいち |
| 知らんぷりをすることです | 恍ける | とぼける |
| 1980年に『黄色い牙』で直木賞を受賞した作家です | 志茂田景樹 | しもだかげき |
| 5世紀にササン朝ペルシアと組んでエフタルを滅ぼしました | 突厥 | とっけつ |
| ウトウトしている様子です | 微睡む | まどろむ |
| ルイ14世の明言「○は国家なり」? | 朕 | ちん |
| 江戸時代の画家・尾形光琳の代表作は『○○○図屏風』? | 紅白梅 | こうはくばい |
| 初めて足のない幽霊を描いたと言われる江戸時代の画家 | 円山応挙 | まるやまおうきょ |
| 鎌倉時代の執権・北条氏において嫡流の当主を指した言葉です | 得宗 | とくそう |
| 猛烈な勢いで物事に対処すること | 獅子奮迅 | ししふんじん |
| 武田氏が釜無川に施した大規模な治水工事の通称 | 信玄堤 | しんげんづつみ |
| 信長、秀吉の姓にちなむ安土桃山時代の別名です | 織豊時代 | しょくほうじだい |
| 戦国武将・北条早雲の別名は「伊勢○○○」? | 新九郎 | しんくろう |
| 北条早雲によって討たれた堀越公方、足利政知の子 | 茶々丸 | ちゃちゃまる |
| 明治の作家・東海散士が書いた政治小説です | 佳人之奇遇 | かじんのきぐう |
| 戦国から江戸時代にかけて「直轄領」を指 した言葉です | 蔵入地 | くらいりち |
| 「賤ヶ岳の七本槍」の一人にも数えられる戦国時代の武将です | 平野長泰 | ひらのながやす |
| 「賤ヶ岳の七本槍」の一人にも数えられる戦国時代の武将です | 脇坂安治 | わきさかやすはる |
| 寛政の改革や天保の改革のものが有名 | 棄捐令 | きえんれい |
| お酒を飲んで仲直りすること | 杯酒解怨 | はいしゅかいえん |
| 現在の栃木県とはほぼ同じ地域にかつて存在した国です | 下野 | しもつけ |
| 運を天に任せ、一世一代の大勝負に出ること | 乾坤一擲 | けんこんいってき |
| 小おどりして大喜びすること | 欣喜雀躍 | きんきじゃくやく |
| 「かろうじて」「なんとか」といった意味を持つ副詞です | 漸く | ようやく |
| 「もてあます」という意味の言葉です | 手子摺る | てこずる |
| 1905年に発表された夏目漱石の短編小説です | 倫敦塔 | ろんどんとう |
| ひなげしの別名が題名になった夏目漱石の小説です | 虞美人草 | ぐびじんそう |
| 明治の作家・夏目漱石の後期三部作のひとつです | 行人 | こうじん |
| 何のわだかまりもない素直な心で物事にのぞむこと | 虚心坦懐 | きょしんたんかい |
| 小説『二十四の瞳』で有名な作家です | 壺井栄 | つぼいさかえ |
| 従兄弟・畠山政長とのいざこざが応仁の乱を導いた畠山○○ | 義就 | よしなり |
| 怒ったり喜んだり感情がころころと変わること | 采色不定 | さいしょくふてい |
| 代表作に『公余探勝図』がある江戸時代後期の画家です | 谷文晁 | たにぶんちょう |
| 「言いのがれ」という意味の言葉です | 遁辞 | とんじ |
| 現在の均一ショップにあたる江戸時代の価格が一律のお店 | 四文屋 | しもんや |
| 1925年刊行のルポルタージュ『女工哀史』で有名な作家 | 細井和喜蔵 | ほそいわきぞう |
| 2011年に、残した炭鉱画などが世界記憶遺産に登録されました | 山本作兵衛 | やまもとさくべい |
| 平安中期から室町時代にかけて傭兵が為政者に要求をしたこと | 強訴 | ごうそ |
| 太平洋戦争のミッドウェー海戦を指揮した第一航空艦隊長官 | 南雲忠一 | なぐもちゅういち |
| 著書『県民性』で知られた日本の心理人類学者です | 祖父江孝男 | そふえたかお |
| 1918年に児童雑誌「赤い鳥」を創刊した作家です | 鈴木三重吉 | すずきみえきち |
| 『赤い蝋燭と人魚』で有名な大正・昭和の児童文学作家です | 小川未明 | おがわみめい |
| 「京焼の幕末三名人」の一人である江戸時代の陶工 | 青木木米 | あおきもくべい |
| 戦国時代に使われた元号です | 永正 | えいしょう |
| 戦国時代に使われた元号です | 文亀 | ぶんき |
| 戦国時代に使われた元号です | 長享 | ちょうきょう |
| 三重県の地名にちなむ図々しいことを表す言葉 | 阿漕 | あこぎ |
| 寄せ集めのグループのこと | 烏合の衆 | うごうのしゅう |
| 尾崎紅葉の小説『金色夜叉』のヒロイン、お宮の名字は? | 鴫沢 | しぎさわ |
| 中国・元の時代の小説『漢宮秋』のヒロイン | 王昭君 | おうしょうくん |
| 明治時代に尾崎紅葉を中心に結成された硯友社の機関誌です | 我楽多文庫 | がらくたぶんこ |
| 尾崎紅葉らと共に硯友社を創設した明治の小説家です | 石橋思案 | いしばししあん |
| 1912年に岸田劉生らと共にヒュウザン会を結成した画家 | 斎藤与里 | さいとうより |
| 武士の身分を奪った上で領地も没収する罰のことです | 改易 | かいえき |
| 諸葛亮亡き後の蜀を支えた中国・三国時代の名将です | 姜維 | きょうい |
| 蜀の軍師・諸葛亮はこう呼ばれていました | 伏龍 | ふくりゅう |
| 東北学を提唱したことで知られる日本の民族学者 | 赤坂憲雄 | あかさかのりお |
| 松山出身の俳人正岡子規の命日です | 糸瓜忌 | へちまき |
| 正岡子規の晩年の四大随筆の一つである私的な病床日記 | 仰臥漫録 | ぎょうがまんろく |
| 向井去来と共に『猿蓑』を編集した、松尾芭蕉の弟子 | 野沢凡兆 | のざわぼんちょう |
| 欠点などを指摘して手ひどく批判すること | 扱き下ろす | こきおろす |
| ザラ峠越えで有名な織田信長に仕えた武将 | 佐々成政 | さっさなりまさ |
| 山本周五郎の代表作は小説『○ノ木は残った』? | 樅 | もみ |
| 太宰治の小説『人間失格』の主人公 | 大庭葉蔵 | おおばようぞう |
| 太宰治の小説『富嶽百景』の舞台になりました | 天下茶屋 | てんがぢゃや |
| 作家・太宰治の命日です | 桜桃忌 | おうとうき |
| 武士が額から頭の中ほどにかけて髪を剃り落としたこと | 月代 | さかやき |
| 武士が武芸訓練として励みました | 笠懸 | かさがけ |
| 武士が武芸訓練として励みました | 流鏑馬 | やぶさめ |
| セオドア・ルーズベルト大統領のラテンアメリカに対する政策 | 棍棒外交 | こんぼうがいこう |
| 第1回谷崎潤一郎賞を受賞した小島信夫の小説です | 抱擁家族 | ほうようかぞく |
| かつての満州国やペタン政権 | 傀儡政権 | かいらいせいけん |
| 1928年、奉天に引き上げる途中日本軍によって暗殺されました | 張作霖 | ちょうさくりん |
| 上杉家の家老として活躍した戦国武将です | 直江兼続 | なおえかねつぐ |
| 情け容赦が無くたちが悪い様子 | 悪辣 | あくらつ |
| 1336年に楠木正成が戦死した戦いは○○の戦い? | 湊川 | みなとがわ |
| 1335年、北条高時の遺児・時行が起こした反乱は「○○○の乱」? | 中先代 | なかせんだい |
| 『万葉集』に収められている和歌のひとつです | 東歌 | あずまうた |
| 夜明けの一歩手前に見られる薄明りの茜色の空 | 東雲 | しののめ |
| 妻にメリー喜多川を持つ代表作に『孤獨の人』がある作家 | 藤島泰輔 | ふじしまたいすけ |
| 二葉亭四迷の小説『浮雲』の主人公です | 内海文三 | うつみぶんぞう |
| 光明皇后によって設置された病人を治療する施設 | 施薬院 | せやくいん |
| 勝海舟が艦長を務めました | 咸臨丸 | かんりんまる |
| 木が茂って薄暗い様子 | 鬱蒼 | うっそう |
| 「きまりが悪い」「照れくさい」といった意味の表現です | 面映い | おもはゆい |
| 公武合体のため和宮と結婚した江戸幕府の将軍 | 徳川家茂 | とくがわいえもち |
| 「真田十勇士」の一人です | 海野六郎 | うんのろくろう |
| 「真田十勇士」の一人です | 筧十蔵 | かけいじゅうぞう |
| 官渡の戦いで曹操軍に敗れた中国・後漢王朝末期の大将軍 | 袁紹 | えんしょう |
| ケネディが最も尊敬した日本人に挙げた米沢藩の藩主 | 上杉鷹山 | うえすぎようざん |
| 作家・有島武郎の代表作は『カインの○○』? | 末裔 | まつえい |
| 小説『生まれ出づる悩み』や『カインの末裔』で有名な作家 | 有島武郎 | ありしまたけお |
| 20世紀前半にアメリカで活躍した日本人画家です | 国吉康雄 | くによしやすお |
| 『女人平家』『徳川の夫人たち』『鬼火』で知られる女流作家は? | 吉屋信子 | よしやのぶこ |
| インドへの旅で知られる「三蔵法師」とも呼ばれた僧 | 玄奘 | げんじょう |
| 「女戦国大名」と呼ばれた武将・今川義元の母親です | 寿桂尼 | じゅけいに |
| 「年月」のことを、星の巡りと冬の霜にたとえた表現 | 星霜 | せいそう |
| 織田信長の死後領土の配分を決めた会議 | 清州会議 | きよすかいぎ |
| 高熱などで意識の混濁した人が無意識に口走る言葉のこと | 譫言 | うわごと |
| 『黒い雨』『山椒魚』などの小説を著した作家です | 井伏鱒二 | いぶせますじ |
| 井伏鱒二の小説『黒い雨』の主人公の名前は? | 閑間重松 | しずましげます |
| 刷毛(はけ)で擦ったような跡がある土器です | 擦文土器 | さつもんどき |
| 平塚雷鳥を中心に結成されました | 青鞜社 | せいとうしゃ |
| 洋画家・岡田三郎助の妻であった女流小説家です | 岡田八千代 | おかだやちよ |
| 桓武天皇が大鴉から授かり平家に与えたという伝説の剣 | 小烏丸 | こがらすまる |
| 日本の国際連盟脱退が決まった会議の首席全権 | 松岡洋右 | まつおかようすけ |
| フランスの画家ミレーの代表作です | 落穂拾い | おちぼひろい |
| 『赤光』『あらたま』などの歌集があるアララギ派の歌人 | 斎藤茂吉 | さいとうもきち |
| 山内一豊の妻・千代を主人公にした、司馬遼太郎の歴史小説 | 功名が辻 | こうみょうがつじ |
| 本心ではないうわべだけの言葉 | 舌先三寸 | したさきさんずん |
| 代表作に『二神会舞図』がある「最後の文人」と呼ばれる画家 | 富岡鉄斎 | とみおかてっさい |
| 「肉を斬らせて骨を断つ」といわれた剣術の流派です | 示現流 | じげんりゅう |
| 将軍・足利義輝を暗殺した下剋上の典型とされる戦国武将 | 松永久秀 | まつながひさひで |
| 「四凶」の一つとされる中国神話に登場する怪物です | 渾沌 | こんとん |
| ラッキーな出来事をこのように言います | 僥倖 | ぎょうこう |
| 「必ず」「絶対に」という意味の副詞です | 急度 | きっと |
| 中国最古の王朝夏の建国者 | 禹 | う |
| アメリカ公使館通訳ヒュースケンを暗殺した薩摩藩の藩士です | 伊牟田尚平 | いむたしょうへい |
| 大河ドラマ『平清盛』の題字を書いたことで注目の女性書道家 | 金澤翔子 | かなざわしょうこ |
| 大化から数えて100番目の元号 | 嘉応 | かおう |
| 「起こる可能性がある」という意味の動詞です | 有り得る | ありうる |
| 修験道の山伏がかぶるずきん | 兜巾 | ときん |
| 映画『東京島』の主人公のモデルとなった「アナタハンの女王」 | 比嘉和子 | ひがかずこ |
| 「少しの間」「しばらく」という意味の言葉です | 暫時 | ざんじ |
| ひたすら突き進みます | 驀進 | ばくしん |
| 物事が相次いで現れることを野菜の名を使って何という? | 雨後の筍 | うごのたけのこ |
| 大阪夏の陣でも活躍した豊臣秀吉が創設した旗本衆 | 七手組 | ななてぐみ |
| 女優・朝丘雪路の父でもある美人画で有名な日本画家 | 伊東深水 | いとうしんすい |
| 真田昌幸・幸村親子に仕えた戦国武将 | 高梨内記 | たかなしないき |
| 戦国時代の分国法の一つです | 塵芥集 | じんかいしゅう |
| 江戸時代、旗本・御家人の代理で蔵米の取り引きをしました | 札差 | ふださし |
| 陽明学者の山田方谷が開発させた2~5本の歯がある農具 | 備中鍬 | びっちゅうぐわ |
| 南北朝時代に書かれた作者不詳の軍記物語です | 梅松論 | ばいしょうろん |
| 南北朝時代に大覚寺統と交互に皇位を継承した皇室の系統です | 持明院統 | じみょういんとう |
| 自分の身一つで他に頼むものがないことをいいます | 徒手空拳 | としゅくうけん |
| 「美人すぎる日本画家」として人気がある女性画家です | 松井冬子 | まついふゆこ |
| 比叡山の僧侶であった豊臣秀吉の五奉行のひとり | 前田玄以 | まえだげんい |
| 復讐のために耐え忍ぶこと | 臥薪嘗胆 | がしんしょうたん |
| 嘉吉の乱で殺された室町幕府第6代将軍 | 足利義教 | あしかがよしのり |
| 公文所を前身とする鎌倉幕府の機関です | 政所 | まんどころ |
| 日本で活躍するイギリス出身の作家C・W・ニコルの小説です | 勇魚 | いさな |
| 蒔岡家の四姉妹を描いた谷崎潤一郎の小説は? | 細雪 | ささめゆき |
| 谷崎潤一郎の小説『細雪』の主人公は○○家の四人姉妹? | 蒔岡 | まきおか |
| 豊臣秀吉の正室である高台院の通称です | 北政所 | きたのまんどころ |
| 摂政や関白の正妻を指す敬称 | 北政所 | きたのまんどころ |
| 第78回芥川賞を『蛍川』で受賞した作家です | 宮本輝 | みやもとてる |
| 日中戦争のきっかけとなったのは○○○事件? | 盧溝橋 | ろこうきょう |
| 後醍醐天皇の元で活躍した武将・楠木正成の幼名です | 多聞丸 | たもんまる |
| 後醍醐天皇の冥福を祈るために天龍寺を開山しました | 夢窓疎石 | むそうそせき |
| 源氏物語・第30帖のタイトルです | 藤袴 | ふじばかま |
| モンゴル帝国の創設者チンギス・ハンの幼名 | 鉄木真 | テムジン |
| フビライ・ハンが南宋を滅ぼしたのは1279年の○○の戦い? | 崖山 | がいざん |
| 現在の島根県西部にかつて存在した国です | 石見 | いわみ |
| 志賀直哉の長編小説『暗夜行路』の主人公 | 時任謙作 | ときとうけんさく |
| 『十六夜日記』を著した女流歌人 | 阿仏尼 | あぶつに |
| 日本最初の流通貨幣とされています | 和同開弥 | わどうかいちん |
| 恋人などとの仲を人前で得意気に話すこと | 惚気る | のろける |
| 悪いことをすればバチがあたるということ | 天罰覿面 | てんばつてきめん |
| 六歌仙の一人に数えられた平安時代の歌人です | 文屋康秀 | ふんやのやすひで |
| 作品『女』で有名な日本の彫刻家です | 荻原守衛 | おぎわらもりえ |
| 斎藤道三に仕えた美濃三人衆の一人です | 氏家卜全 | うじいえぼくぜん |
| 社会主義者・無政府主義者12名が死刑に | 大逆事件 | たいぎゃくじけん |
| 正宗白鳥の小説『何処へ』の主人公 | 菅沼健次 | すがぬまけんじ |
| 日本人として初めてノーベル文学賞候補となった人物です | 賀川豊彦 | かがわとよひこ |
| 皇帝が使用する印章のことです | 玉璽 | ぎょくじ |
| 愚かで、物事の道理を知らないこと | 無知蒙昧 | むちもうまい |
| 物事の本質を見抜いたり真偽を見分ける洞察力のこと | 慧眼 | けいがん |
| 物事の食い違いのことです | 齟齬 | そご |
| 中国四大奇書のひとつとされる西門慶を主人公とした小説は? | 金瓶梅 | きんぺいばい |
| まわりくどくて実用的でないこと | 迂遠 | うえん |
| 蜀の黄忠に討ち取られた中国・三国時代の魏の武将 | 夏侯淵 | かこうえん |
| 時間は円環運動をしているというドイツの哲学者ニーチェの思想 | 永劫回帰 | えいごうかいき |
| 宮本武蔵が霊巌洞で執筆したとされる兵法書です | 五輪書 | ごりんのしょ |
| 663年に倭国と新羅・唐の連合が戦ったのは「○○○の戦い」? | 白村江 | はくすきのえ |
| 丸橋忠弥とともに慶安の変を起こしました | 由井正雪 | ゆいしょうせつ |
| かすかな動揺のことをこうも言います | 細波 | さざなみ |
| 個人の罪による刑罰が親族にも及ぶという制度 | 縁坐制 | えんざせい |
| 「富士には月見草がよく似合う」という一節が有名な太宰治の小説 | 富嶽百景 | ふがくひゃっけい |
| 詩集『測量船』で有名な大阪府出身の詩人です | 三好達治 | みよしたつじ |
| 石原慎太郎の小説『太陽の季節』の主人公 | 津川竜哉 | つがわたつや |
| 五木寛之の小説『青春の門』の主人公 | 伊吹信介 | いぶきしんすけ |
| 道に外れて正しくないことや誠実でないこと | 邪な | よこしまな |
| 『不連続殺人事件』『堕落論』で知られる無頼派の作家です | 坂口安吾 | さかぐちあんご |
| 彫刻師の恋を描いた幸田露伴の小説です | 風流仏 | ふうりゅうぶつ |
| 被爆体験を基に書いた小説『夏の花』で有名な作家 | 原民喜 | はらたみき |
| あらゆる仕事を一人でたくみに処理する能力を持っていること | 八面六臂 | はちめんろっぴ |
| 901年に右大臣の菅原道真が大宰府に左遷された事件 | 昌泰の変 | しょうたいのへん |
| 初めは勢いがよいが最後は振るわないことをいう言葉 | 竜頭蛇尾 | りゅうとうだび |
| 恵美押勝の乱を平定した奈良時代の文人 | 吉備真備 | きびのまきび |
| 古人の優れた筆跡を一冊にまとめた書画帳のこと | 手鑑 | てかがみ |
| 盲目の三味線奏者を主人公とした谷崎潤一郎の小説 | 春琴抄 | しゅんきんしょう |
| 仙人になろうとする青年を主人公とした芥川龍之介の小説です | 杜子春 | とししゅん |
| 戦場で叫ぶ「鬨(とき)の声」をある動物を用いてこう言います | 鯨波 | げいは |
| 『見返り美人』で有名な江戸時代の浮世絵師です | 菱川師宣 | ひしかわもろのぶ |
| 効果○○、天罰○○? | 覿面 | てきめん |
| 正岡子規に師事した歌人・小説家です | 伊藤左千夫 | いとうさちお |
| 日明貿易では、これと区別するために勘合符が使われました | 倭寇 | わこう |
| 中国の都市・南京のかつての名前です | 建康 | けんこう |
| 琉球王国の最後の国王です | 尚泰王 | しょうたいおう |
| 代表作に縦に描いた『鮭』がある明治の洋画家です | 高橋由一 | たかはしゆいち |
| 日本人なら誰でも使えるものです | 仮字 | かな |
| 江戸時代初期に起こった幕府と朝廷が対立した事件 | 紫衣事件 | しえじけん |
| 難しくありません | 容易い | たやすい |
| 日清戦争後の下関条約で清が日本に割譲したのは○○諸島? | 澎湖 | ほうこ |
| 下関条約締結後に清の全権大使李鴻章を襲撃したテロリスト | 小山豊太郎 | こやまとよたろう |
| 奈良時代の743年に発布された法律は「○○○○私財法」? | 墾田永年 | こんでんえいねん |
| 1945年の神戸空襲で亡くなったエジソン唯一の日本人助手 | 岡部芳郎 | おかべよしろう |
| 南の方角を守るといわれる神様 | 朱雀 | すざく |
| 江戸時代の作家・滝沢馬琴を主人公とした芥川龍之介の小説 | 戯作三昧 | げさくざんまい |
| 田山花袋の小説『田舎教師』の主人公 | 林清三 | はやしせいぞう |
| 小説『田舎教師』『蒲団』で有名な作家です | 田山花袋 | たやまかたい |
| シルクスクリーンに代表される版画の分類の一つです | 孔版画 | こうはんが |
| 堂々とした立派な容姿で勇ましくきびきびとした様子 | 英姿颯爽 | えいしさっそう |
| 体をひねるような様子です | 仰け反る | のけぞる |
| システィナ礼拝堂の壁に描かれたミケランジェロの代表作です | 最後の審判 | さいごのしんぱん |
| 主人公の僧侶・宗朝の不思議な体験を描いた泉鏡花の小説です | 高野聖 | こうやひじり |
| 心の中にしまいこむことを「○○○に納める」という? | 胸三寸 | むねさんずん |
| 羽柴秀吉が柴田勝家を破った戦いの舞台となった山 | 賤ヶ岳 | しずがたけ |
| 19世紀ロシアの作家ゴーゴリの小説です | 外套 | がいとう |
| 井上靖の小説『闘牛』の主人公津上のモデルとなった人物です | 小谷正一 | こたにまさかず |
| 口語文法の仮定形に当たる文語文法の活用形です | 已然形 | いぜんけい |
| 戦いの始まりの合図として放たれた、音を立てる矢です | 鏑矢 | かぶらや |
| 聖徳太子が国書を送った随の第2代皇帝 | 煬帝 | ようだい |
| 現在の岡山県東北部にかつて存在した国です | 美作 | みまさか |
| 三国志でおなじみの武将・関羽が戦死したのは「○○の戦い」? | 樊城 | はんじょう |
| 城の裏側の門の別名は○○門? | 搦手 | からめて |
| 著書に『聖教要録』がある江戸時代の儒学者です | 山鹿素行 | やまがそこう |
| かつての日本海軍で根拠地として設置された機関 | 鎮守府 | ちんじゅふ |
| 呉・東晋・宋・斉・梁・陳の王朝をまとめてこう呼びます | 六朝 | りくちょう |
| 戒めを込めた短い言葉です | 箴言 | しんげん |
| 政治小説『経国美談』を書いた明治の作家は? | 矢野龍渓 | やのりゅうけい |
| 日本最古の漫画ともいわれる様々な生き物が描かれた巻物 | 鳥獣戯画 | ちょうじゅうぎが |
| 代表作に『西洋道中膝栗毛』『安愚楽鍋』がある明治の作家 | 仮名垣魯文 | かながきろぶん |
| 現在の中国・陝西省にある蜀の諸葛孔明が没した場所 | 五丈原 | ごじょうげん |
| 「悪いことをした」と感じて心を痛めること | 咎める | とがめる |
| 広瀬淡窓や稲村三伯の師匠である江戸時代の儒学者 | 亀井南冥 | かめいなんめい |
| 中国の易姓革命における君主の交代方法のひとつ | 放伐 | ほうばつ |
| 平安時代の京都で、安倍晴明とライバル関係にあった陰陽師 | 蘆屋道満 | あしやどうまん |
| 書道や絵画の作品が完成した後に作者が署名や押印をすること | 落款 | らっかん |
| 西太后が摂政を務めた中国・清朝の第11代皇帝 | 光緒帝 | こうしょてい |
| 京都の犯罪などを取り締まった平安時代に置かれた役職です | 検非違使 | けびいし |
| 何事にも動じないたとえ「○○の心」? | 匪石 | ひせき |
| 何事にも一言口を挟まないと気が済まない性格の人 | 一言居士 | いちげんこじ |
| 1940年に南京国民政府を樹立した中国の政治家です | 汪兆銘 | おうちょうめい |
| 明治維新後、大阪の商業の発展に尽力した人物です | 五代友厚 | ごだいともあつ |
| 大阪の法善寺横丁を舞台にした昭和の作家・織田作之助の小説 | 夫婦善哉 | めおとぜんざい |
| 小説『夫婦善哉』で知られる作家です | 織田作之助 | おださくのすけ |
| 本居宣長が書いた源氏物語の注釈書は『源氏物語○○○○』? | 玉の小櫛 | たまのおぐし |
| 画家として活動する石原慎太郎の四男です | 石原延啓 | いしはらのぶひろ |
| かな4文字で読んでください | 古 | いにしえ |
| 徳川家康の側近として活躍した人物です | 本多正信 | ほんだまさのぶ |
| 現在の千葉県中部にかつて存在した国です | 上総 | かずさ |
| こうするのもいい加減にしないと | 巫山戯る | ふざける |
| どんな困難にもひるまずくじけないこと | 不撓不屈 | ふとうふくつ |
| 助力を求めて頼りとします | 縋る | すがる |
| 明治に入って会津藩が移封されて青森県で誕生した藩です | 斗南藩 | となみはん |
| 中国・戦国時代の楚で使われたアリの顔に似た形の青銅貨幣 | 蟻鼻銭 | ぎびせん |
| 『古寺巡礼』『風土』などの著書で有名な日本の哲学者は? | 和辻哲郎 | わつじてつろう |
| 戦国時代の合戦で用いられた携帯用の食糧です | 干飯 | ほしいい |
| 室町時代から戦国時代にかけて下総国を本拠とした足利氏のこと | 古河公方 | こがくぼう |
| 埴谷雄高の小説『死霊』の主人公です | 三輪与志 | みわよし |
| 時期はずれで役に立たない物 | 夏炉冬扇 | かろとうせん |
| 役に立たない人や機転が利かない人のこと | 木偶坊 | でくのぼう |
| 地質年代で、第4紀前半の氷河時代にあたります | 更新世 | こうしんせい |
| 日本では奈良時代頃から使われ始めた赤色の顔料 | 鉛丹 | えんたん |
| 色々な物をひとまとめに扱うことです | 十把一絡げ | じっぱひとからげ |
| 仏教の開祖・釈迦の母です | 摩耶夫人 | まやふじん |
| 寺田屋で襲撃された坂本龍馬を救った槍の名手である長府藩士 | 三吉慎蔵 | みよししんぞう |
| 源頼光が酒呑童子を斬ったとされる刀は「○○○安綱」? | 童子切 | どうじぎり |
| 言葉巧みに信用させて相手を自分に従わせること | 言い包める | いいくるめる |
| 急いで駆けつけることを武士の様子に例えて何という? | 押っ取り刀 | おっとりがたな |
| 二つのものが接近して隣り合っていること | 一衣帯水 | いちいたいすい |
| 小説『英語屋さん』などのサラリーマン小説で有名な作家 | 源氏鶏太 | げんじけいた |
| これを貸して母屋を取られることもあります | 庇 | ひさし |
| 学問の道理をまげ、世間や権力者に気に入られるように振舞うこと | 曲学阿世 | きょくがくあせい |
| 他人の詩文を盗用することや頑固で融通がきかないこと | 活剝生呑 | かっぱくせいどん |
| 1837年に乱を起こした越後国の国学者 | 生田万 | いくたよろず |
| 威張って人を見下すことを意味する言葉です | 倨傲 | きょごう |
| 伊庭想太郎に刺殺された明治の政治家 | 星亨 | ほしとおる |
| 五街道とその付属街道以外の道路をこう呼びました | 脇街道 | わきかいどう |
| 大正デモクラシーの指導者・吉野作造が唱えました | 民本主義 | みんぽんしゅぎ |
| 2020年9月刊行の日本史上初『原典監訳 アヴェスタ』の作者 | 野田恵剛 | のだけいごう |
| 小さな利のため大きな損失をする事「○○を殺して狐狸を求む」? | 戎馬 | じゅうば |
| 歌人・斎藤茂吉を父にもつ芥川賞作家です | 北杜夫 | きたもりお |
| 自分の力を優れたものとして誇る気持ちのこと | 矜持 | きょうじ |
| 中国で起こった「安史の乱」の「史」とはこの人のこと | 史思明 | ししめい |
| 「馬脚を現す」と同じ意味の言葉を「何が剥げる」という? | 鍍金 | めっき |
| 天保の改革をした水野忠邦の長男で老中を務めたのは水野○○? | 忠精 | ただきよ |
| 「蛙の子は蛙」と同じ意味のことわざ「○の子は○」? | 蝮 | まむし |
| 明治初期に採用されていた1と6の付く日を休日とした制度 | 一六日 | いちろくび |
| お由羅騒動で切腹した薩摩島津家の重臣 | 赤山靱負 | あかやまゆきえ |
| 後で証拠となるような約束の言葉のこと | 言質 | げんち |
| 名君として讃えられている中国・清朝の第4代皇帝 | 康煕帝 | こうきてい |
| 著書に『天国にいちばん近い島』がある女流小説家です | 森村桂 | もりむらかつら |
| 後鳥羽上皇や後醍醐天皇が流されました | 隠岐 | おき |
| 2019年に亡くなった人間国宝の狂言師は五世○○○○? | 茂山千作 | しげやませんさく |
| 764年に反乱を起こした藤原仲麻呂の別名 | 恵美押勝 | えみのおしかつ |
| 豊臣秀吉が一夜城を作ったと伝えられています | 墨俣 | すのまた |
| 969年に左大臣・源高明が左遷された事件は○○の変? | 安和 | あんな |
| 芸術や学問などの分野に深い知識を持っていること | 造詣 | ぞうけい |
| 1946年に群馬県の岩宿で打製石器を発見した考古学者 | 相沢忠洋 | あいざわただひろ |
| 弓の弦に塗る粘着剤で、ことわざで待ち構える時にこれを引きます | 手薬練 | てぐすね |
| 文化大革命で台頭した中国の青年学生運動 | 紅衛兵 | こうえいへい |
| 戦国時代の合戦で取られた陣形の一つです | 雁行 | がんこう |
| 長々としゃべりたてること | 長広舌 | ちょうこうぜつ |
| 谷崎潤一郎の小説『痴人の愛』の主人公です | 河合譲治 | かわいじょうじ |
| 古墳時代から平安時代まで生産された青灰色の土器 | 須恵器 | すえき |
| 権力を得ようとして争うこと | 逐鹿 | ちくろく |
| 戦国時代に発達した、都市における自治的な協同組織です | 会合衆 | えごうしゅう |
| 江戸幕府第4代将軍・家綱の補佐役として活躍しました | 保科正之 | ほしなまさゆき |
| 『滑稽新聞』『面白半分』などの雑誌を発行したジャーナリスト | 宮武外骨 | みやたけがいこつ |
| 『後漢書』が出典の、泥棒を意味する言葉は「○○の君子」? | 梁上 | りょうじょう |
| 『後漢書』や『魏志倭人伝』に記されている倭人の国 | 奴国 | なのくに |
| オランダの学者スピノザが説いた哲学説 | 汎神論 | はんしんろん |
| たわいもないという意味「○○に等しい」? | 児戯 | じぎ |
| 始皇帝陵のものが有名な人や動物をかたどった人形です | 兵馬俑 | へいばよう |
| 現在の群馬県とほぼ同じ地域にかつて存在した国です | 上野 | こうずけ |
| 「要領よく立ち回る人」のことをある動物に例えてこう呼びます | 蝙蝠 | こうもり |
| 戦場で、部隊の士気を高めるため大勢で一緒に叫ぶ声のことです | 鬨の声 | ときのこえ |
| はなればなれになってしまうことです | 乖離 | かいり |
| 生前の行ないに基づいて死者に贈る称号 | 諡 | おくりな |
| かつて新聞を指して言われた言葉は「社会の○○」? | 木鐸 | ぼくたく |
| プロレタリア作家・小林多喜二の遺作となった小説です | 党生活者 | とうせいかつしゃ |
| ライト兄弟より120年も前に初めて空を飛んだ日本人 | 浮田幸吉 | うきたこうきち |
| 『小倉百人一首』にも歌が詠まれている奈良時代の歌人です | 山部赤人 | やまべのあかひと |
| 明治時代の翻訳家・黒岩涙香が創刊した日刊新聞 | 万朝報 | よろずちょうほう |
| がっくりとしています | 項垂れる | うなだれる |
| 1931年に日本の関東軍が鉄道を爆破したのは○○○事件? | 柳条湖 | りゅうじょうこ |
| 漫画家・白土三平の父であるプロレタリア画家です | 岡本唐貴 | おかもととうき |
| 日本に無教会主義を創始した明治・大正のキリスト教伝道者 | 内村鑑三 | うちむらかんぞう |
| 神事の前に飲食など慎み水浴で心身を清めること | 斎戒沐浴 | さいかいもくよく |
| 兄と大喧嘩をした日本神話に登場する神です | 山幸彦 | やまさちひこ |
| 清では漢民族にも強制された満州族の髪型です | 辮髪 | べんぱつ |
| 戦国時代、毛利元就や豊臣秀吉に仕えた外交僧 | 安国寺恵瓊 | あんこくじえけい |
| 日本神話で、神武天皇を道案内したとされる烏 | 八咫烏 | やたのからす |
| 『本当は恐ろしいグリム童話』で有名な女性2人からなる作家は? | 桐生操 | きりゅうみさお |
| 天文の乱においては義父の伊達稙宗を救出している戦国大名 | 相馬顕胤 | そうまあきたね |
| 直木賞を68歳と史上最年長で受賞した作家です | 星川清司 | ほしかわせいじ |
| 神様のご利益が明らかであることです | 灼たか | あらたか |
| 江戸幕府の将軍に直属した旗本や御家人の総称 | 直参 | じきさん |
| 何もしゃべらない状態をいった表現は「口を○○」? | 噤む | つぐむ |
| 「利休七哲」の一人で織田信長の弟にあたる茶人 | 織田有楽斎 | おだうらくさい |
| 平城京と平安京を南北に走っていた大通り | 朱雀大路 | すざくおおじ |
| きたない言葉で、悪口を並べ立ててののしること | 罵詈雑言 | ばりぞうごん |
| 陸軍の基礎を確立した第3代・9代内閣総理大臣 | 山県有朋 | やまがたありとも |
| 父とともに討ち入りに参加した赤方浪士の一人 | 大石主税 | おおいしちから |
| 大佛次郎の小説『赤穂浪士』などを手掛けた挿絵画家 | 岩田専太郎 | いわたせんたろう |
| 氏姓制度の「姓」のひとつ | 造 | みやつこ |
| 現在の千葉県北部と茨城県南部にかつて存在した国です | 下総 | しもうさ |
| 19世紀フランスの作家モーパッサンのデビュー作は? | 脂肪の塊 | しぼうのかたまり |
| 658年に軍船180隻を率いて蝦夷を討ったと伝えられます | 阿倍比羅夫 | あべのひらふ |
| 日本最大級の縄文集落跡といえば○○○○遺跡? | 三内丸山 | さんないまるやま |
| 息子に作家の逢坂剛を持った主に時代小説を手がけた挿絵画家 | 中一弥 | なかかずや |
| 利益や権利を独占すること | 壟断 | ろうだん |
| あまり上手ではありません | 拙い | つたない |
| 仲間に加わることや味方することを意味する言葉です | 与する | くみする |
| 作家・島崎藤村の小説『破戒』の主人公は? | 瀬川丑松 | せがわうしまつ |
| 中山道の追分と北陸道の高田を結んだ江戸時代の街道です | 北国街道 | ほっこくかいどう |
| ことばによる情報教育に関する本を多数執筆している言語学者 | 外山滋比古 | とやましげひこ |
| 気持ちが大きく快活で小さなことにこだわらないこと | 豪放磊落 | ごうほうらいらく |
| 戦国武将・徳川家康の生母は○○の方? | 於大 | おだい |
| 「寛政の三博士」の一人です | 古賀精里 | こがせいり |
| 日本で最も大きい装飾古墳は岡山市にある「○○古墳」? | 造山 | つくりやま |
| 契約書や納品書など取引を証明する書類を○○書類という? | 証憑 | しょうひょう |
| 物事の完成させるための最後の大事な仕上げのことです | 画竜点睛 | がりょうてんせい |
| 北条時宗に招かれ来日し円覚寺を開いた南宋の僧侶 | 無学祖元 | むがくそげん |
| 富田常雄の小説『姿三四郎』に登場するヒロインです | 村井乙美 | むらいおとみ |
| 代表作に『バラと少女』がある1919年に22歳で死去した洋画家 | 村山槐多 | むらやまかいた |
| 『鞍馬天狗』『パリ燃ゆ』などの小説を書いた作家 | 大佛次郎 | おさらぎじろう |
| 秦の始皇帝が建設した宮殿 | 阿房宮 | あぼうきゅう |
| 「田中ビネ-知能検査」に名を残す日本の心理学者 | 田中寛一 | たなかかんいち |
| 「無駄に」という意味の副詞です | 徒に | いたずらに |
| 小説『黴』『あらくれ』で有名な明治生まれの作家です | 徳田秋声 | とくだしゅうせい |
| 皮膚や物の表面がなめらかなこと | 肌理 | きめ |
| 中国・清の時代の地税と人頭税を合わせた税制 | 地丁銀 | ちていぎん |
| 詩集『山羊の歌』で有名な山口県生まれの詩人です | 中原中也 | なかはらちゅうや |
| 立場や主張がはっきりしていること | 旗幟鮮明 | きしせんめい |
| 物事がうまく運んで満足して喜ぶこと | 悦に入る | えつにいる |
| 大日本帝国海軍で建造された綾波型駆逐艦の7番艦 | 朧 | おぼろ |
| 大日本帝国海軍で建造された陽炎型駆逐艦の9番艦 | 天津風 | あまつかぜ |
| 平安時代中期に貴族の慶滋保胤が著した随筆 | 池亭記 | ちていき |
| 三木一草の一人に数えられた南北朝時代の武将です | 結城親光 | ゆうきちかみつ |
| 鎌倉・室町時代、港や大都市で運輸や取引を行ないました | 問丸 | といまる |
| 自分の子供をへりくだっていう言葉です | 豚児 | とんじ |
| 1947年に玉川大学の初代学長に就任した心理学者 | 田中寛一 | たなかかんいち |
| 新選組による池田屋事件で亡くなった土佐出身の人物 | 望月亀弥太 | もちづきかめやた |
| 礼儀をわきまえないこと | 不躾 | ぶしつけ |
| 戦後農民文学の金字塔と呼ばれる小説『荷車の歌』の作者 | 山代巴 | やましろともえ |
| 明治時代に日本で最初の外交官を務めました | 鮫島尚信 | さめしまなおのぶ |
| 中国最初の統一王朝秦の都です | 咸陽 | かんよう |
| どんなつらいことがあっても心を動かさず堪え忍ぶこと | 堅忍不抜 | けんにんふばつ |
| 現在の山口県東部にかつて存在した国です | 周防 | すおう |
| 自由律俳句で有名な山口県出身の俳人です | 種田山頭火 | たねださんとうか |
| 2人の皇后が唐の政治を混乱させた事件 | 武韋の禍 | ぶいのか |
| 乙女山古墳などに代表されるのは「○○貝型古墳」? |
ほたて
| 徳川家光が東海寺を開かせた僧侶です |
たくあん
| 川の中の小さな穴を舞台にした井伏鱒二の小説です |
さんしょううお
| 女優アルカージナが登場するチェーホフの小説は? |
かもめ
| ベランジェを主人公とした劇作家イヨネスコの代表作は? |
サイ
| 朝鮮戦争の別名は「○○○○○○○戦争」? |
アコーディオン
| 安楽死をテーマにした森鴎外の短編小説です |
たかせぶね

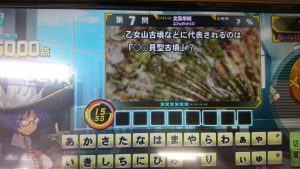

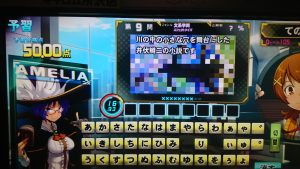
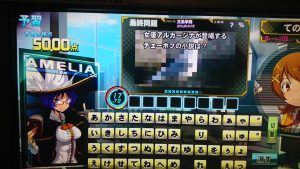
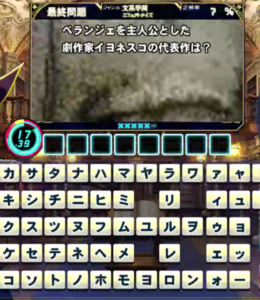
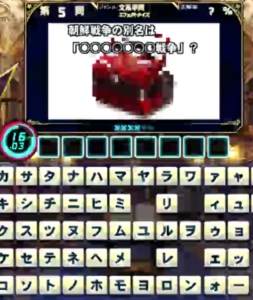
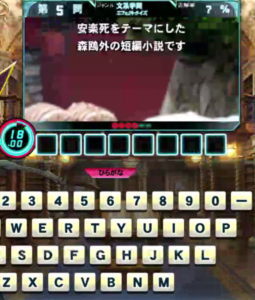
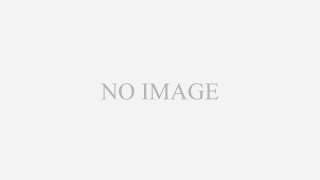
コメント