| けちのアルパゴンを主人公としたモリエールの小説です | 守銭奴 | しゅせんど |
| 第二次世界大戦前のスローガン | 挙国一致 | きょこくいっち |
| ロカンタンを主人公としたサルトルの小説 | 嘔吐 | おうと |
| フランスの哲学者サルトルの代表作です | 存在と無 | そんざいとむ |
| 後々の世まで長く残る作品は「○○の名作」 | 不朽 | ふきゅう |
| 律令制の下で九州防衛のために置かれた兵士 | 防人 | さきもり |
| 東条英機内閣のもとで1942年に行われた選挙は○○選挙? | 翼賛 | よくさん |
| ナターシャが登場するトルストイの小説です | 戦争と平和 | せんそうとへいわ |
| 1156年、この事件のあと崇徳上皇は讃岐に流されました | 保元の乱 | ほうげんのらん |
| 1910年に刊行された石川啄木の処女詩集です | 一握の砂 | いちあくのすな |
| 石川啄木の第二歌集の題名は『悲しき○○』? | 玩具 | がんぐ |
| 中国における禅宗の始祖とされるインド出身の僧侶 | 達磨 | だるま |
| 多くの人が周りを取り囲んで見ていること | 衆人環視 | しゅうじんかんし |
| 「結局は」という意味合いで使う副詞です | 所詮 | しょせん |
| 幕末に土佐藩士の中岡慎太郎が結成した軍隊 | 陸援隊 | りくえんたい |
| 最重要ポイントです | 肝心要 | かんじんかなめ |
| お互いに差がありません | 均等 | きんとう |
| シルクロードを描いた作品などで有名な、2009年に亡くなった画家 | 平山郁夫 | ひらやまいくお |
| 『小倉百人一首』にも和歌が収められている平安時代の歌人 | 蝉丸 | せみまる |
| 「細々と暮らしていく」という意味の言葉「○○をしのぐ」? | 糊口 | ここう |
| 気取ったりせずありのままであること | 天真爛漫 | てんしんらんまん |
| 自分の行為を再考し反省すること | 省みる | かえりみる |
| 中国や日本の遺跡から出土した古代の文字が記された木の札 | 木簡 | もっかん |
| 1981年に小説『人間万事塞翁が丙午』で直木賞を受賞しました | 青島幸男 | あおしまゆきお |
| 清が藩部の管理のために置いた中央官庁 | 理藩院 | りはんいん |
| お釈迦様の入滅から56億7000万年後に現れるとされています | 弥勒菩薩 | みろくぼさつ |
| 平安時代前期に活躍した六歌仙のひとりです | 小野小町 | おののこまち |
| 物事の隠れた面に重点を置いて記述する歴史のこと | 裏面史 | りめんし |
| 非協調的な態度を取ることを指す表現は「○○を向く」? | 外方 | そっぽ |
| 「真田十勇士」の一人です | 穴山小助 | あなやまこすけ |
| 「真田十勇士」の一人です | 由利鎌之助 | ゆりかまのすけ |
| 「真田十勇士」の一人です | 根津甚八 | ねづじんぱち |
| 西郷隆盛が奄美大島に潜居した際に結婚した妻 | 愛加那 | あいかな |
| 心痛や病気のためにやつれること | 憔悴 | しょうすい |
| 元々は遊女の言葉だった「結構だ」という意味の表現 | 御の字 | おんのじ |
| ナオミをヒロインとした谷崎潤一郎の小説です | 痴人の愛 | ちじんのあい |
| 土、国、一向などがあります | 一揆 | いっき |
| 鎌倉幕府で御家人統制や警察の役割を担った機関 | 侍所 | さむらいどころ |
| 『三国志演義』では劉備、関羽、張飛がここで呂布と戦いました | 虎牢関 | ころうかん |
| 『三国志演義』で董卓と呂布が争った絶世の美女 | 貂蝉 | ちょうせん |
| 訳詩集『海潮音』で知られる日本の詩人です | 上田敏 | うえだびん |
| 戦国時代に活躍した軍師です | 山本勘助 | やまもとかんすけ |
| 戦国時代に北条家に仕えたとされる忍者集団の頭領 | 風魔小太郎 | ふうまこたろう |
| 手探りの状態を意味する四字熟語 | 五里霧中 | ごりむちゅう |
| 手探りの状態を意味する四字熟語 | 暗中模索 | あんちゅうもさく |
| 絶対王政の権力を支えたのは官僚とこれ | 常備軍 | じょうびぐん |
| 絶対王政の根拠となった近世ヨーロッパの○○○○説? | 王権神授 | おうけんしんじゅ |
| おもしろおかしい様子です | 滑稽 | こっけい |
| 時任謙作を主人公とした志賀直哉唯一の長編小説は? | 暗夜行路 | あんやこうろ |
| 話を大げさにする例えは「○○をつける」? | 尾鰭 | おひれ |
| 江戸時代の画家・尾形光琳の代表作は『○○○○図屏風』? | 風神雷神 | ふうじんらいじん |
| 石器時代と鉄器時代の間は○○○時代? | 青銅器 | せいどうき |
| 若く未熟な人をあざけってこれが「黄色い」と表現します | 嘴 | くちばし |
| 伝説上の存在とされている初代琉球国王 | 舜天 | しゅんてん |
| 現在の茨城県北東部にかつて存在した国です | 常陸 | ひたち |
| 他人につらく当たることを意味する言葉は「○○にする」? | 足蹴 | あしげ |
| 他人に先んじられることを「○○を排す」という? | 後塵 | こうじん |
| 1999年に発掘され注目を浴びた和同開珎以前の通貨 | 富本銭 | ふほんせん |
| 娘を描いた作品『麗子像』で有名な近代日本絵画の巨匠 | 岸田劉生 | きしだりゅうせい |
| お嬢様などに対してよく使う清らかな様子を指す熟語 | 清楚 | せいそ |
| 江戸時代に武士が領地を治めたことをこう言います | 知行 | ちぎょう |
| 『赤頭巾ちゃんに気をつけて』で芥川賞を受賞した作家は? | 庄司薫 | しょうじかおる |
| 反対語は「粋」です | 野暮 | やぼ |
| 「徹底的に」という意味の表現「○○無きまで」? | 完膚 | かんぷ |
| 現在の広島県西部にかつて存在した国です | 安芸 | あき |
| あなたに任せます | 委ねる | ゆだねる |
| 落ちぶれることです | 凋落 | ちょうらく |
| 君主にそむいて兵を挙げること | 謀反 | むほん |
| 「長征」と呼ばれる大移動で中国共産党の軍が行き着きました | 延安 | えんあん |
| 607年に随に渡りました | 小野妹子 | おののいもこ |
| 林羅山によって江戸幕府の官学になりました | 朱子学 | しゅしがく |
| 江戸幕府の直轄領のこと | 天領 | てんりょう |
| 江戸時代の奉行所で法廷にあたる場所 | 白洲 | しらす |
| 「自画自賛」と同じ意味です | 手前味噌 | てまえみそ |
| 印象派の画家モネの代表作です | 日傘の女 | ひがさのおんな |
| 印象派の画家モネの代表作です | 睡蓮 | すいれん |
| 相手の言った言葉をそっくりそのまま言い返すこと | 鸚鵡返し | おうむがえし |
| 第一次世界大戦から使われた銃撃から身を守る穴 | 塹壕 | ざんごう |
| 無頼派の作家・坂口安吾の代表作です | 堕落論 | だらくろん |
| 小説『金閣寺』で知られる作家三島由紀夫の命日を何という? | 憂国忌 | ゆうこくき |
| 奈良時代に始まった漆工芸の一種 | 蒔絵 | まきえ |
| メソポタミアなど古代オリエントで使用された文字 | 楔形文字 | くさびがたもじ |
| 江戸幕府で将軍と老中の間を取り次いだ役職 | 側用人 | そばようにん |
| 中世日本の同業者組合 | 座 | ざ |
| 中国語で使われている簡略化されていない漢字 | 繁体字 | はんたいじ |
| 現在の大分県とほぼ同じ地域にかつて存在した国です | 豊後 | ぶんご |
| 日本とパリを拠点に活動したアンフォルメルの画家 | 今井俊満 | いまいとしみつ |
| 叱咤激励すること「○○をかける」? | 発破 | はっぱ |
| 賈宝玉を主人公とした中国の古典文学です | 紅楼夢 | こうろうむ |
| 小説『破戒』『夜明け前』や詩集『若菜集』で有名な作家 | 島崎藤村 | しまざきとうそん |
| 小説『高野聖』『婦系図』で有名な明治生まれの作家 | 泉鏡花 | いずみきょうか |
| 老人問題を題材とした有吉佐和子の小説です | 恍惚の人 | こうこつのひと |
| 手ごたえがないことを意味することわざは「○○に腕押し」? | 暖簾 | のれん |
| 織田信長の旗印となった明から輸入された貨幣 | 永楽銭 | えいらくせん |
| 大化の改新後に6歳以上の男女に配られました | 口分田 | くぶんでん |
| 貫一とお宮を主人公とした小説『金色夜叉』の作者は? | 尾崎紅葉 | おざきこうよう |
| 森鴎外の小説『舞姫』で踊り子と恋に落ちる主人公 | 太田豊太郎 | おおたとよたろう |
| 桜田門外の変で暗殺された幕末の大老 | 井伊直弼 | いいなおすけ |
| 心の迷いを、かずらと藤の枝のもつれにたとえた熟語 | 葛藤 | かっとう |
| 瀬川丑松を主人公とした島崎藤村の小説です | 破戒 | はかい |
| 他を全てを忘れて熱中することを意味する言葉です | 血眼 | ちまなこ |
| 他のものより際立ってすぐれています | 出色 | しゅっしょく |
| 剣豪・机竜之助を主人公とする中里介山の小説は? | 大菩薩峠 | だいぼさつとうげ |
| 日本人初のノーベル文学賞受賞者です | 川端康成 | かわばたやすなり |
| 警察予備隊→○○○→自衛隊 | 保安隊 | ほあんたい |
| 『わだつみのいろこの宮』や『海の幸』で有名な画家です | 青木繁 | あおきしげる |
| 中国の武将・李克用と日本の武将伊達政宗に共通する異名 | 独眼竜 | どくがんりゅう |
| 前田慶次郎らが有名です | 傾奇者 | かぶきもの |
| 現在は「瀋陽」と呼ばれるかつての満州国最大の都市 | 奉天 | ほうてん |
| レベッカ・シャープを主人公としたサッカレーの小説は? | 虚栄の市 | きょえいのいち |
| 明治政府が日比谷に設けた欧風の社交場 | 鹿鳴館 | ろくめいかん |
| 経験者のほうが優っていること | 一日の長 | いちじつのちょう |
| 従来のやり方をそのまま受け継ぐこと | 踏襲 | とうしゅう |
| 東京女子大学の初代学長を務めました | 新渡戸稲造 | にとべいなぞう |
| お腹いっぱいまで食べること | 鱈腹 | たらふく |
| 田山花袋の小説『蒲団』で主人公の小説家の名前は? | 竹中時雄 | たけなかときお |
| 若い頃に身に付けた腕前は衰えない例え「昔取った○○」? | 杵柄 | きねづか |
| 過去に鍛えた腕前を誇る言葉は「昔とった○○」? | 杵柄 | きねづか |
| 織田信長が焼き打ちしました | 延暦寺 | えんりゃくじ |
| 19世紀にアメリカで起きた内戦です | 南北戦争 | なんぼくせんそう |
| ペリー率いる黒船が来航したときの元号 | 嘉永 | かえい |
| 幽霊のお露が登場する三遊亭圓朝の怪談は? | 牡丹灯籠 | ぼたんどうろう |
| 中国・新朝の軍事組織です | 八旗 | はっき |
| 時おり芸能人の作品が入賞し話題となる美術展覧会です | 二科展 | にかてん |
| 『雁の寺』『飢餓海峡』などの小説で有名な作家です | 水上勉 | みずかみつとむ |
| 西郷隆盛、板垣退助、江藤新平らが主張しました | 征韓論 | せいかんろん |
| 日銀総裁と内閣総理大臣の両方を務めた唯一の人物です | 高橋是清 | たかはしこれきよ |
| 安楽死をテーマとした森鴎外の小説です | 高瀬舟 | たかせぶね |
| こうすると豚も木に登ります | 煽てる | おだてる |
| 939年に乱を起こし「新皇」を名乗った武将 | 平将門 | たいらのまさかど |
| 「トリックスター論」などの文化理論で知られた文化人類学者 | 山口昌男 | やまぐちまさお |
| 日露戦争後のポーツマス条約で日本の全権を務めました | 小村寿太郎 | こむらじゅたろう |
| 本屋大賞と直木賞をダブル受賞した『蜜蜂と遠雷』の作者 | 恩田陸 | おんだりく |
| 寺山修司の劇団「天井桟敷」の美術担当だったデザイナーです | 横尾忠則 | よこおただのり |
| プロレタリア文学の代表作『蟹工船』の作者です | 小林多喜二 | こばやしたきじ |
| 坂本龍馬が最後を遂げた京都の醤油屋 | 近江屋 | おうみや |
| フランスのケネーらが主張した経済思想です | 重農主義 | じゅうのうしゅぎ |
| 物事に必要以上にこだわり気にかけることです | 拘泥 | こうでい |
| 長野県長野市にあった武田信玄が築いたお城 | 松代城 | まつしろじょう |
| 熱にあてられて頭がぼうっとしてしまうこと | 逆上せる | のぼせる |
| 「五大老」の一人でもある戦国時代の武将です | 前田利家 | まえだとしいえ |
| 大正時代に活躍した画家竹久夢二の代表作です | 黒船屋 | くろふねや |
| 頭数に応じて数を分け合うこと | 按分 | あんぶん |
| 美しく飾りたてた言葉 | 美辞麗句 | びじれいく |
| 代表作に『落葉』『黒き猫』がある明治期の日本画家です | 菱田春草 | ひしだしゅんそう |
| 臣・連・君・直などがあった古代の豪族の称号 | 姓 | かばね |
| 倉敷の大原美術館が収蔵しているエル・グレコの絵画です | 受胎告知 | じゅたいこくち |
| 漢の武帝が朝鮮に設置しました | 楽浪郡 | らくろうぐん |
| 『浮世風呂』『浮世床』などで知られる江戸時代の戯作者です | 式亭三馬 | しきていさんば |
| 明治から昭和初期にかけて活躍した宮崎県出身の歌人 | 若山牧水 | わかやまぼくすい |
| 『柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺』という俳句の作者は? | 正岡子規 | まさおかしき |
| 約束を破ることを「○○にする」といいます | 反故 | ほご |
| ためらうことです | 躊躇 | ちゅうちょ |
| 江戸時代の武士が持っていた特権のひとつ | 切捨御免 | きりすてごめん |
| 豊臣秀吉が京都に造営した華麗な大邸宅 | 聚楽第 | じゅらくだい |
| キリスト教が日本に伝来した時のカトリック宣教師の呼び名です | 伴天連 | バテレン |
| 随筆『方丈記』で有名な鎌倉時代の人物です | 鴨長明 | かものちょうめい |
| 戦国時代の合戦で取られた陣形の一つです | 長蛇 | ちょうだ |
| 歴史書の記述法のひとつです | 編年体 | へんねんたい |
| 中国・後漢末期の農民反乱「黄巾の乱」の首謀者です | 張角 | ちょうかく |
| 第一国立銀行の初代頭取を務めました | 渋沢栄一 | しぶさわえいいち |
| スサノオノミコトに退治された日本神話に登場する大蛇です | 八岐大蛇 | ヤマタノオロチ |
| 265年に魏の元帝の禅譲を受け西普を建国しました | 司馬炎 | しばえん |
| 小説『牛肉と馬鈴薯』『武蔵野』で有名な作家 | 国木田独歩 | くにきだどっぽ |
| 真面目でで堅苦しいことを、ある漢数字を使った言葉で何という? | 四角四面 | しかくしめん |
| 明治生まれの作家徳田秋声の小説です | 仮装人物 | かそうじんぶつ |
| 現在の千葉県南部にかつて存在した国です | 安房 | あわ |
| 中国・三国時代の名軍師諸葛亮の終生のライバルです | 司馬懿 | しばい |
| わが国の初代天皇は○○天皇? | 神武 | じんむ |
| 代表作の『浮雲』やロシア文学の翻訳で知られる明治時代の作家 | 二葉亭四迷 | ふたばていしめい |
| 小説『放浪記』『浮雲』『めし』で有名な女流作家 | 林芙美子 | はやしふみこ |
| 同等か目下の人に対して苦労に感謝していたわること | 労う | ねぎらう |
| 特殊的な例から普遍的な規則を見出そうとする推論方法のこと | 帰納法 | きのうほう |
| 現在の福岡県東部から大分県北部にかけて、かつて存在した国です | 豊前 | ぶぜん |
| 物事がはっきりしない様子のこと | 曖昧模糊 | あいまいもこ |
| 切腹をする武士の後ろから首を刀ではねること | 介錯 | かいしゃく |
| 司馬遷が紀伝体で著した歴史書 | 史記 | しき |
| 『宵待草』などの詩を残すなど多方面で活躍した画家 | 竹久夢二 | たけひさゆめじ |
| 調子に乗って付け上がること | 増長 | ぞうちょう |
| 1999年に大量の富本銭が発見された「○○○工房遺跡」? | 飛鳥池 | あすかいけ |
| 徳川家康が派遣しました | 朱印船 | しゅいんせん |
| 1911年に清朝を倒して中華民国を立てた革命 | 辛亥革命 | しんがいかくめい |
| 伊勢湾口に浮かぶ神島を舞台にした三島由紀夫の小説 | 潮騒 | しおさい |
| 執権・北条時頼が置いた評定衆の補佐役 | 引付衆 | ひきつけしゅう |
| 大坂城や駿府城に置かれた江戸幕府の役職です | 城代 | じょうだい |
| 宮沢賢治が生前に刊行した詩集 | 春と修羅 | はるとしゅら |
| 1960年に新日米安保を調印した総理大臣 | 岸信介 | きしのぶすけ |
| 俳句雑誌「ほととぎす」で活躍した松山市生まれの俳人 | 高浜虚子 | たかはまきょし |
| ドイツの哲学者ハイデガーの著書です | 存在と時間 | そんざいとじかん |
| 平安時代に貴族の間で行われた球を蹴りあう遊びです | 蹴鞠 | けまり |
| 悲しみと喜びを交互に味わうこと | 悲喜交交 | ひきこもごも |
| 鎌倉幕府が朝廷の動きを監視するために設けた機関 | 六波羅探題 | ろくはらたんだい |
| 北条早雲によって討たれた堀越公方・足利政知の子 | 茶々丸 | ちゃちゃまる |
| 非常にむごたらしい様子のこと | 阿鼻叫喚 | あびきょうかん |
| 非常に恥ずかしい気持ちを表した言葉は「?の至り」 | 汗顔 | かんがん |
| 戦国時代のようにあまたの英雄が覇を争うこと | 群雄割拠 | ぐんゆうかっきょ |
| 馬主でもあった作家の菊池寛が広めた格言 | 無事之名馬 | ぶじこれめいば |
| 箱館戦争で戦死した新選組の副長です | 土方歳三 | ひじかたとしぞう |
| 怖気づくことを「○○○に吹かれる」という? | 臆病風 | おくびょうかぜ |
| ちらっと見ること | 一瞥 | いちべつ |
| 1894年に撤廃されました | 治外法権 | ちがいほうけん |
| 実際にはなかったことを事実であるかのようにでっちあげること | 捏造 | ねつぞう |
| 2011年に縄文時代のクワガタムシの全身が出土された奈良県の遺跡 | 秋津遺跡 | あきついせき |
| 1996年に文化功労者にも選ばれたアメリカ生まれの写真家 | 石元泰博 | いしもとやすひろ |
| 樋口一葉の小説『たけくらべ』の主人公 | 美登利 | みどり |
| 残さずすべて | 一切合財 | いっさいがっさい |
| インド神話の神ヴァイシュラヴァナを原型とする仏教の神 | 毘沙門天 | びしゃもんてん |
| 嫌な夢を見るとこうなります | 魘される | うなされる |
| 人目をはばからずに勝手気ままな行動をすること | 傍若無人 | ぼうじゃくぶじん |
| 大坂夏の陣で千姫を救った坂崎出羽守はここの藩主でした | 津和野藩 | つわのはん |
| 奈良県天理市の石上神宮にある百済から伝来したとされる刀 | 七支刀 | しちしとう |
| 一時しのぎの対応をすること | 姑息 | こそく |
| 多くのものの中で一番です | 随一 | ずいいち |
| 小林一茶の俳句「雀の子そこのけそこのけ”?”が通る」 |
おうま
| 坂本龍馬がここで襲撃されました |
てらだや
| 戦国時代の武将・直江兼続の兜にあしらわれた文字は? |
あい
| 星座の名前にもなっているルネサンスの三大発明のひとつ |
らしんばん
| 九州の志賀島で発見されました |
きんいん
| 足利義政が建立したのは○○寺? |
ぎんかく
| ハート型、みみずく型などがあります |
どぐう
| ナツメそうの『坊っちゃん』に登場する、校長先生のあだ名です |
たぬき
| パレスチナからシリアにいたる地域は「肥沃な○○○地帯」? |
みかづき
| 横山芳子と竹中時雄の恋愛を描いた田山花袋の小説は? |
ふとん

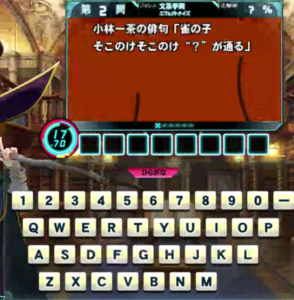

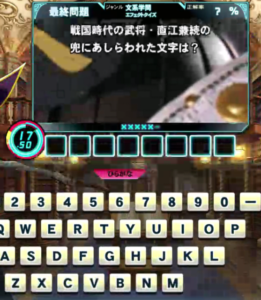
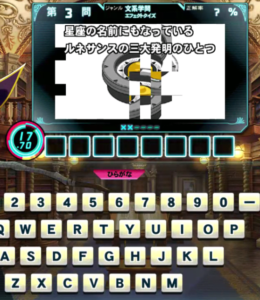
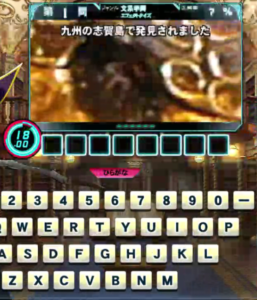

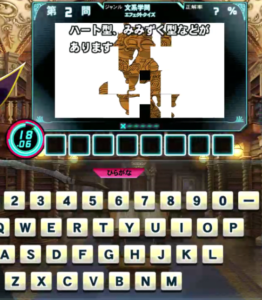
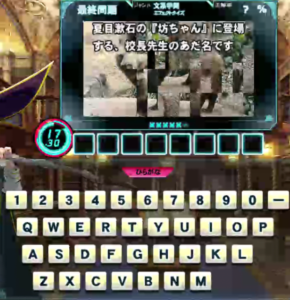
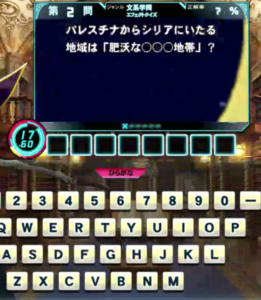
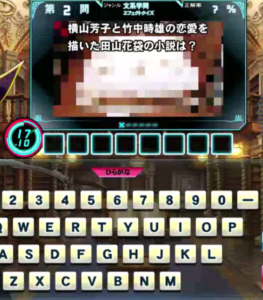
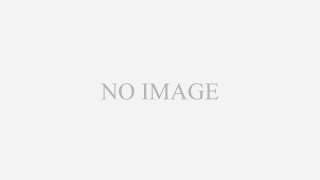
コメント