| 作家ゴーゴリと芥川龍之介の小説に共通するタイトルです | 鼻 | はな |
| 日本の元号を五十音順に並べると最後にくるのは? | 和銅 | わどう |
| 天下統一を目指した戦国大名です | 織田信長 | おだのぶなが |
| 天下統一を成し遂げた戦国大名です | 豊臣秀吉 | とよとみひでよし |
| 天下統一を成し遂げた戦国大名です | 徳川家康 | とくがわいえやす |
| 中国・三国時代の一国です | 魏 | ぎ |
| 文における成分の一つです | 主語 | しゅご |
| 大和朝廷から派遣された使節 | 遣隋使 | けんずいし |
| オイルショックを日本語でいうと? | 石油危機 | せきゆきき |
| 太平洋戦争の際、日本軍に奇襲攻撃を受けました | 真珠湾 | しんじゅわん |
| 「マヌ」や「ハムラビ」が有名 | 法典 | ほうてん |
| 地獄に落ちたカンダタを主人公とする芥川龍之介の小説です | 蜘蛛の糸 | くものいと |
| 英語で「コック」はオンドリ「ピーコック」はこの鳥です | 孔雀 | くじゃく |
| あまねく行き渡ること | 普及 | ふきゅう |
| 代表作に『老猿』『西郷隆盛像』がある明治の彫刻家は? | 高村光雲 | たかむらこううん |
| 茶の湯を大成しました | 千利休 | せんのりきゅう |
| 現在の奈良県とほぼ同じ地域にかつて存在した国です | 大和 | やまと |
| 戦国時代に登場した「種子島」とも呼ばれる銃器 | 火縄銃 | ひなわじゅう |
| アメリカ、イギリスなどで用いられる言語です | 英語 | えいご |
| 天皇に代わって国政をとります | 摂政 | せっしょう |
| 戦国時代の発端となったのは「○○の乱」? | 応仁 | おうにん |
| 1912年に滅亡した中国最後の王朝です | 清 | しん |
| ことわざで「習わぬ経を読む」小僧がいます | 門前 | もんぜん |
| ドイツ帝国宰相・ビスマルクのカトリック弾圧政策 | 文化闘争 | ぶんかとうそう |
| イギリスの元首相チャーチルの演説で有名「?のカーテン」 | 鉄 | てつ |
| 太田豊太郎を主人公とした明治の作家・森鴎外の小説 | 舞姫 | まいひめ |
| 早起きするとこれだけ得します | 三文 | さんもん |
| 二葉亭四迷と林芙美子に共通する小説のタイトル | 浮雲 | うきぐも |
| 戦いに敗れた武将の身の処し方です | 自害 | じがい |
| 小説『高瀬舟』や『舞姫』を書いた明治の文豪は? | 森鴎外 | もりおうがい |
| 琉球王朝の都が置かれました | 首里 | しゅり |
| お城の中心をなすヤグラのことです | 天守閣 | てんしゅかく |
| 江戸幕府が町人や農民に作らせた隣保組織 | 五人組 | ごにんぐみ |
| 元気がなくしょげるさまを「○○に塩」という? | 青菜 | あおな |
| イギリスと清の間に起こった戦争の原因ともなった麻薬 | 阿片 | アヘン |
| 「一挙両得」と同じ意味の言葉をある動物を使って何という? | 一石二鳥 | いっせきにちょう |
| ドラマ『水戸黄門』でもおなじみの江戸時代に薬を入れた道具 | 印籠 | いんろう |
| 水戸黄門の「黄門」はこの官職のこと | 中納言 | ちゅうなごん |
| 自分自身にうぬぼれてしまうこと | 自己陶酔 | じことうすい |
| 現在の山口県北西部にかつて存在した国です | 長門 | ながと |
| 戦国武将・北条早雲の別名は「伊勢○○○」? | 新九郎 | しんくろう |
| 重要なことと、つまらないことを逆に扱ってしまうこと | 本末転倒 | ほんまつてんとう |
| シルクロードを日本語でいうと「”何”の道」? | 絹 | きぬ |
| 考古学上、石器、青銅器の次はこの時代です | 鉄器 | てっき |
| 何かにつけていがみあってばかり | 犬猿の仲 | けんえんのなか |
| オランダの画家ゴッホが好んで題材にした花です | 向日葵 | ひまわり |
| オランダ商館が置かれました | 出島 | でじま |
| 未だに知られていません | 未知 | みち |
| 縄文時代の人々が食べた貝殻や動物の骨を捨てた場所 | 貝塚 | かいづか |
| 「随」に代わって中国を統一 | 唐 | とう |
| 中国を代表する観光名所である「○○の長城」? | 万里 | ばんり |
| 歌集『一握の砂』『悲しき玩具』で有名な明治末期の歌人は? | 石川啄木 | いしかわたくぼく |
| 罪や責めをまぬがれるためのもの | 免罪符 | めんざいふ |
| 海外では通じません | 和製英語 | わせいえいご |
| 1941年に竣工された旧日本海軍最大の戦艦 | 大和 | やまと |
| 梁山泊に集まった108人の豪傑たちの物語です | 水滸伝 | すいこでん |
| 能ある○は爪を隠す | 鷹 | たか |
| 「いい国作ろう!」 | 鎌倉幕府 | かまくらばくふ |
| けちな人は「ここに火をともす」と言われる体の部分 | 爪 | つめ |
| 「伝教大師」と呼ばれました | 最澄 | さいちょう |
| 信仰のために命を捧げること | 殉教 | じゅんきょう |
| 鴨長明によって書かれた有名な随筆です | 方丈記 | ほうじょうき |
| 正岡子規の俳句は「柿くへば鐘が鳴るなり○○○」? | 法隆寺 | ほうりゅうじ |
| 多くの戦国武将たちがこれを目指しました | 天下統一 | てんかとういつ |
| ことわざで、棒が出てきたり蛇が出てきたり | 藪 | やぶ |
| 武士が打刀とともに腰に差した短い刀 | 脇差 | わきざし |
| 作家・井上靖の芥川賞受賞作です | 闘牛 | とうぎゅう |
| シェークスピアの『リア王』も『マクベス』も『ハムレット』も | 悲劇 | ひげき |
| 現存するわが国最古の歴史書 | 古事記 | こじき |
| 高橋泥舟・山岡鉄舟とともに「幕末三舟」と呼ばれました | 勝海舟 | かつかいしゅう |
| 江戸幕府第13代将軍徳川家定の正室です | 篤姫 | あつひめ |
| 随筆『徒然草』で有名な鎌倉時代の人物です | 吉田兼好 | よしだけんこう |
| ふだんは農業などをしているがいくさの時には兵になります | 足軽 | あしがる |
| 7世紀前後の、奈良盆地南部に都が置かれていた時代 | 飛鳥時代 | あすかじだい |
| 決して自分のものにはできないたとえです | 高嶺の花 | たかねのはな |
| 645年に始まる日本最初の年号 | 大化 | たいか |
| ひどい失敗を犯して二度とするまいと思うこと | 懲りる | こりる |
| 1853年、ペリーが黒船を率い来航したところです | 浦賀 | うらが |
| 邪馬台国の女王です | 卑弥呼 | ひみこ |
| 1866年に同盟を結びました | 薩長 | さっちょう |
| 律令時代の税のひとつ | 租 | そ |
| 木版画をするときに欠かせない美術道具です | 馬連 | ばれん |
| 経験豊富でしたたかなこと | 海千山千 | うみせんやません |
| 庶民には「義賊」と呼ばれて人気を集めた江戸時代の盗賊 | 鼠小僧 | ねずみこぞう |
| 隠れキリシタン摘発に用いたキリストなどの像を刻んだ板 | 踏絵 | ふみえ |
| 「心の窓」だったり、「口ほどに物を言う」こともあったりします |
め
| 最初は「詩人」という題名だったロダンの彫刻です |
かんがえるひと
| 薩長同盟の立役者です |
さかもとりょうま



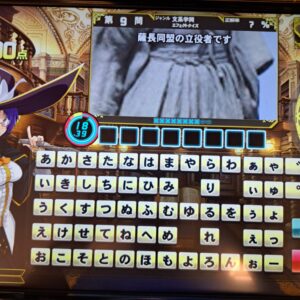
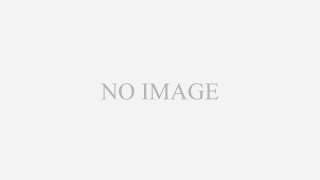
コメント