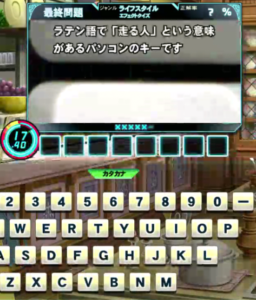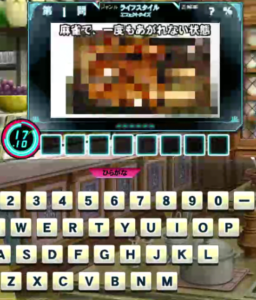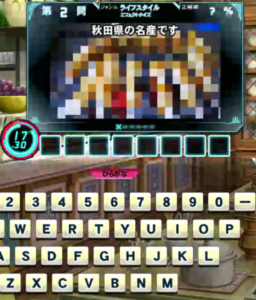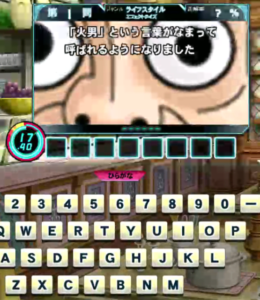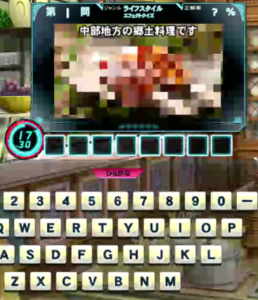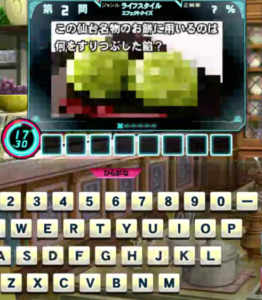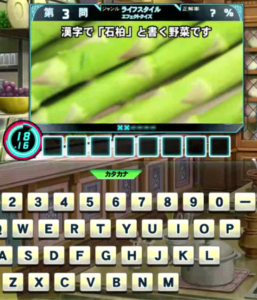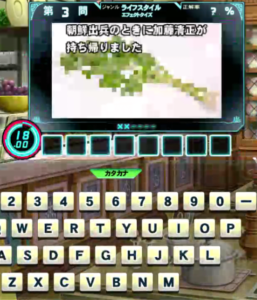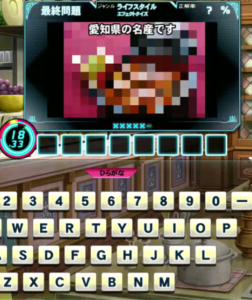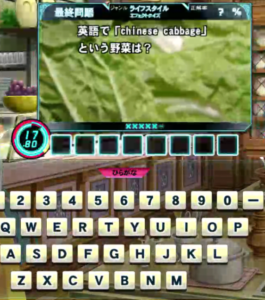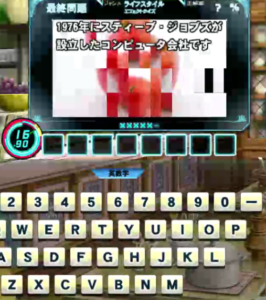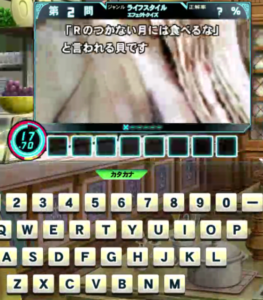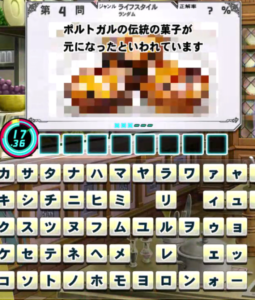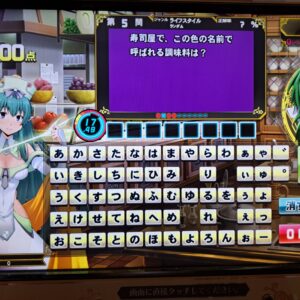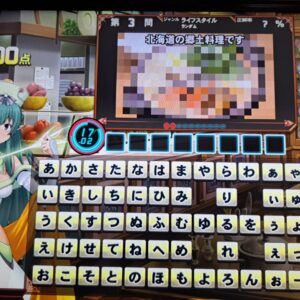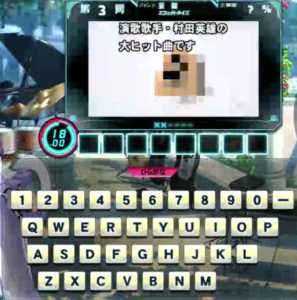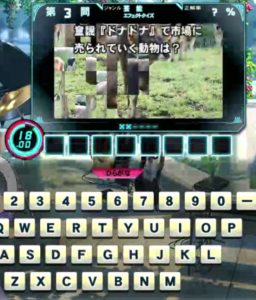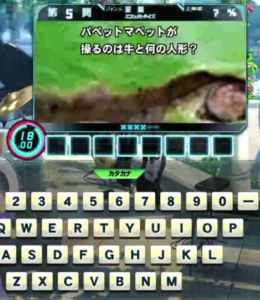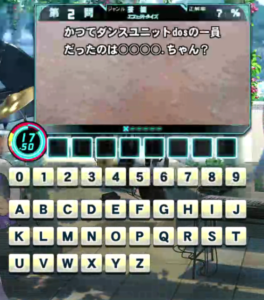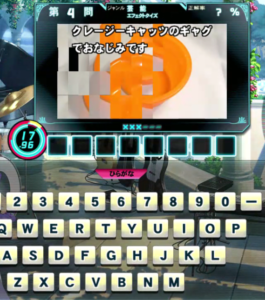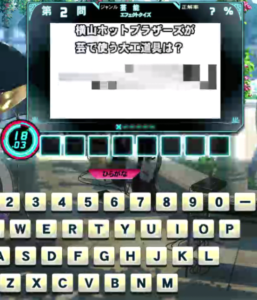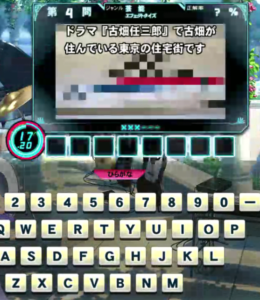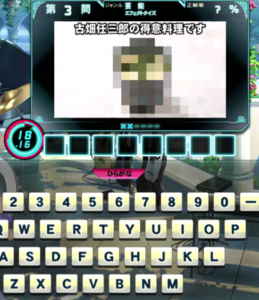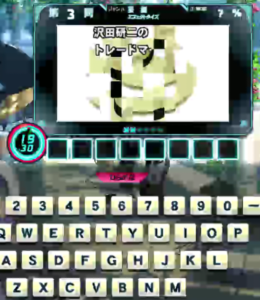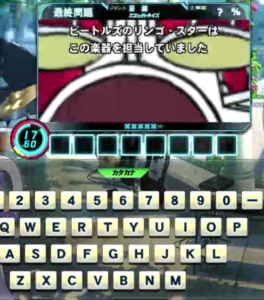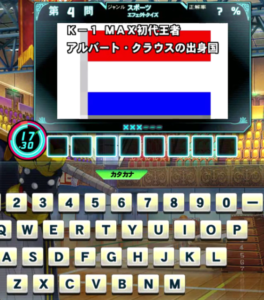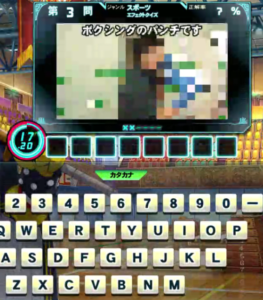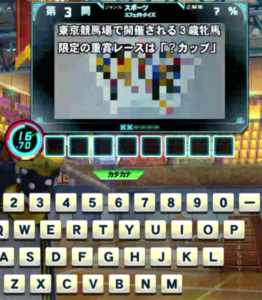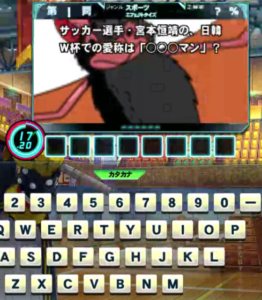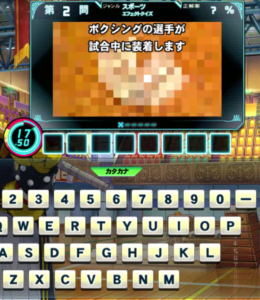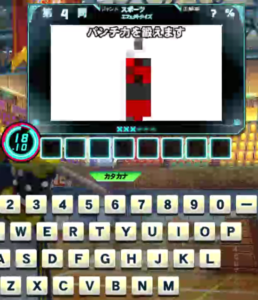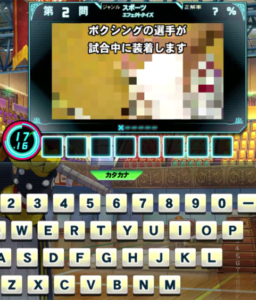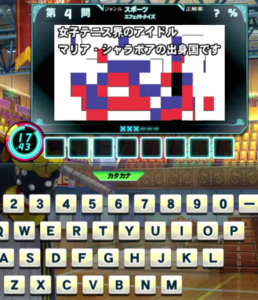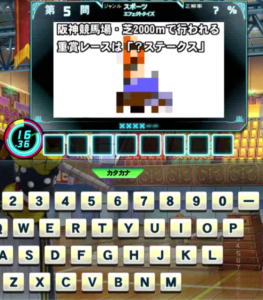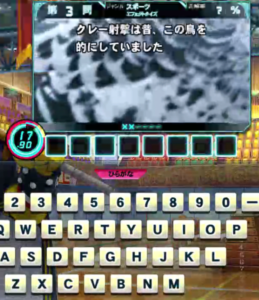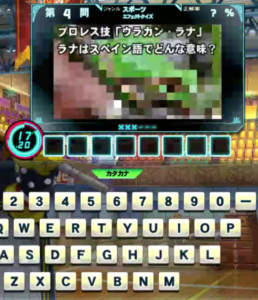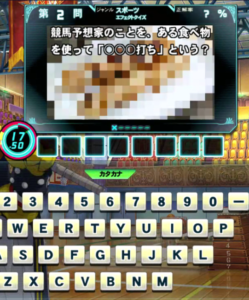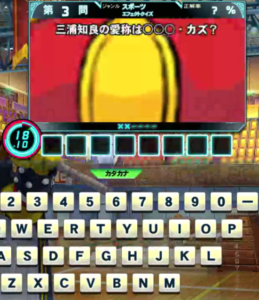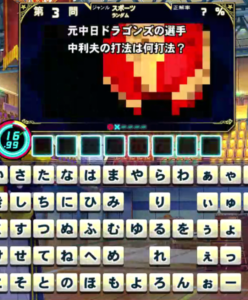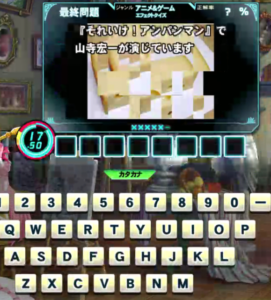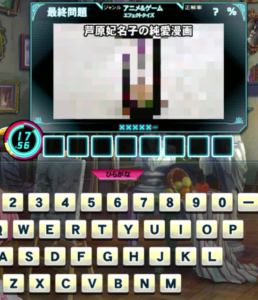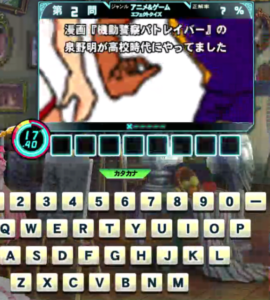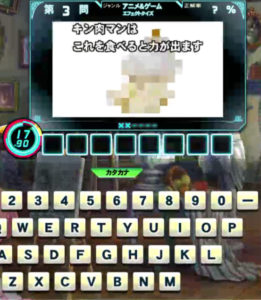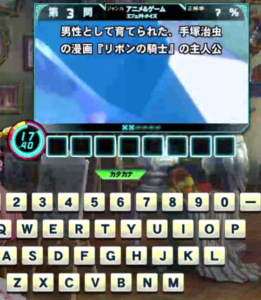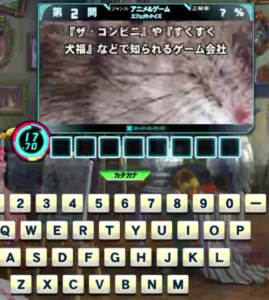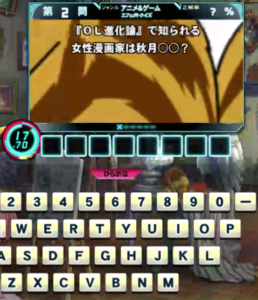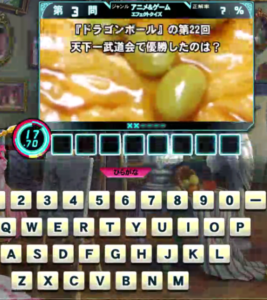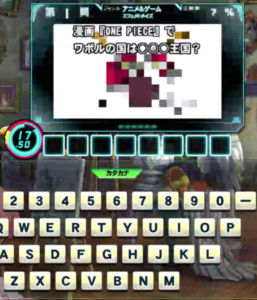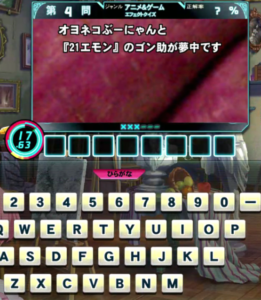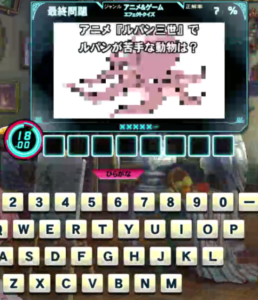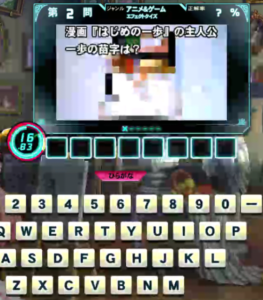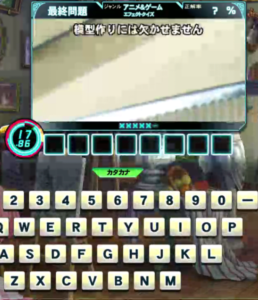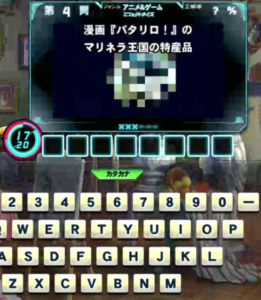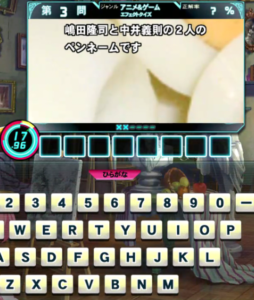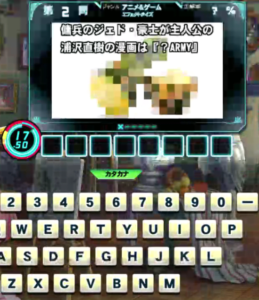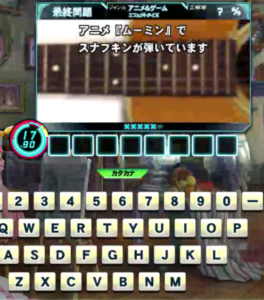| 星一徹がひっくり返すイメージがあります | 卓袱台 | ちゃぶだい |
| 出店の「りんご飴」によく用いられるリンゴの品種 | 姫小町 | ひめこまち |
| 活字の書体の一つです | 明朝体 | みんちょうたい |
| 盆の終わりに行なう、先祖の霊を送る行事は「○○流し」? | 精霊 | しょうろう |
| 中国から帰化した林浄因が日本に伝えたとされています | 饅頭 | まんじゅう |
| プロフェッショナルの人のことです | 玄人 | くろうと |
| 熊本県の郷土料理です | 辛子蓮根 | からしれんこん |
| 将棋で、うっかりしたミスで負けることを何という? | 頓死 | とんし |
| 将棋で、正式な初段並みの実力を持つ人のことをこう呼びます | 田舎初段 | いなかしょだん |
| 映画でチャップリンが着用したダービーハットとも呼ばれる帽子 | 山高帽 | やまたかぼう |
| 掛け軸の両端に下げる重りのこと | 風鎮 | ふうちん |
| 怪談『牡丹灯籠』に登場する幽霊です | お露 | おつゆ |
| おせち料理によく入っています | 栗金団 | くりきんとん |
| インターネット上で人気を呼んだ中国製ロボット | 先行者 | せんこうしゃ |
| 芥川賞と直木賞の選考会が行われる東京都・築地の料亭 | 新喜楽 | しんきらく |
| 普段着のことを「礼服」に対してこういいます | 平服 | へいふく |
| 悪役がよくお似合い | 強面 | こわもて |
| 「暑さが峠を越えた頃」とされる8月にある二十四節気の一つ | 処暑 | しょしょ |
| 衝撃的な結末が話題となった作家・貫井徳郎のデビュー作です | 慟哭 | どうこく |
| 小説『利休にたずねよ』で第140回直木賞を受賞しました | 山本兼一 | やまもとけんいち |
| 大きく燃え広がる前に消し止められた火事のこと | 小火 | ぼや |
| 京都の下鴨神社で生まれた食べ物です | 御手洗団子 | みたらしだんご |
| 2019年に史上初の女流6冠を達成した将棋の棋士です | 里見香奈 | さとみかな |
| 誘いが多くてモテモテです | 引く手数多 | ひくてあまた |
| 柳川鍋には、背開きにしたこれが欠かせません | 泥鰌 | どじょう |
| 柳川鍋には、笹掻きにしたこれが欠かせません | 牛蒡 | ごぼう |
| 歳暮や中元に贈ることが多いもの | 手拭 | てぬぐい |
| 俗に「武士は食わねど○○○」といいます | 高楊枝 | たかようじ |
| 一流選手を数多く育てた優秀な指導者のことです | 名伯楽 | めいはくらく |
| 生きていくための収入を得る仕事のことです | 生業 | なりわい |
| ガラスや友情に入ったりします | 罅 | ひび |
| 別名を「ひもかわ」ともいう名古屋名物です | 棊子麺 | きしめん |
| 名古屋名物です | 外郎 | ういろう |
| 坊主が上手に坊主の絵を描きます | 屏風 | びょうぶ |
| いばった様子で勝手気ままに振る舞うことを意味する言葉 | 闊歩 | かっぽ |
| 電動歯ブラシなど外出先で使う電化製品の、家電に対する呼び名 | 外電 | そとでん |
| 赤ちゃんのオムツのことです | 御湿 | おしめ |
| 魚のすり身から作られ鍋料理の具となります | 摘入 | つみれ |
| 豆腐を固めるために用います | 滷汁 | にがり |
| 雑誌「STORY」などで活躍するカリスマ主婦モデルです | 前田典子 | まえだのりこ |
| これを気にする人は多いようです | 世間体 | せけんてい |
| 秋の味覚です | 秋刀魚 | さんま |
| 山形の秋の風物詩です | 芋煮会 | いもにかい |
| 俗に「男の顔」にたとえられます | 履歴書 | りれきしょ |
| 俗に「女の顔」にたとえられます | 請求書 | せいきゅうしょ |
| 団体や企業が行動の目標として掲げる主義・主張のこと | 旗印 | はたじるし |
| 関連のある人や物が次々と明らかになること | 芋蔓式 | いもづるしき |
| 持ち帰り寿司専門の全国チェーン店です | 京樽 | きょうたる |
| 山で返ってくるものです | 木霊 | こだま |
| ぼんやりしています | 朦朧 | もうろう |
| 恋人にこれをかけられているとビックリします | 二股 | ふたまた |
| おいたが過ぎる子どものことです | 悪戯っ子 | いたずらっこ |
| バストをボリュームアップする美容整形手術の一つです | 豊胸術 | ほうきょうじゅつ |
| 苗代から田んぼに移す頃の苗です | 早苗 | さなえ |
| 中居正広の主演で映画化もされた宮部みゆきの代表作です | 模倣犯 | もほうはん |
| 薄型テレビにおける画面の明るさのことです | 輝度 | きど |
| 「心根が卑しい」という意味の相手を罵倒するための言葉 | 下衆 | げす |
| どんぐりの背くらべ | 五十歩百歩 | ごじっぽひゃっぽ |
| 旺文社が発行している大学受験生向けの月刊雑誌 | 螢雪時代 | けいせつじだい |
| 子どもや芸術家はこれが豊かといわれます | 感受性 | かんじゅせい |
| 50%以下に精米した白米を原料とする清酒 | 大吟醸 | だいぎんじょう |
| 麻雀で、あがりの牌を間違えてしまうことです | 錯和 | チョンボ |
| 麻雀で、配牌の時にすでにあがりの形が完成している役満 | 天和 | テンホー |
| 麻雀で、これをする時には千点棒を場に出します | 立直 | リーチ |
| 結婚式場で新婦の世話係を務める女性のことです | 介添人 | かいぞえにん |
| 乳幼児や子供の用品を専門に取り扱うチェーンストアです | 西松屋 | にしまつや |
| セレブのために用意されたシートのことです | 貴賓席 | きひんせき |
| 男にはちょっとした「これ」も必要です | 拘り | こだわり |
| 結婚披露宴の招待客へのおみやげ | 引出物 | ひきでもの |
| 鬼のアイテムとして読んでください | 鉄棒 | かなぼう |
| 果物のことを指す言葉です | 水菓子 | みずがし |
| 盗賊や悪党などが隠れ住んでいる場所のことです | 巣窟 | そうくつ |
| 常に敷きっぱなしで片付けられていない布団です | 万年床 | まんねんどこ |
| 左右の扉が中央から両側に開く仕組み | 観音開き | かんのんびらき |
| おエラいさんのそばにいつもべったり | 腰巾着 | こしぎんちゃく |
| 1996年に七冠の偉業を成し遂げた将棋棋士 | 羽生善治 | はぶよしはる |
| 園芸用の肥料などに用いられる堆積した落ち葉が朽ちてできた土 | 腐葉土 | ふようど |
| カード破産を題材とした宮部みゆきの代表作です | 火車 | かしゃ |
| 『焦茶色のパステル』で江戸川乱歩賞を受賞しました | 岡嶋二人 | おかじまふたり |
| 葬儀に際して当主を務める人のことです | 喪主 | もしゅ |
| 「10円カレー」で有名な日比谷公園にあるレストランです | 松本楼 | まつもとろう |
| 企業や団体に宛てる手紙で「様・殿」の代わりに使います | 御中 | おんちゅう |
| 囲碁のタイトル戦の一つです | 碁聖戦 | ごせいせん |
| 全身を見ることができる大型の鏡のことです | 姿見 | すがたみ |
| アメリカを拠点に活動しているバスフィッシングのプロです | 大森貴洋 | おおもりたかひろ |
| 2008年に登録された鳥取県産の赤梨の品種です | 新甘泉 | しんかんせん |
| 名門・名士の子弟のことです | 御曹司 | おんぞうし |
| 山梨県南アルプス市で開発された「世界で最も重いスモモ」 | 貴陽 | きよう |
| 地酒ブームの火付け役となった福島県の純米吟醸酒 | 飛露喜 | ひろき |
| フラフープをやり過ぎるとなると噂された病気です | 腸捻転 | ちょうねんてん |
| 今までの成り行きのことです | 次第 | しだい |
| 電車などに無賃乗車することをこのようにもいいます | 煙管 | キセル |
| 囲碁で、基盤の中央にうたれた点のことです | 天元 | てんげん |
| 腕前を披露する晴れの場所 | 檜舞台 | ひのきぶたい |
| 気の利かない人のことをこういいます | 唐変木 | とうへんぼく |
| 茹でた鶏肉をごまだれで食べる中国・四川料理の一つです | 棒棒鶏 | バンバンジー |
| 最高級のウーロン茶です | 鉄観音 | てつかんのん |
| 高級”生”食パンの専門店 | 乃が美 | のがみ |
| 干したものは中華料理の高級食材としても使われます | 鮑 | あわび |
| 花札では「雨」と呼ばれる植物です | 柳 | やなぎ |
| 主食ではないものです | 御菜 | おかず |
| 「コム・デ・ギャルソン」を展開する日本人デザイナー | 川久保玲 | かわくぼれい |
| 長野県の郷土料理である鶏もも肉のから揚げ | 山賊焼 | さんぞくやき |
| 一つでも失われると元へは戻せません | 欠片 | かけら |
| お正月の飾りに使われるミカン科の果物です | 橙 | だいだい |
| 正月の縁起物として神社で売られます | 破魔矢 | はまや |
| 歯にはさまったものを取り除く時に用います | 爪楊枝 | つまようじ |
| クタクタに疲れることです | 疲労困憊 | ひろうこんばい |
| かつて日本で製造されていたオートバイのブランド | 陸王 | りくおう |
| 家畜の肉や骨から作られ肥料・飼料として用いられます | 肉骨粉 | にくこっぷん |
| 2011年に同じく芥川賞作家の川上未映子と結婚しました | 阿部和重 | あべかずしげ |
| 女子トイレの必需である装置です | 音姫 | おとひめ |
| 安楽に、悠々と暮らすさまを「○○○」という? | 左団扇 | ひだりうちわ |
| 顔色が悪くて何だか弱そうな人 | 青瓢箪 | あおびょうたん |
| お酒を飲む時に使う器です | お猪口 | おちょこ |
| 将棋で、必要な時にいつでも取ることができる状態の駒のこと | 質駒 | しちごま |
| 高い所へ昇るのに使います | 梯子 | はしご |
| ミカンやタチバナに代表される果物の総称です | 柑橘類 | かんきつるい |
| 京都の一乗寺に本店を構える老舗のラーメン店です | 天天有 | てんてんゆう |
| 日本初のブライダル専門店を作ったデザイナーです | 桂由美 | かつらゆみ |
| 将棋におけるハンディキャップのこと | 駒落ち | こまおち |
| シウマイでおなじみです | 崎陽軒 | きようけん |
| 日本女性の美しさを花にたとえた言葉です | 大和撫子 | やまとなでしこ |
| ふたまたをかけることです | 両天秤 | りょうてんびん |
| 登山やキャンプで使う携帯用の炊飯器です | 飯盒 | はんごう |
| 「オヤジギャル」という流行語を生んだ漫画家は○○○ゆつこ? | 中尊寺 | ちゅうそんじ |
| 2011年に将棋の第1期リコー杯女流王座戦を制した女流棋士 | 加藤桃子 | かとうももこ |
| 駐車場によく書いてある1ヶ月単位の契約を表す言葉 | 月極 | つきぎめ |
| 底に板を入れた巾着袋です | 信玄袋 | しんげんぶくろ |
| 『小倉百人一首』を使った競技かるたの名人戦が行われます | 近江神宮 | おうみじんぐう |
| 麻雀の基本的な役です | 平和 | ピンフ |
| 「史上最強の棋士」とも評される将棋の十五世名人です | 大山康晴 | おおやまやすはる |
| お釈迦様の骨を語源とするすし飯を指す言葉です | 舎利 | しゃり |
| 必要以上に誇張した様子を言います | 大袈裟 | おおげさ |
| ちょっと誇張しすぎのことです | 大袈裟 | おおげさ |
| プロ棋士を目指す者が所属する日本将棋連盟の研修機関 | 奨励会 | しょうれいかい |
| 「なっとういち」などの製品で知られる食品会社は○○食品? | 旭松 | あさひまつ |
| 新潟県長岡市の大和屋が販売する日本三大銘菓の一つです | 越乃雪 | こしのゆき |
| ケガをすると必要になるものです | 繃帯 | ほうたい |
| これに取り組む熟年世代の女性が増えているそうです | 離活 | りかつ |
| 魚を白焼きにしてから、骨が軟らかくなるまで煮込みます | 甘露煮 | かんろに |
| オーダーメイドの服でサイズをはかることです | 採寸 | さいすん |
| 靴や書類とじで紐を通すまたの小穴のことです | 鳩目 | はとめ |
| 自動車を運転する際に加入が義務付けられている保険 | 自賠責保険 | じばいせきほけん |
| 寒い冬には欠かせない暖房具です | 炬燵 | こたつ |
| 2005年に小説『天使のナイフ』で江戸川乱歩賞を受賞しました | 薬丸岳 | やくまるがく |
| ちらし寿司によくのっています | 錦糸卵 | きんしたまご |
| どことなく怪しくて油断ができない様子です | 胡散臭い | うさんくさい |
| 衣服や調度品などを入れる蓋が付いた長方形の大きな箱 | 長持 | ながもち |
| 麻雀で、他人の捨て牌であがることです | 栄和 | ロンホー |
| 宮内早生温州みかんとトロビタオレンジの交配種 | 清見 | きよみ |
| 小さい声で言葉を口にします | 呟く | つぶやく |
| ふてくされて寝ること | 不貞寝 | ふてね |
| 苦難の多い人生のことをこういいます | 茨の道 | いばらのみち |
| チョークを日本語でいうと? | 白墨 | はくぼく |
| 麻雀で、他の2人を無視して特定の1人と順位を争うこと | 差し馬 | さしうま |
| 間接的に温める方法です | 湯煎 | ゆせん |
| 相手に強く願う言葉です | 何卒 | なにとぞ |
| 囲碁や将棋の、対局での手順が記録されています | 棋譜 | きふ |
| 対人関係をスムーズにするためにも重要なことです | 挨拶 | あいさつ |
| 何から何まで回分だらけの泡坂妻夫の小説です | 喜劇悲喜劇 | きげきひきげき |
| 築地から豊州に移転した大正元年創業の老舗カレー屋 | 中栄 | なかえい |
| モラルに欠けた行動を取った時にはこれを買います | 顰蹙 | ひんしゅく |
| サンタクロースがトナカイに曳かせます | 橇 | そり |
| おひたしにして食べると美味しい野菜 | 菠薐草 | ほうれんそう |
| 奈良県生駒市が名産地である抹茶を点てる時に用いる茶道具 | 茶筅 | ちゃせん |
| 小さな新設大きなお世話 | 有難迷惑 | ありがためいわく |
| どこからともなくやってくる人物です | 風来坊 | ふうらいぼう |
| 酒や味噌を作るのに不可欠です | 麹 | こうじ |
| 手紙文を結ぶ言葉のひとつ | 敬具 | けいぐ |
| 奄美大島産の黒砂糖を使用した和歌山県名物の黒飴です | 那智黒 | なちぐろ |
| 物を種類によって区分けすること | 分別 | ぶんべつ |
| 魚の調理に適した和包丁の一種 | 出刃包丁 | でばぼうちょう |
| 子供に教え込むのが親の務めです | 躾 | しつけ |
| 名探偵・明智小五郎の助手といえば○○少年? | 小林 | こばやし |
| 「五目並べ」の別名です | 連珠 | れんじゅ |
| 健康によい冬場の体の温めかた | 頭寒足熱 | ずかんそくねつ |
| ベニバナで染めた濃い紅赤色のことです | 唐紅 | からくれない |
| この占いの分野では藤木相元が有名です | 観相学 | かんそうがく |
| 細かい点まで調べることです | 詮索 | せんさく |
| パソコンでデータ交換に用いる「MO」といえば「?ディスク」 | 光磁気 | ひかりじき |
| 「オムライス発祥の店」とされる東京・銀座にある洋食レストラン | 煉瓦亭 | れんがてい |
| 昔はおおらかな様子をこのように表現しました | 大陸的 | たいりくてき |
| 2011年の年末よりブームとなっている調味料です | 塩麹 | しおこうじ |
| 紅白、金銀、白黒などの種類があります | 水引 | みずひき |
| 第131回芥川賞を受賞したモブ・ノリオの小説 | 介護入門 | かいごにゅうもん |
| 香川の名物です | 饂飩 | うどん |
| 落雁や煎餅のような水分の少ない乾燥した和菓子の総称です | 干菓子 | ひがし |
| 2016年に史上初めて七冠同時制覇を達成した囲碁棋士です | 井山裕太 | いやまゆうた |
| 大塚製薬「オロナミンC」のキャッチフレーズにもある言葉 | 溌剌 | はつらつ |
| お天前で使う水をためておく茶道具の名前です | 水指 | みずさし |
| 一年で最初の「国民の祝日」です | 元日 | がんじつ |
| アメリカの祝日・感謝祭には欠かせない動物です | 七面鳥 | しちめんちょう |
| 根拠がないこと | 出鱈目 | でたらめ |
| パタパタと動かして風をおこす道具です | 扇 | おうぎ |
| 昭和初期まで使われていた木製の人力荷車 | 大八車 | だいはちぐるま |
| 1958年、東京・池袋で創業した定食屋チェーンです | 大戸屋 | おおとや |
| よくできた日本刀のことです | 業物 | わざもの |
| 浜崎あゆみらとの親交で有名な通販会社ピーチ・ジョンの創業者 | 野口美佳 | のぐちみか |
| 昔ながらの町にはこれがあります | 風情 | ふぜい |
| 機嫌が悪い人や愛想がない人によく見られます | 仏頂面 | ぶっちょうづら |
| お酒の好きな人がお酒を飲まない日のことです | 休肝日 | きゅうかんび |
| 婚約が成立した証として金銭や品物を取り交わすこと | 結納 | ゆいのう |
| 『ソビエト帝国の崩壊』などの著書で知られる評論家です | 小室直樹 | こむろなおき |
| 1980年に販売された、ロッテの空気を含んだチョコレート | 霧の浮舟 | きりのうきぶね |
| 頭の切れる人物の別名にもなっています | 剃刀 | かみそり |
| 将棋・囲碁に共通するタイトル戦です | 王座戦 | おうざせん |
| 将棋・囲碁に共通するタイトル戦です | 棋聖戦 | きせいせん |
| 木材に線を引くときに用いる大工道具 | 墨壺 | すみつぼ |
| 狭くて小さい様子です | 狭小 | きょうしょう |
| 耐えきれず怒りが爆発することを「○○○の緒が切れる」という? | 堪忍袋 | かんにんぶくろ |
| 1790年に創業された京都の老舗の製茶会社 | 福寿園 | ふくじゅえん |
| 『よろずのことに気をつけよ』で第57回江戸川乱歩賞を受賞 | 川瀬七緒 | かわせななお |
| 東京の寺井広樹さんは、これのプランナーとして活動しています | 離婚式 | りこんしき |
| 東京の佃煮メーカーが販売しているふりかけ | 錦松梅 | きんしょうばい |
| 砂浜でアサリやハマグリを探します | 潮干狩り | しおひがり |
| 新潟県南魚沼市に編集部を置く中高年向けの生活雑誌 | 自遊人 | じゆうじん |
| 囲碁で、最後まで打たずに勝負がつくことを何という? | 中押し | ちゅうおし |
| 会いたい時にあなたはいません | 遠恋 | えんれん |
| 何事も凶とされる日です | 仏滅 | ぶつめつ |
| 家計簿の項目の1つ | 光熱費 | こうねつひ |
| 「デジャ・ヴュ」と呼ばれる感覚を日本語ではこう称します | 既視感 | きしかん |
| 小説『ホテルローヤル』で第149回直木賞を受賞しました | 桜木紫乃 | さくらぎしの |
| 着物や布団の中に入れられます | 中綿 | なかわた |
| 物価などが際限なく高く値上がりすることをいいます | 青天井 | あおてんじょう |
| 2012年に第3回山田風太郎賞を受賞した冲方丁の小説です | 光圀伝 | みつくにでん |
| 「日本一まずい」と評判だった2010年に閉店したラーメン店です | 彦龍 | ひこりゅう |
| 「ウルトラマリン」とも呼ばれる青色の顔料 | 群青 | ぐんじょう |
| タルトで有名な、愛媛県松山市に本社を置く製菓会社 | 六時屋 | ろくじや |
| マンナンライフの人気商品です | 蒟蒻畑 | こんにゃくばたけ |
| 渋くて味わいのあるベテランのこと | 燻し銀 | いぶしぎん |
| ウバメガシを材料として作る良質な白炭です | 備長炭 | びんちょうずみ |
| 男ならつまらないこれはしないことです | 嫉妬 | しっと |
| カイコのまゆから作ります | 生糸 | きいと |
| 2012年にトヨタ自動車が発売したスポーツカーです | 86 | ハチロク |
| おかわり三杯目は遠慮気味 | 居候 | いそうろう |
| 全国に支店を広げているとんかつチェーンです | 和幸 | わこう |
| 名古屋名物・手羽先唐揚げのチェーン店です | 風来坊 | ふうらいぼう |
| 悔しがる時に踏みます | 地団駄 | じだんだ |
| タンスやようかんなどを数えるときに使う助数詞です | 棹 | さお |
| 妻として迎えること | 娶る | めとる |
| 人の話に合わせてうなづくこと | 相槌 | あいづち |
| 小説『共喰い』で第146回芥川賞を受賞しました | 田中慎弥 | たなかしんや |
| 小説『道化師の蝶』で第146回芥川賞を受賞しました | 円城塔 | えんじょうとう |
| 小説『蜩ノ記』で第146回直木賞を受賞しました | 葉室麟 | はむろりん |
| 「俺の小説の犯人は探せない」という意気込みが表れた筆名です | 佐賀潜 | さがせん |
| ミステリの作者が、読者に対して仕掛けるのは「○○トリック」? | 叙述 | じょじゅつ |
| 2011年のマイナビ女子オープンで初タイトルを獲得した女流棋士 | 上田初美 | うえだはつみ |
| 昔話の「瓜子姫」をさらってしまう悪鬼です | 天邪鬼 | あまのじゃく |
| 高いところの物を取るときなどに使います | 脚立 | きゃたつ |
| 炎天下で食べるのがオススメな森永製菓のタブレット菓子 | 塩添加 | えんてんか |
| 火事とともに「江戸の華」と呼ばれました | 喧嘩 | けんか |
| 『こちらあみ子』で第24回三島由紀夫賞を受賞した作家 | 今村夏子 | いまむらなつこ |
| 魚介類をこれで和えると「ぬた」になります | 辛子酢味噌 | からしすみそ |
| 将棋において最初に思いつく手のことです | 第一感 | だいいっかん |
| 鶴や亀の絵が描かれた袋に入っています | 千歳飴 | ちとせあめ |
| 鍋物の薬味や和え物の天盛りに用いる、白い縦切り | 白髪葱 | しらがねぎ |
| 植木などに水をかけるのに使う道具です | 如雨露 | じょうろ |
| 赤玉土や途上改良材を混ぜた、園芸用の土です | 培養土 | ばいようど |
| 将棋で、相手の駒を取らずに成ることです | 空成り | からなり |
| 2013年に映画化された首藤瓜於の推理小説 | 脳男 | のうおとこ |
| 幼い頃に結婚の約束をした相手をこう呼びます | 許婚 | いいなずけ |
| 子供向けの作品を多く残したSF作家です | 瀬川昌男 | せがわまさお |
| 汗、ムレ対策を施したトリンプの女性向け下着『○○○○!』? | 涼快です | りょうかいです |
| 契約などに定められている個々の条項のことです | 約款 | やっかん |
| 寒天にメレンゲを加えて固めた和菓子です | 淡雪 | あわゆき |
| 「普通に旨い」がコンセプトの鹿児島・原口酒造の芋焼酎です | 悠翠 | ゆうすい |
| 被写体に近づいて写真を撮影することです | 接写 | せっしゃ |
| 「ドモホルンリンクル」で有名な熊本県の企業は○○○製薬所? | 再春館 | さいしゅんかん |
| 揺れ動く社会の中で活躍する英雄的人物です | 風雲児 | ふううんじ |
| 気がついたら寝ていました | 転た寝 | うたたね |
| 水の蒸発を利用した簡易的な冷房装置です | 冷風扇 | れいふうせん |
| 暮らしにくいという意味です | 世知辛い | せちがらい |
| 雨傘などに施される水をはじく○○加工? | 撥水 | はっすい |
| 『天狗の面』『影の告発』などの作品を残した推理作家です | 土屋隆夫 | つちやたかお |
| 和菓子に使われる高級な砂糖です | 和三盆 | わさんぼん |
| 取るに足らないつまらない連中 | 有象無象 | うぞうむぞう |
| 2009年に刊行された、東野圭吾の「加賀恭一郎」シリーズの小説 | 新参者 | しんざんもの |
| 第126回直木賞候補作となった石田衣良の小説 | 娼年 | しょうねん |
| 以心伝心で息がぴったり合っていることです | 阿吽の呼吸 | あうんのこきゅう |
| 麻雀で、あと1枚必要な牌がくればあがることができる状態 | 聴牌 | テンパイ |
| 手紙を書いても返事がありません | 梨の礫 | なしのつぶて |
| 奈良県に本店があるラーメンチェーン店は○○ラーメン? | 彩華 | さいか |
| 水を飲んだり息を止めたりすれば治る、といわれます | 吃逆 | しゃっくり |
| 愛媛県を舞台にした天童荒太のミステリー小説 | 永遠の仔 | えいえんのこ |
| 本屋大賞と直木賞をダブル受賞した『蜜蜂と遠雷』の作者 | 恩田陸 | おんだりく |
| 奥さんに頭があがりません | 恐妻家 | きょうさいか |
| サントリーのウイスキーです | 角瓶 | かくびん |
| 式典や祝い事で割られます | 薬玉 | くすだま |
| リムーバーとも呼ばれるホッチキスの針を取る道具 | 除針器 | じょしんき |
| 『迷犬ルパン』シリーズなどの作品で知られる日本の作家です | 辻真先 | つじまさき |
| 将棋の禁じ手の1つです | 二歩 | にふ |
| 死者の霊前に供える金品のことです | 香典 | こうでん |
| 東京都内で展開しているステーキのチェーン店 | 加真呂 | かまろ |
| 昔から「食べると物忘れをする」と言われる野菜は? |
ミョウガ
| 5月5日の端午の節句のお供物にします |
かしわもち
| トッグルというボタンが特徴的な「○○○○コート」? |
ダッフル
| ラテン語で「走る人」という意味があるパソコンのキーです |
カーソル
| イソップ童話の「ウサギとカメ」で、スタートの合図をした動物 |
キツネ
| 麻雀で、一度もあがれない状態 |
やきとり
| 秋田県の名産です |
きりたんぽ
| 「火男」という言葉がなまって呼ばれるようになりました |
ひょっとこ
| スペイン語で「仮面」という意味がある化粧道具です |
マスカラ
| メキシコの州の名前に由来する犬種です |
チワワ
| 中部地方の郷土料理です |
ごへいもち
| この仙台名物のお餅に用いるのは何をすりつぶした餡? |
えだまめ
| 漢字で「石柏」と書く野菜です |
アスパラガス
| アニメで有名な犬種です |
ダルメシアン
| 朝鮮出兵のときに加藤清正が持ち帰りました |
セロリ
| 愛知県の名産です |
ひつまぶし
| 英語で「chinese cabbage」という野菜は? |
はくさい
| 1976年にスティーブ・ジョブズが設立したコンピュータ会社です |
APPLE
| ビリヤードで遊べるバーを「○○○バー」といいます |
プール
| 「Rのつかない月には食べるな」と言われる貝です |
オイスター
| ポルトガルの伝統の菓子が元になったといわれています |
エッグタルト
| 寿司屋で、この色の名前で呼ばれる調味料は? |
しょうゆ
| 北海道の郷土料理です |
いしかりなべ
| かつては水夫の寝具として使われていました |
ハンモック